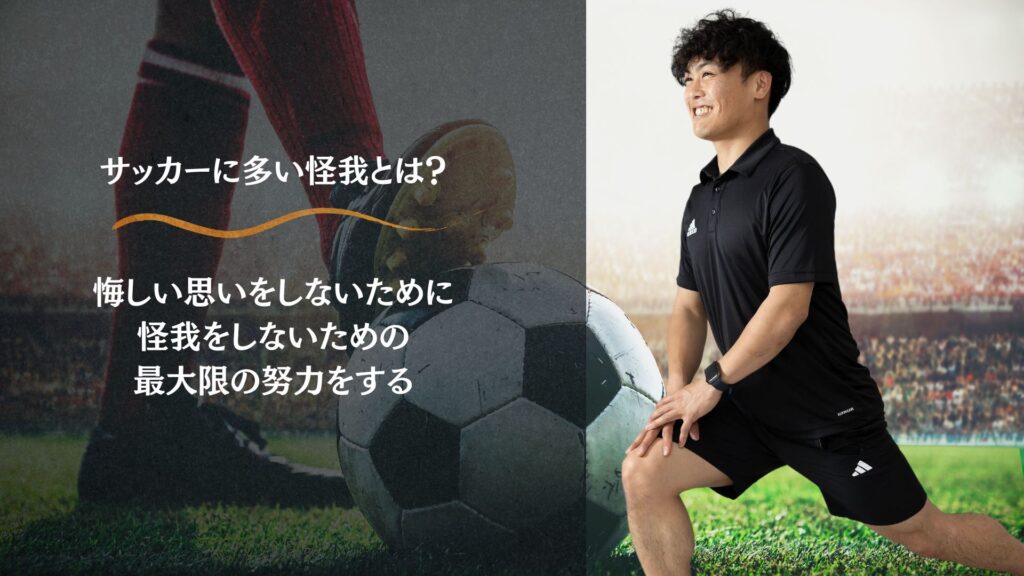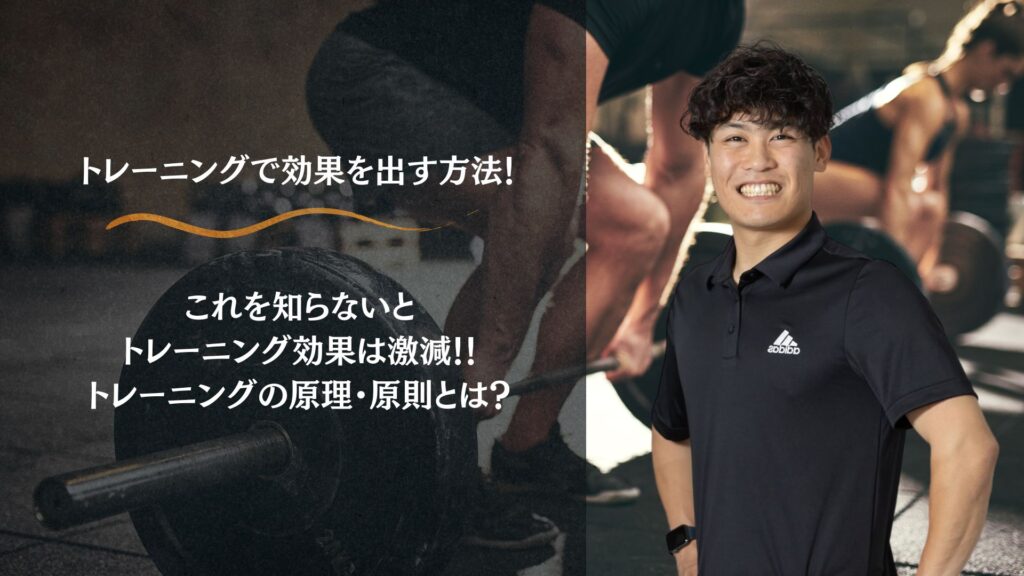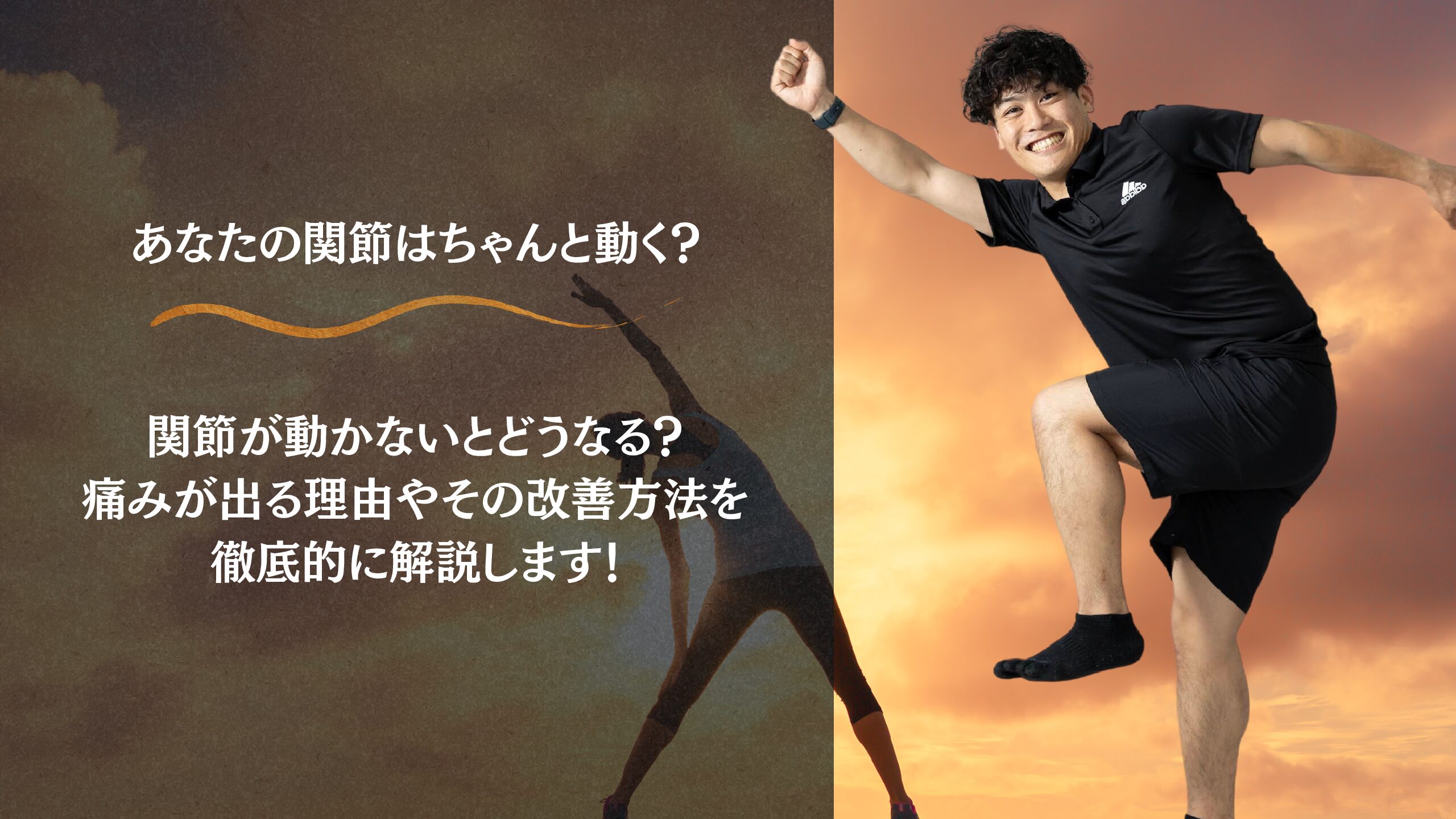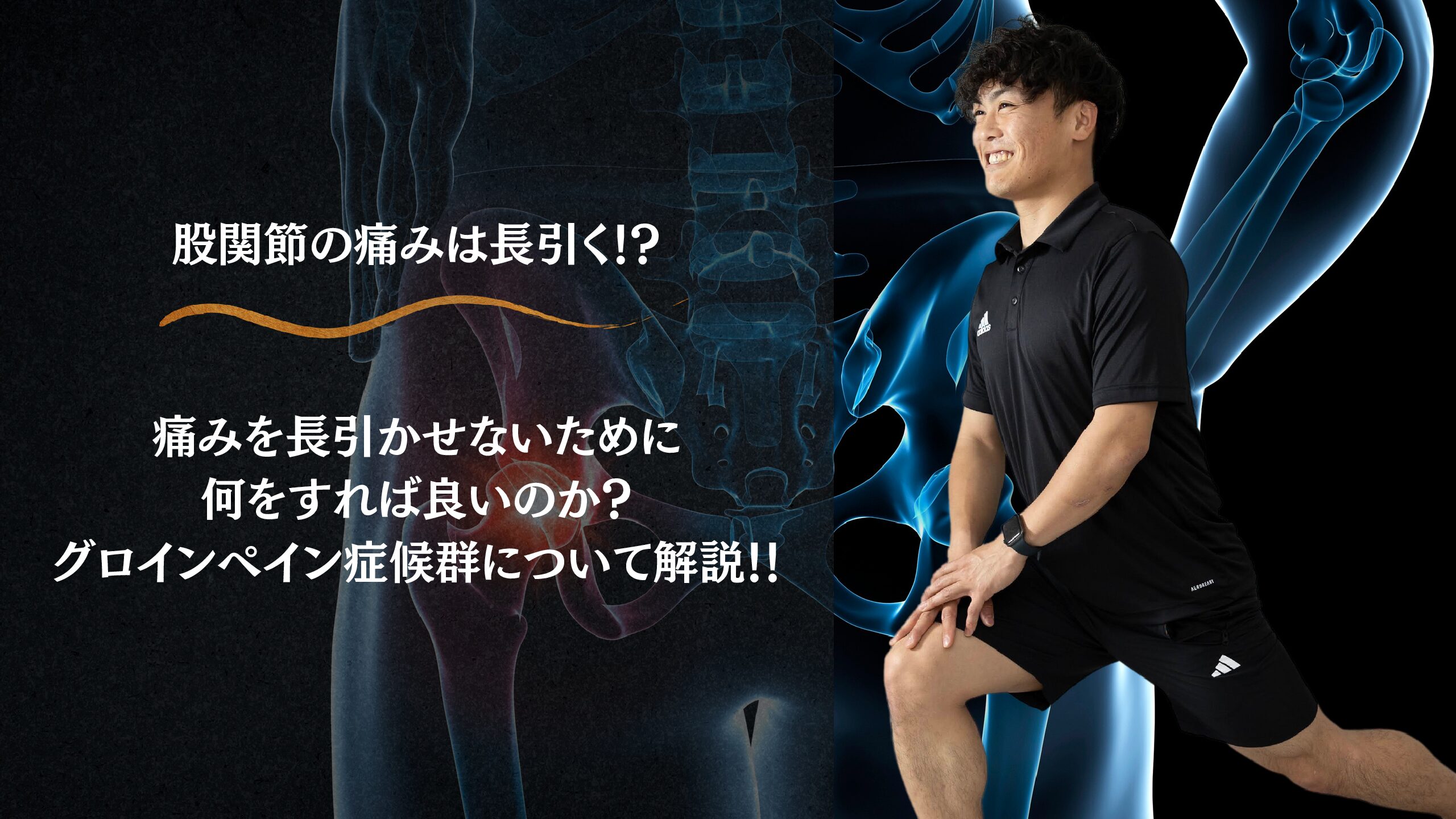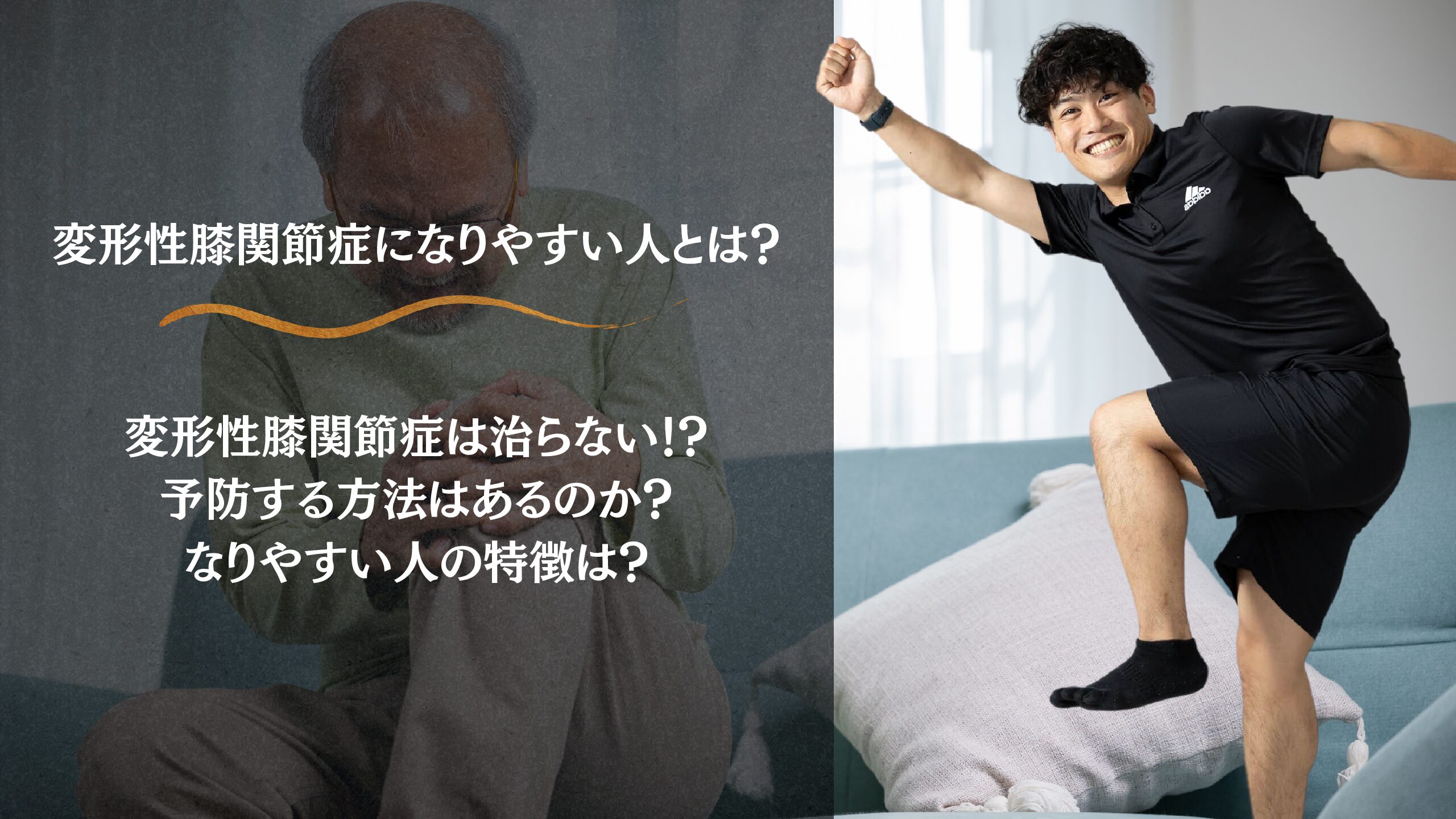【意外と怖い打撲】打撲で救急車を呼ぶ場合とは!?
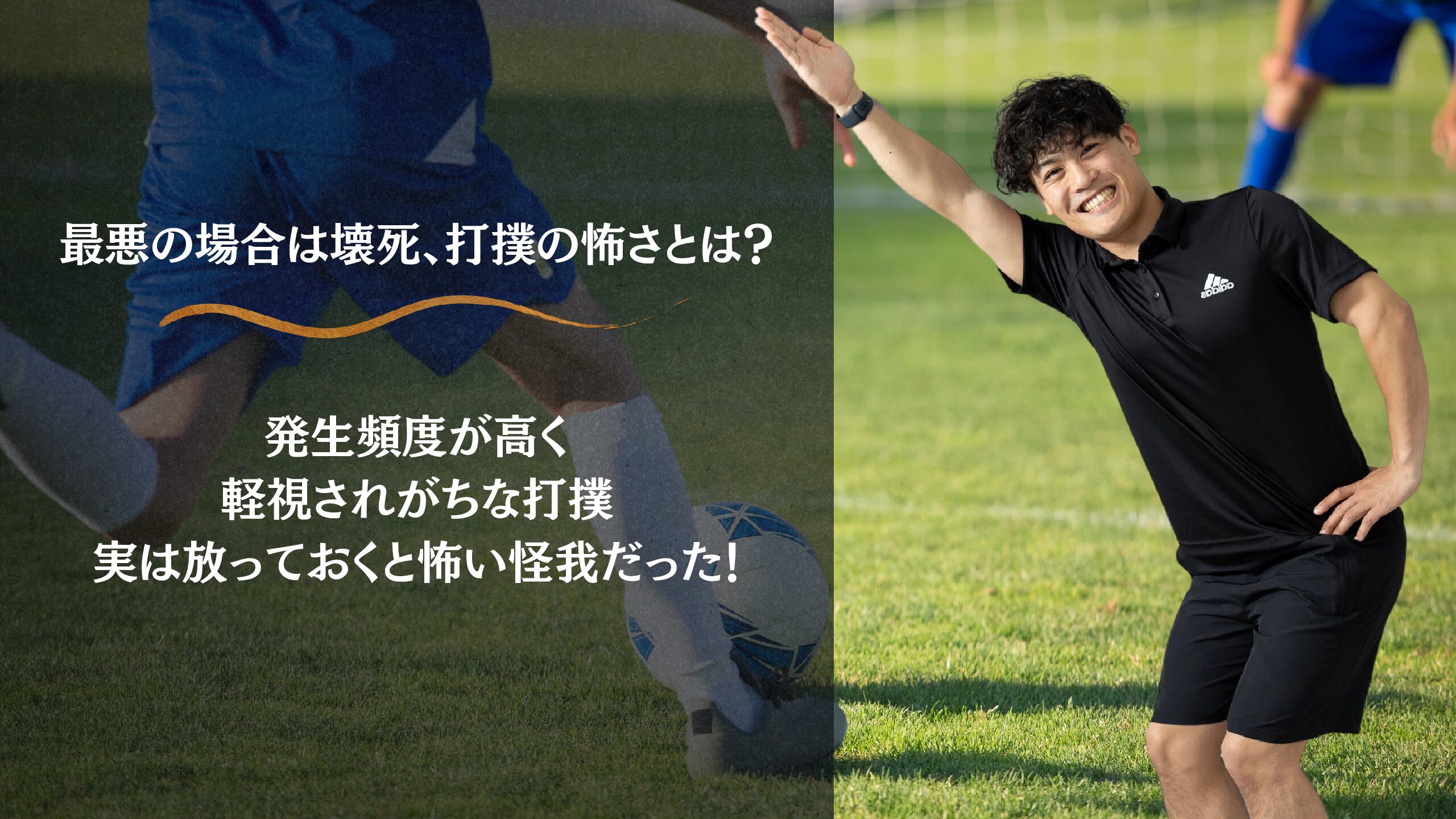
こんにちは!緑橋で整体院をしている【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。
「チャランポ」「とんこ」「モモカン」
みなさんは、これらの言葉を知っていますか?
少し地方によって、呼び方が変わりますが、これらは全て【打撲】のことです。
スポーツ現場では、よく使われる言葉で、発生頻度がとても高い怪我の一つになります。
打撲は、少し時間が経てば、症状が回復してしまうため、軽くみられがちですが、実は放置しておくと、取り返しのつかない後遺症を、残してしまうことになります。
今回は、そんな【打撲】について解説していきます。
打撲ってどんな怪我?
打撲とは、相手との接触やボールにぶつかったりするなどの強い衝撃によって、皮膚には傷口がないものの、皮下組織や筋肉が損傷している怪我のことを言います。
特に接触の多い、サッカーやラグビーなどのスポーツによく見られます。
これは、突発的に起こるため、予防がとても難しく、起こった時に対応していくしかありません。
ここからは、そんな打撲の時にみられる症状について解説していきます。
青タン(皮下出血)
打撲の場合、身体の中で出血が起こっている可能性があるので、皮下が青く黒くなってきます。
この皮下出血は放っておくと、筋肉の動きを制限し、関節可動域の低下を招く原因となります。
可動域の低下
筋肉に強い衝撃が加わると一時的に、痛みによる可動域の低下が起こります。
ただの打撲の場合は、ここで痛みがなくなるまで動かさず放置していると、痛みが引いてからも、可動域制限が残る可能性があるので、ゆっくりで良いので動かせる範囲で動かしていくことが重要になってきます。
骨化性筋炎
骨化性筋炎とは、筋肉が繰り返し炎症を起こすことで、筋肉の中に骨が形成されてしまうことを言います。
骨化性筋炎になってしまうと、強い痛みが長引いたり、関節の可動域制限が大きくなってしまいます。
また最悪の場合は手術になってしまうため、注意が必要です。
骨化性筋炎にならないようにするためには、打撲をしたその日にしっかり病院で診てもらい、痛みが引くまでは接触のあるプレーを控えるようにしましょう。
コンパートメント症候群
ここからは、少し怖いお話になります。
コンパートメント症候群とは、太もものように大きい筋肉がついている部位は、いくつかの区画(コンパートメント)に分けられています。
そしてその、区画の中で、打撲により炎症や皮下出血が起こると、それが原因で区画の中の内圧がどんどん上がってしまいます。
それにより、血管が圧迫され、血流が悪くなってしまいます。
また、血流だけでなく、神経や筋肉も圧迫してしまい、これは気づかず放っておくと、最悪の場合「壊死」してしまいます。
特徴的な症状として、皮膚がパツパツに張って少し光沢が出てくるくらいの腫脹があります。
この場合はすぐに救急車を呼んで、対処していきましょう。
このように打撲といえど、一つ判断を間違えると最悪の場合、壊死してしまいます。
僕も以前、勤めていた整骨院で、打撲で来院された患者様がコンパートメント症候群になっており、すぐに救急車を呼んだことがあります。
発生頻度の高い、比較的軽視されがちな、怪我ですが、最悪の場合を考えて、しっかり病院に行って、診てもらうようにしましょう。
どんな処置をしたら良いの?
では、打撲をした時にどんな処置をするのが、正解なのでしょうか?
スポーツ現場で発生頻度の高い怪我です。
監督やコーチなら、正しい処置の仕方を知って、対処できるようにしておきましょう。
H3 ピース&ラブ?
応急処理の今までの常識は「RICE処置」でした。
それが、POLICE処置に変わり、今では「PEACE &LOVE」に変わっています。
内容は以下の通りです。
✅Protection (保護)
→数日間は痛みの伴う運動は控える
✅Elevation (挙上)
→怪我をした部位を心臓より高く挙上する
✅Avoid Anti-inflammatories (抗炎症薬を避ける)
→怪我をした組織の回復を低下させる可能性があるため、抗炎症薬の服用は避ける
また、アイシングも避ける
✅Compression (圧迫)
→腫れを抑える
✅Education (教育)
→患者の状態に最も適した対処法を教え、過剰な医学的診療と薬の服用、そして不必要な受動的療法を避ける
✅Load (負荷)
→痛みと相談しながら、徐々に日常生活に戻る
✅Optimism (楽観思考)
→自信を持ち、前向きな考えを持つことで最適な回復が可能になる
✅Vascularisation (血流を増やす)
→痛みが伴わない有酸素運動を行うことで、負傷組織への血流を増やし、回復を促進させる
✅Exercise (運動)
→回復へ向けた積極的なアプローチをとることで、身体の動き、筋力を回復させる
まずはこれらをベースに現場では、対処していきましょう。
可能な範囲で動かす
これは、上記のPEACE &LOVEにも被ってきますが、動かせる範囲でゆっくり関節を動かしていきましょう。
太ももの打撲の場合、動かさずにじっとしていると、皮下出血が固まってしまい、それが原因で関節の可動域が制限されてしまいます。
関節可動域が狭くなってしまうと、それを元に戻すための治療が始まります。
この治療は、正常な範囲まで戻すのには時間がかかり、復帰が遅くなってしまうので、打撲の場合はゆっくり動かしていくのが、おすすめです。
また、これはコンパートメント症候群の予防にもなります。
打撲かどうかの判断が難しい場合は、すぐに病院に行くようにしましょう。
最後に
打撲は発生頻度が高い怪我ですが、意外と危険も隠れている怖い怪我です。
大した痛みじゃないし打撲だからといって、我慢せず、しっかり整骨院や整形外科などの医療機関を受診することをおすすめします。
また、打撲は筋力低下を伴う場合が多いので、痛みが引いた後は、しっかりリハビリをして、筋力を戻してから復帰しましょう。
もし、打撲をしてどんなトレーニングをしたら良いかわからない、という方は、緑橋にある整体院、カラダの説明書にご相談ください。
スポーツに特化した整骨院で勤務経験のあるトレーナーが、お客様にあったプランをご提案させていただきます。