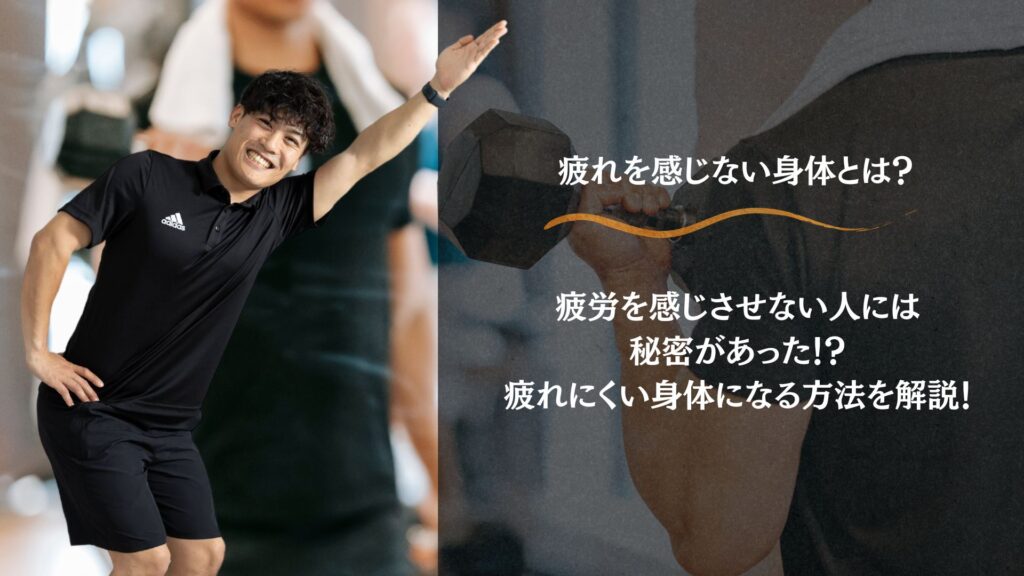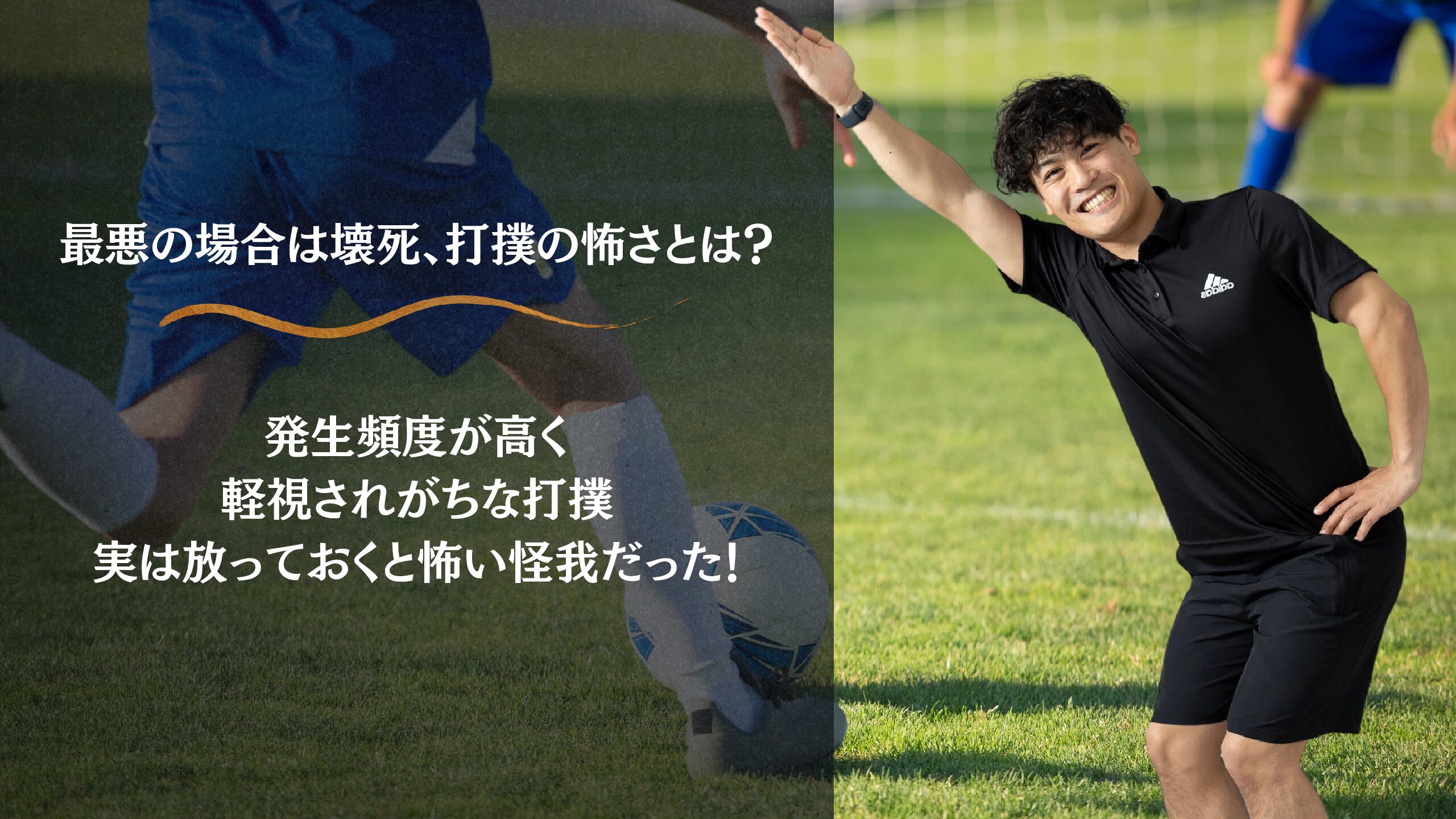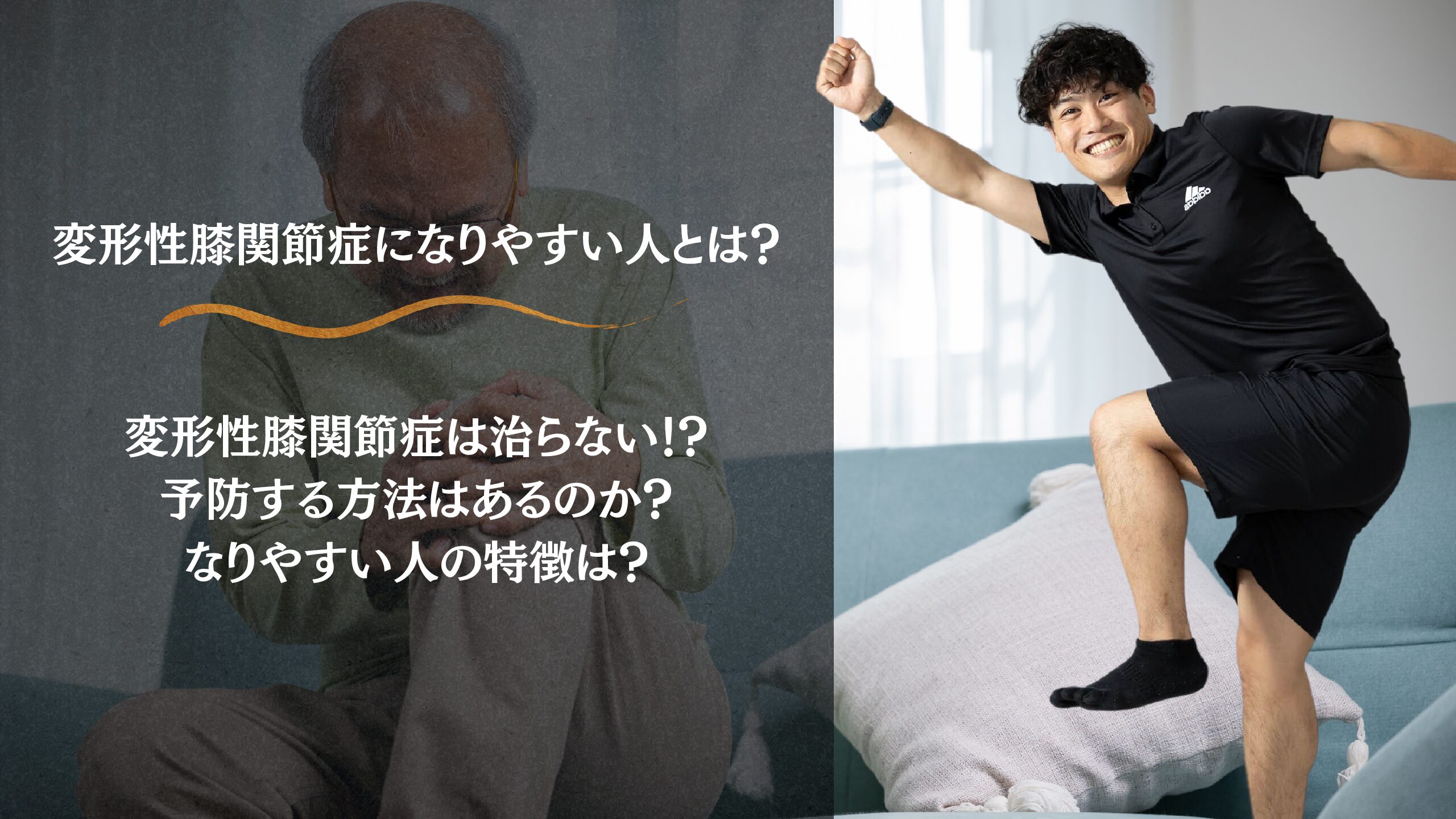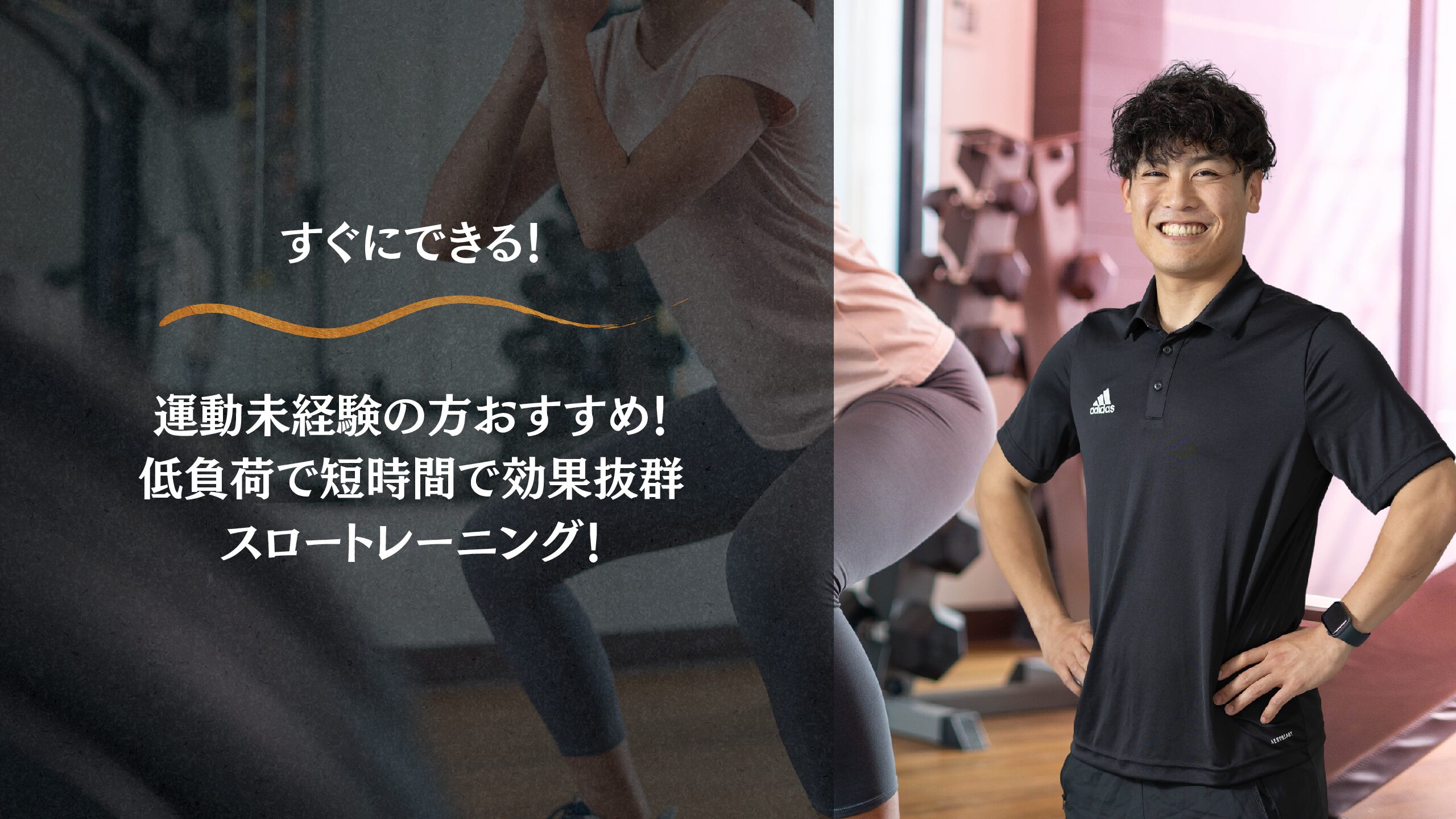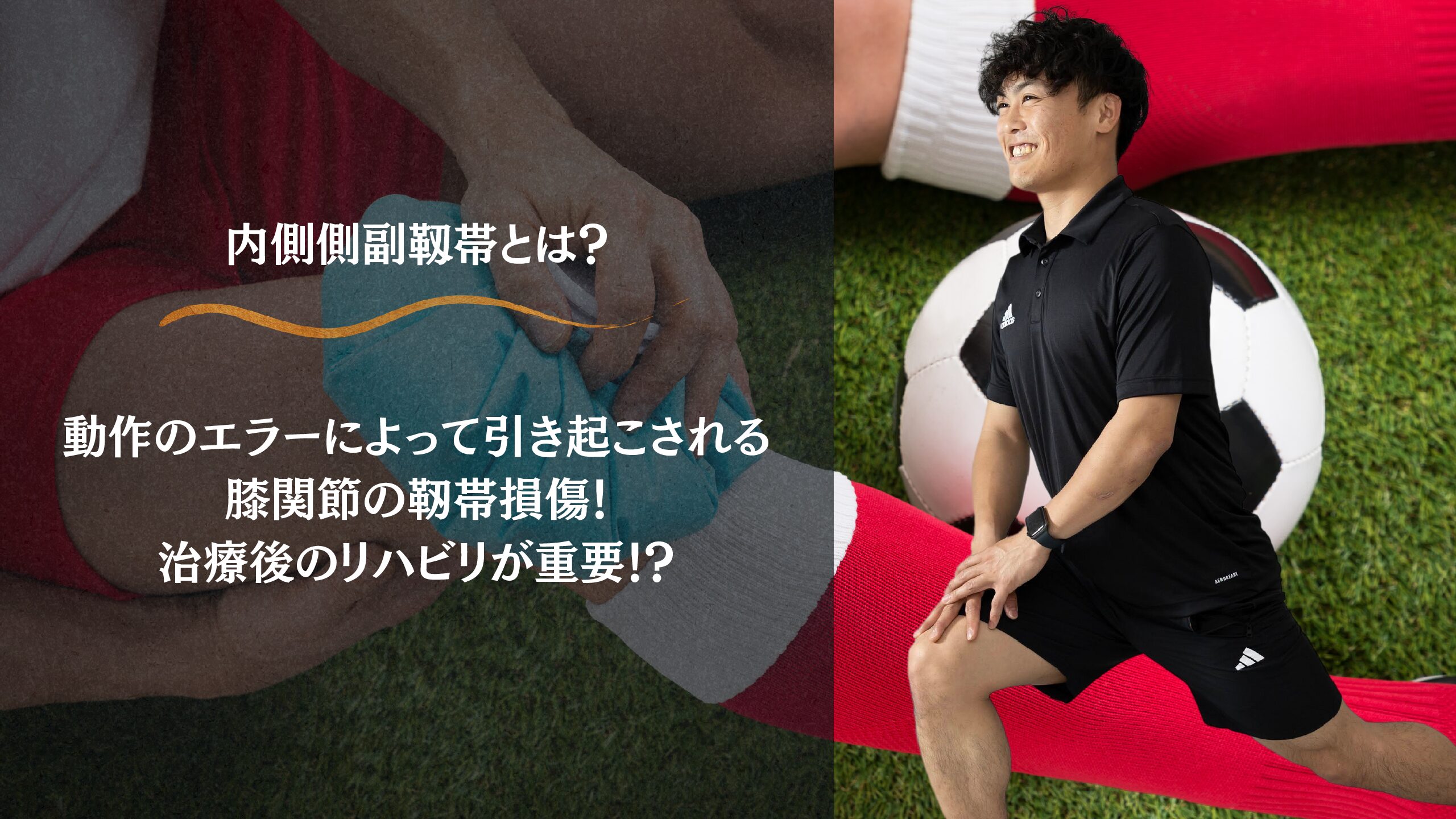【サッカーに多い怪我とは!?】今できる予防方法をお伝えします!
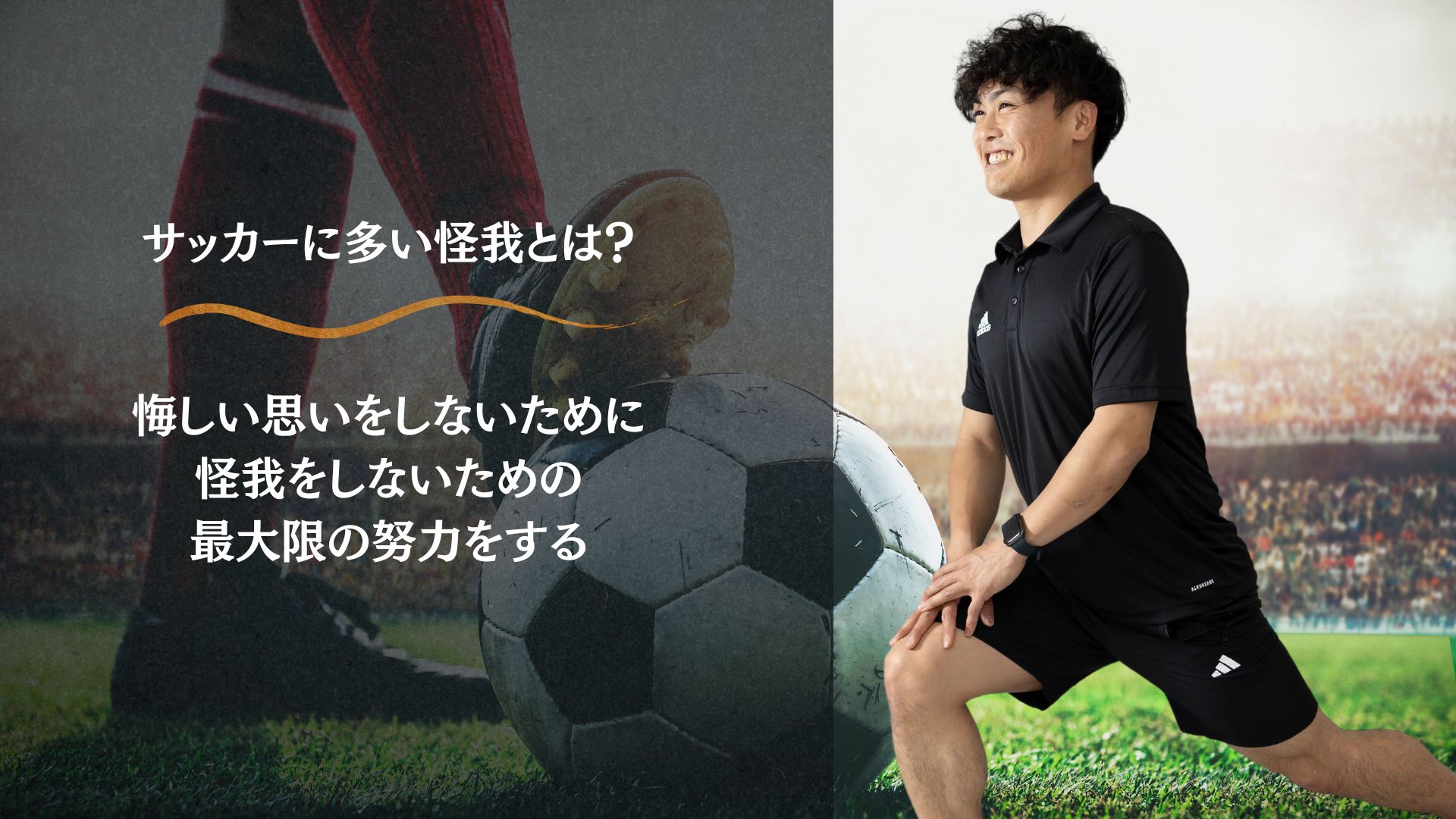
こんにちは!緑橋で整体院をしている【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。
今回は、サッカーで遭遇する頻度の高い、怪我について解説していきます。
サッカーの特徴は、小学生から大人まで、幅広い年代が楽しめるスポーツということです。
しかし、激しい接触プレーが多く、怪我が起きやすいのもサッカーの特徴と言えます。
特に中学校から高校生の、成長期の時期は、身体の成長に伴い怪我やプレー強度、練習強度が格段に高くなるため、怪我もしやすい時期になります。
整骨院で5年以上勤めて、最後の大会の前に怪我をして、100%の力でプレーができずに、悔しい思いをする選手をたくさんみてきました。
今回の記事を読んで、少しでもそんな思いをする選手が少なくなれば、幸いです。
サッカーに多い怪我とは?
サッカーは、他の競技に比べて、足を使うという特徴があります。
そのため、足に関する怪我が、必然的に多いスポーツです。
特に多いのは
✅足首の捻挫
✅太ももの裏の肉離れ
✅オスグッド・シュラッター病(成長痛)
これらになります。
ここからは、これらの怪我について解説していきます。
以外と怖い足首の捻挫
○概要
足首の捻挫は「足関節捻挫」と言われ、サッカー選手だけでなく、一般の方にも多く見られる怪我です。
方向転換や着地時などに、発生することの多い怪我になります。
○症状
痛み、腫れ、皮下出血、足首の可動域制限
○応急処置
現場で起きた場合は、とにかく安静にしてアイシングをしましょう。
また今以上にひどくならないように、固定をして、病院に行くことも必要です。
リハビリをしないと繰り返す肉離れ
○概要
サッカーでは、特にハムストリングスと呼ばれる、太ももの裏の筋肉が、肉離れを起こしやすい部位になります。
ダッシュやキックなど、急激な伸ばされるストレスがかかることで、筋肉が負荷に耐えられなくなり、肉離れは起こります。
○症状
鋭い痛み、皮下出血、可動域の制限などが診られます。
○応急処置
まずは安静にして、アイシングが基本です。
そのあとは、テーピングなどで固定して病院に向かいましょう。
中学生に多い膝の痛み
○概要
オスグッド・シュラッター病(成長痛)は、10歳から15歳の成長期に多くみられる、膝の怪我です。
脛骨粗面と呼ばれる、お皿の少し下の部分が筋肉に引っ張られ、剥がれてしまうことで起こる怪我です。
特に男子が多く、しっかり治療をしないと、膝の出っ張りが大人になっても残ってしまいます。
○症状
オスグッドの特徴的な症状は、運動中に痛みが出て、運動をやめてしばらくすると、痛みがひくことです。
そのため、痛みを我慢して、練習し悪化してしまうことも多くあります。
○治療
まずは安静にしてアイシングをしましょう。
痛みがある場合は、無理をせずに一旦休んで、病院に行くことをおすすめします。
怪我をしないために何をしたら良いの?
サッカーをしていると、必ずと言っていいほど、怪我をします。
それほど、サッカーに怪我はつきものです。
場合によっては、半年以上復帰できないこともあります。
ここからは、怪我をしないために、普段からできる予防方法をお伝えしていきます。
筋力をあげて足首や膝の安定感を高める
筋肉には、身体を動かす以外にも、関節を安定させてくれる役割があります。
足関節捻挫は、足関節の筋力が弱ってしまい、足首が不安定になることで、起こりやすくなる怪我です。
また、膝の靱帯や肉離れなどの怪我も、筋肉の限界を越える負荷が加わることで起こる怪我です。
そのため、普段から筋力トレーニングを欠かさず行うことで、怪我の予防に繋がります。
よく「小さい頃から筋トレをすると、身長が伸びない」と聞きますが、そんなことはありません。
身長はほとんどが、遺伝で決まります。
とはいえ、小学生や中学生から、重い器具を持ってスクワットやベンチプレスをするのは、おすすめしません。
プレートなどを持って行うと落下の際に怪我をしたり、バランスを失った時に転倒する危険性があるので、まずは自重でトレーニングを行っていきましょう。
自重でも十分身体は鍛えていけます。
何をしたら良いかわからない方は、ぜひ一度ご相談ください。
緑橋駅にある、カラダの説明書では国家資格を持ったトレーナーが、お客様にあったトレーニングプランを提案させていただきます。
柔軟性をあげて関節の可動域を増やす
学生年代のサッカー選手を見てて多いのは、柔軟性の低い選手です。
前屈で、指が地面につかない子もたくさんいます。
柔軟性が低いことで、起きやすい怪我は肉離れやオスグッドです。
肉離れは、筋肉が必要以上に伸ばされることで、起こります。
またオスグッドでは、筋肉の柔軟性が低下することにより、脛骨粗面にかかる牽引力が強くなり、脛骨粗面が剥がれてオスグッドになってしまいます。
そのため、日頃からストレッチなどをして筋肉の柔軟性を高めておくことはとても重要です。
ストレッチの方法は、お風呂から出た後や寝る前などに、20秒〜30秒ほどゆっくり伸ばしてください。
いつもより動きが鈍くなる疲労
怪我を予防する上で、疲労回復は欠かせません。
疲労が溜まっていると、頭では普段と同じようにプレーをしていても、身体がついてこない状態になってしまいます。
いつもなら、一歩早く着くのに、届かないから足を無理やり伸ばす。
その結果、筋肉が過度に伸ばされ、肉離れになる。
もしくは、シュートを打った時に、軸足に力が入らず、転倒する。
このように、普段の動きとは、僅かにズレが生じ、いつもよりも怪我のリスクが高くなってしまいます。
また、オーバーユース(使いすぎ)による、怪我のリスクも高くなります。
筋肉や骨などは、繰り返しのストレスにより、怪我起こりやすくなります。
過度な、練習は筋肉や靱帯、関節にかかる負担を大きくし、怪我の原因に繋がってしまいます。
疲労を早く解消するためにも、睡眠や食事、普段のケアは念入りに時間をかけて行いましょう。
最後に
怪我をしてしまうと、1ヶ月や長いと半年以上、復帰できなくなってしまいます。
この間もライバルたちは、成長していき、ポジションを取られてしまうかもしれません。
また、最後の試合に間に合わない、ということもあります。
これは日頃、選手たちにも伝えていますが、怪我はどれだけ予防していても、絶対にならないとは言えません。
ただ、最大限のできることもしていないのに、怪我をして半年以上プレーできなくなるのは、とても勿体無いことです。
筋トレやストレッチで、何をしたら良いかわからない方は、ぜひ一度、緑橋駅にあるカラダの説明書にご相談ください。
あなたにあった、トレーニングやストレッチ方法、改善しないといけない場所を細かくお伝えいたします。
最大限の努力をして、怪我の少ない選手人生を送りましょう。