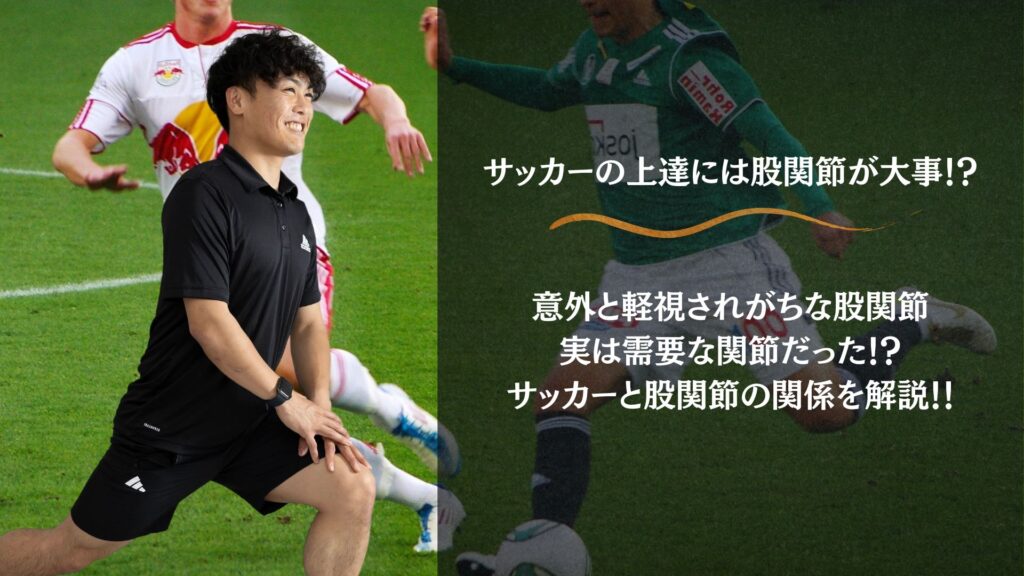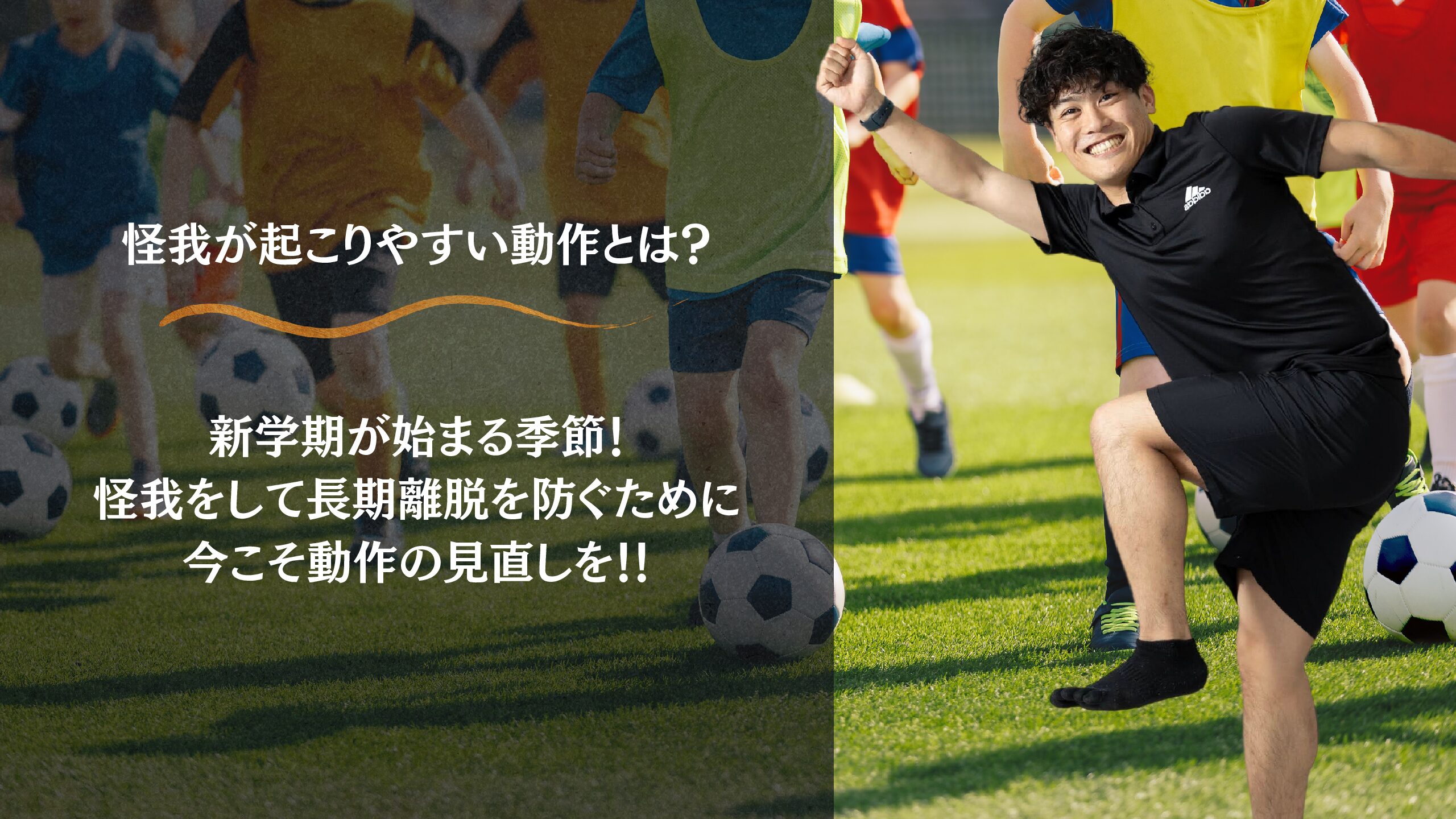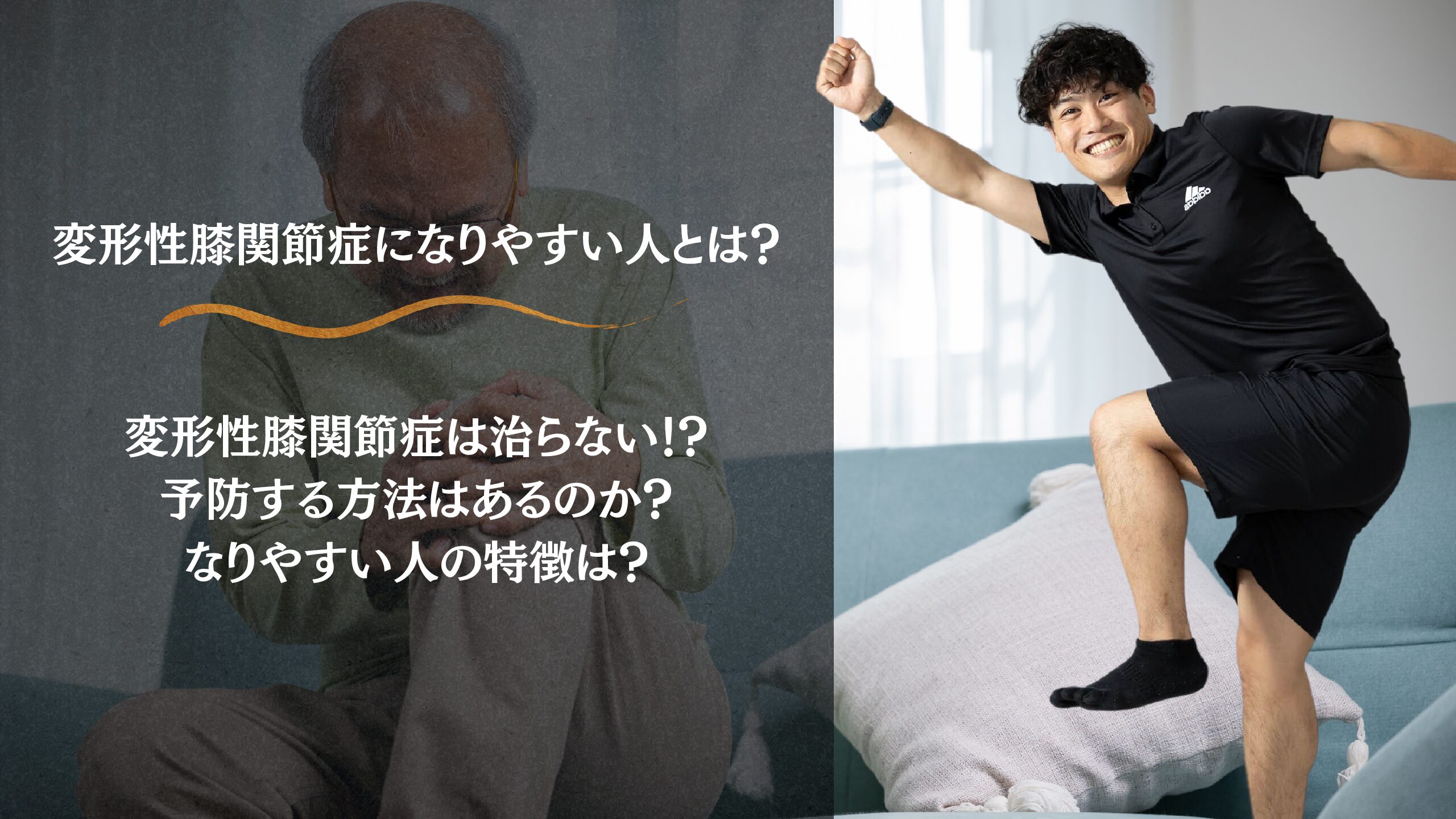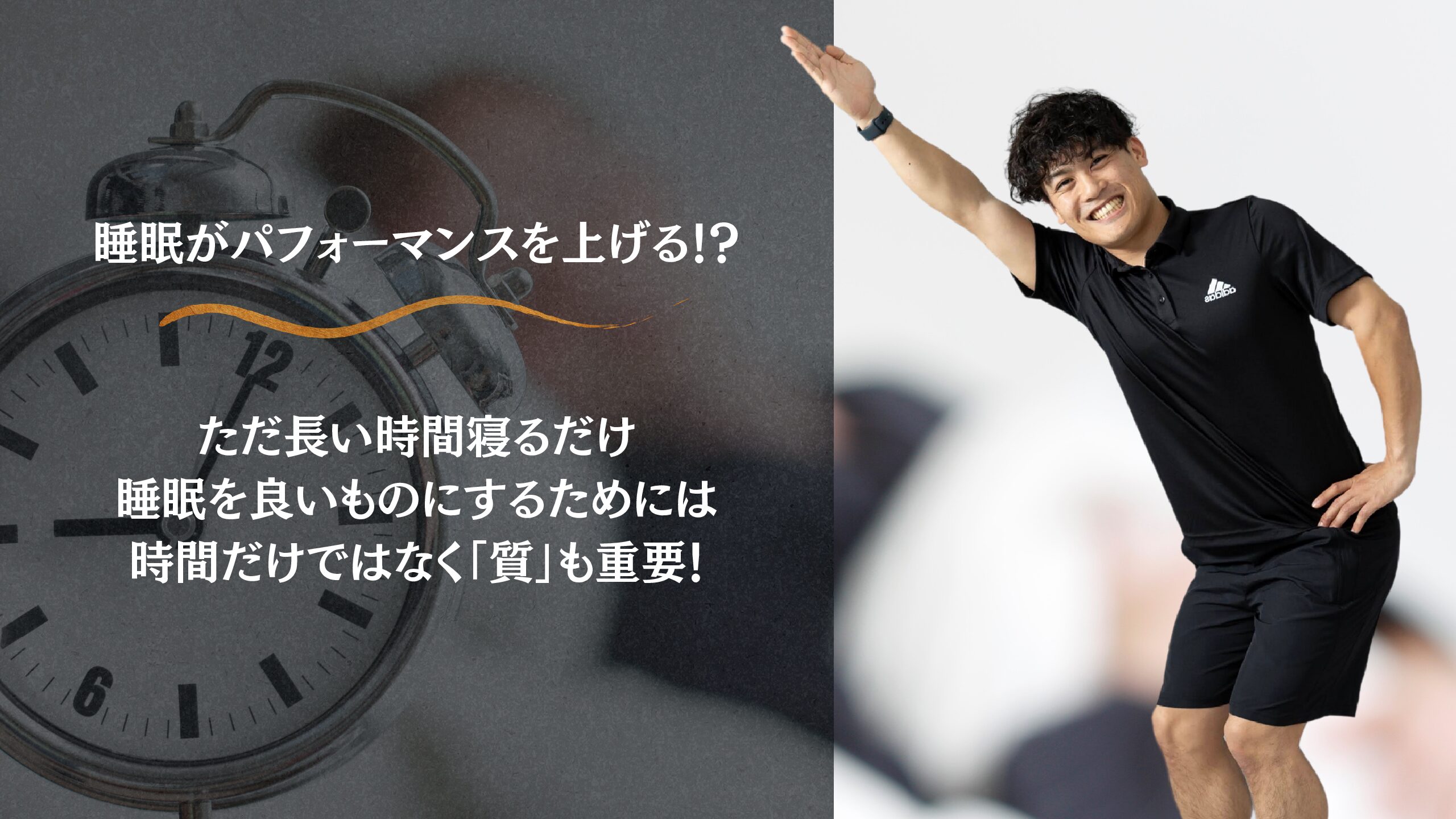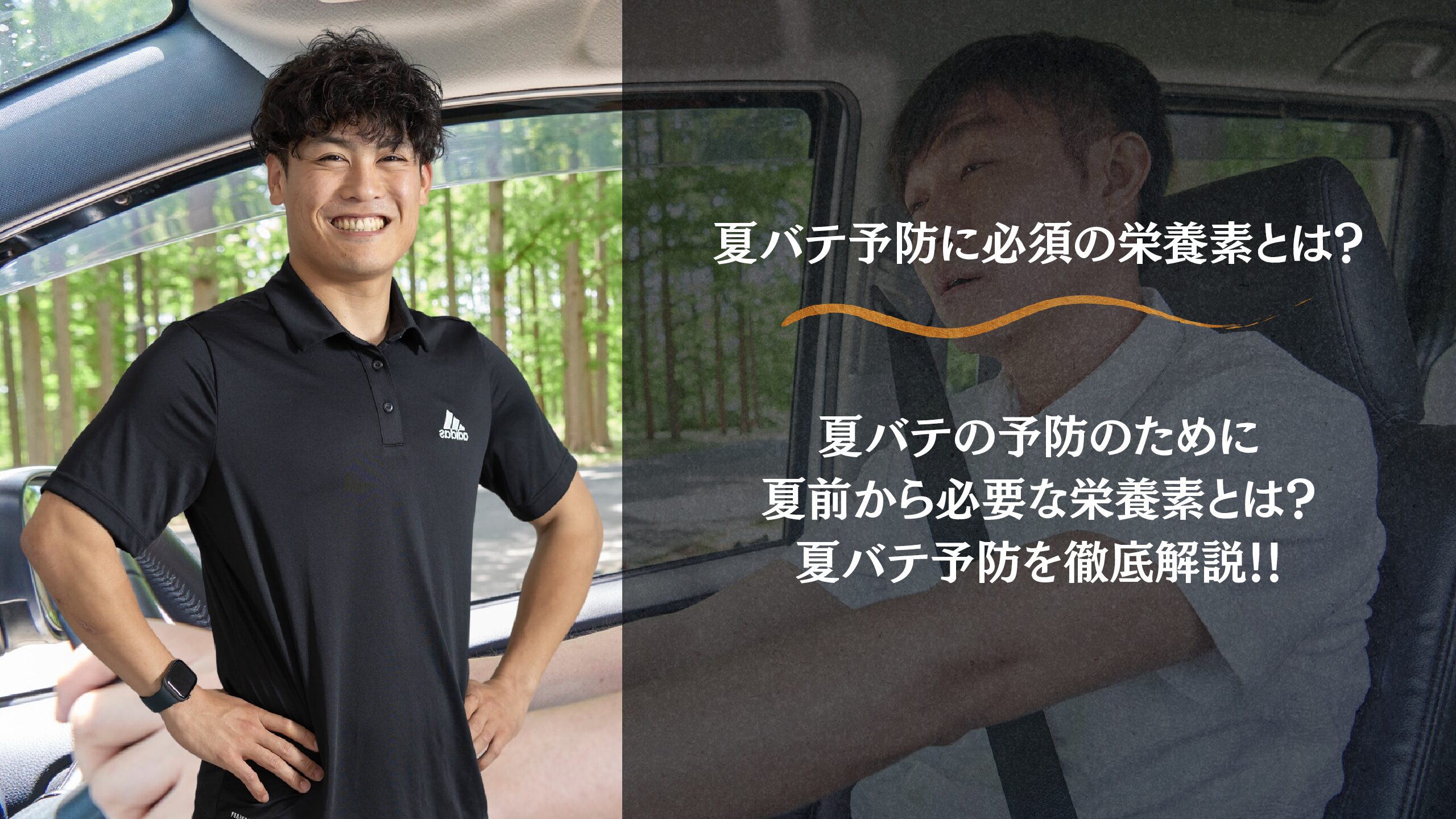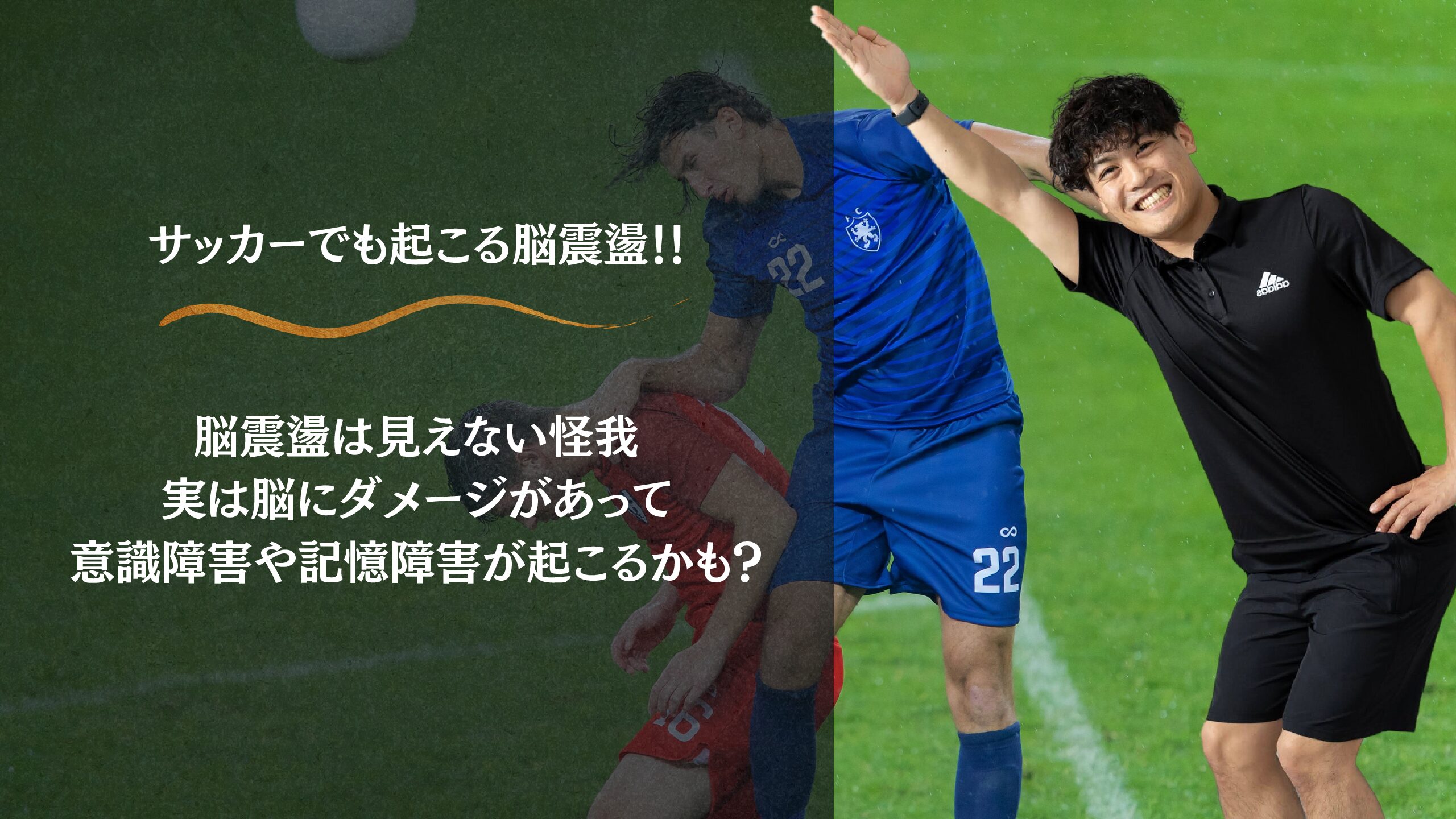【サッカーと成長痛の関係とは?】成長期の体を守るために知っておきたいこと
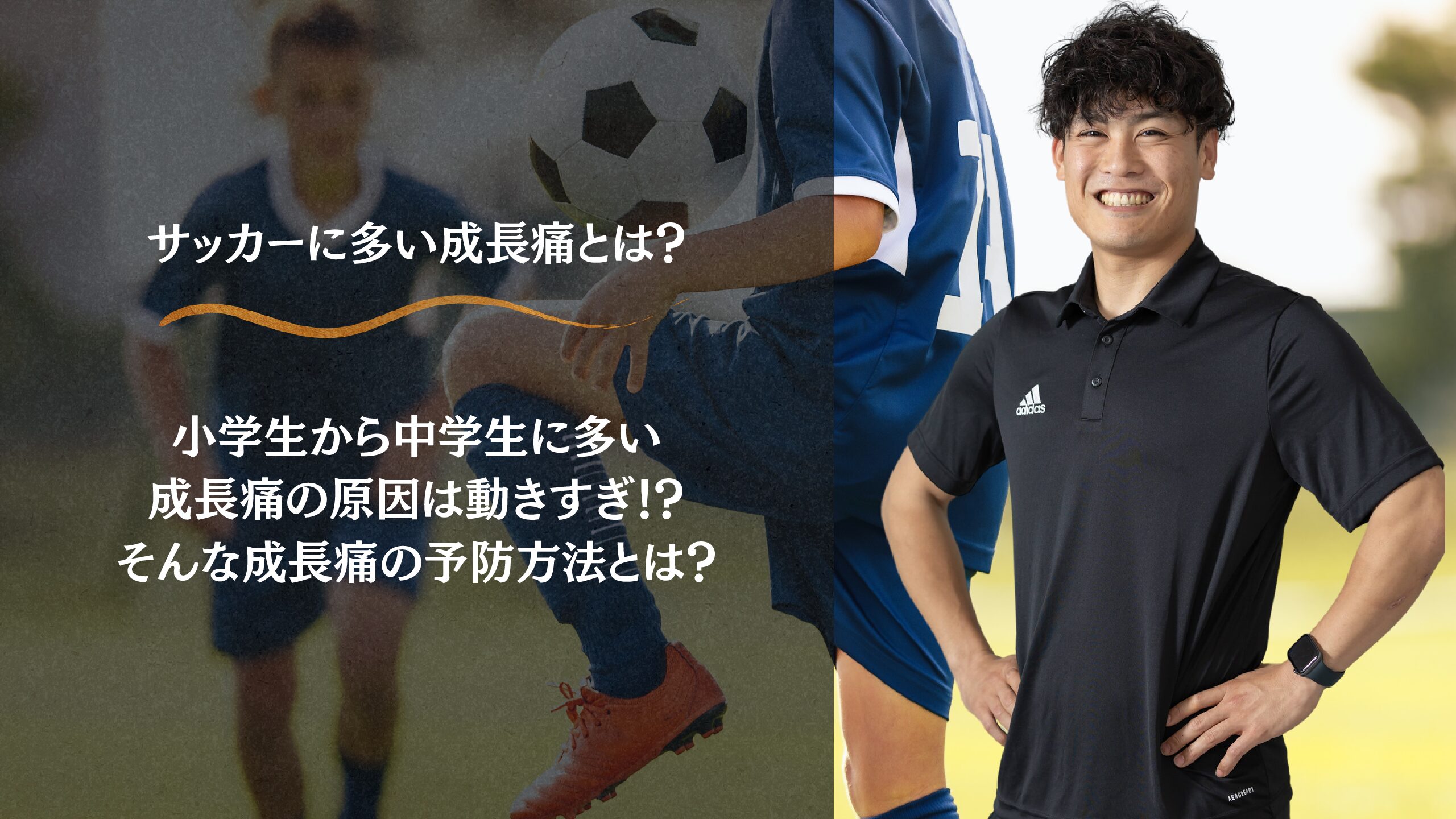
大阪メトロ緑橋駅から徒歩1分
整体とパーソナルトレーニングで痛みや疲労の改善を目指す
カラダの説明書 緑橋の春藤謙介です。
サッカーに打ち込んでいる小学生〜中学生の選手に多く見られる怪我が「成長痛」です。
ある日突然「膝が痛い」「かかとが痛くて走れない」などの訴えがあり、焦った経験をお持ちの親御さんも多いのではないでしょうか?
成長痛は「放っておいても治る」とされることもありますが、サッカー選手にとっては正しい知識と対応が非常に重要です。
痛みを無視して練習を続けると、長期離脱や将来的な怪我につながることもあるからです。
本記事では、「成長痛とは何か?」「なぜサッカー選手に多いのか?」「どう対応すれば良いか?」を丁寧に解説していきます。

成長痛とは何か?その正体を知る
そもそも成長痛とはなんでしょうか?
成長痛といってもいくつか種類があります。
成長痛=骨の痛みではない
「成長期の痛み=骨が伸びて痛い」と誤解されることもありますが、実際には「筋肉と骨のバランスの崩れ」による痛みが大半です。
骨は急速に伸びますが、筋肉や腱はそれに追いつかず、引っ張られるような状態になることで、関節付近に痛みを感じるのです。
つまり、成長痛は成長そのものによるものではなく、“成長に伴う筋骨格系のアンバランス”によって起きています。
オスグッド・セーバー病などの代表例
サッカー選手に特に多い成長痛として有名なのが、以下の2つです。
・オスグッド病:膝のお皿の下(脛骨粗面)が痛くなる。ジャンプやダッシュで悪化。
・セーバー病(踵骨骨端症):かかとの骨が痛む。特にスパイクや固いグラウンドでの練習後に強く出やすい。
これらはいずれも「繰り返しの負荷」が原因となるため、練習内容や身体の使い方に注意が必要です。
一過性の痛みと見過ごせないサイン
成長痛は基本的に一過性のもので、数ヶ月〜1年ほどで自然におさまることが多いです。
しかし、「痛みが長引く」「夜間にも強く痛む」「片足だけ異常に痛む」などの症状がある場合は、成長痛ではなく別の整形外科的疾患の可能性もあります。
そのため、放置せずに専門家の評価を受けることが大切になります。

サッカー選手に成長痛が多い理由と対策
サッカー選手には、成長痛を抱える選手がたくさんいます。
それはなぜしょうか?
ここからはそんな疑問について解説していきます。
キック動作とジャンプ動作が負担になる
サッカーは、キックやジャンプ、方向転換といった瞬発系の動きが多く、膝やかかとへの負担が大きいスポーツです。
特に「ボールを蹴る」という動作は、大腿四頭筋(太もも前)の収縮が強く働き、脛骨粗面(オスグッドの痛む場所)を繰り返し引っ張ります。
ジャンプや急停止を繰り返すトレーニングが多いほど、負荷は蓄積されていきます。
硬いグラウンド・スパイクの影響
土のグラウンドや人工芝は、クッション性が低いため、かかとや膝への衝撃を逃がしにくく、セーバー病やオスグッドの発症リスクが高くなります。
また、スパイクのソールが固いと足底の筋肉が硬直しやすく、アーチの崩れやアキレス腱周囲の緊張が高まることで、踵への牽引力が強くなってしまいます。
柔軟性の不足とウォーミングアップ不足
特に成長期の選手では、「筋肉の柔軟性が追いつかない」ことが痛みの最大の引き金になります。
ストレッチやモビリティエクササイズの習慣が少ないまま、いきなり全力プレーを行うと、筋肉が急激に引き伸ばされ、付着部に炎症が起こります。
「柔軟性を保つ」「準備運動を丁寧に行う」ことで、痛みの予防に大きくつながります。

成長痛を悪化させないために今できること
では成長痛を悪化させないためには何が必要なのでしょうか?
練習量の調整と休養の確保
痛みがあるときは、無理にプレーを続けることは避けるべきです。
「軽く走れるから大丈夫」と思っていても、キックやストップの動作で悪化することは多くあります。
成長痛は「使いすぎ」によって生じるため、休むことは治療そのものです。
休養を恐れず、1日〜数週間の完全オフを取る勇気も大切です。
ストレッチとフォーム改善
特に太ももの前(大腿四頭筋)やふくらはぎ、足裏の筋肉は毎日のストレッチが重要です。
身体のバランスが崩れている場合は、フォームの指導やコンディショニングも併用すると良いでしょう。
片足立ちのバランスや骨盤の傾き、歩き方の癖などから成長痛が悪化しているケースもあります。
専門家の評価とリハビリサポート
自己判断では痛みの原因が見えにくいことも多く、結果として長引かせてしまうこともあります。
整体やスポーツトレーナー、整形外科など、成長痛に詳しい専門家に相談し、的確な対応を受けることが回復の近道です。
リハビリの段階でも、単にストレッチをするだけでなく「どの筋肉が原因で、どの動作が負担になっているか?」まで分析することが大切です。
最後に
成長痛はサッカーを頑張る子どもたちにとって、避けては通れない体の変化の一つです。
しかし、適切な知識と対応を持つことで、「痛みを我慢しながらプレーする」状態から、「正しく休んで、早く回復する」状態へと変えていくことができます。
・成長痛は筋肉と骨のアンバランスによって起こる
・サッカーの繰り返し動作は、特定の部位に負担をかけやすい
・痛みが出たら、練習量を減らし、柔軟性とフォームの見直しを
未来あるジュニアアスリートの体を守るためにも、保護者や指導者の理解と協力が欠かせません。
「今だけでなく、将来もサッカーを楽しめる体づくり」を一緒に目指していきましょう。