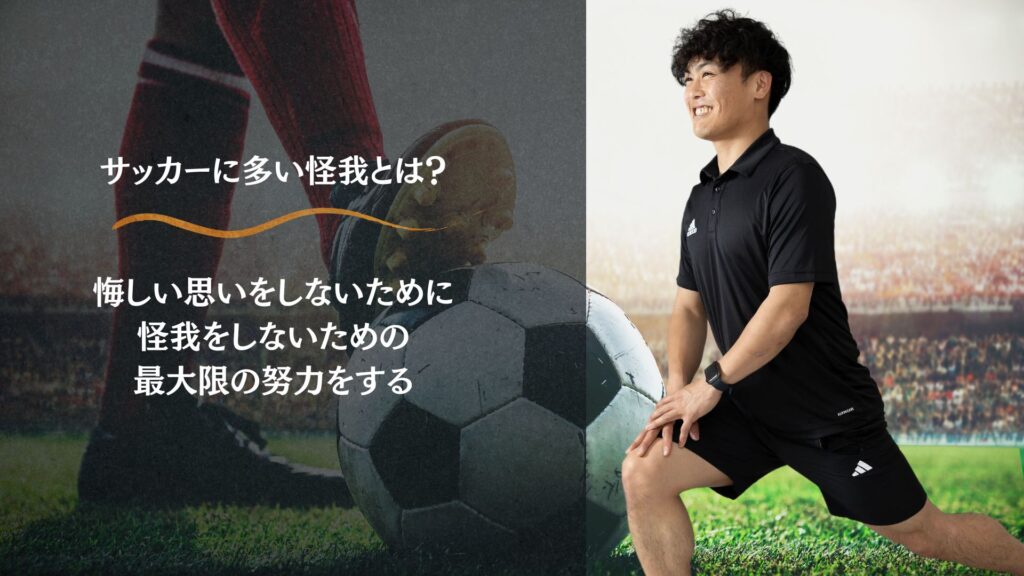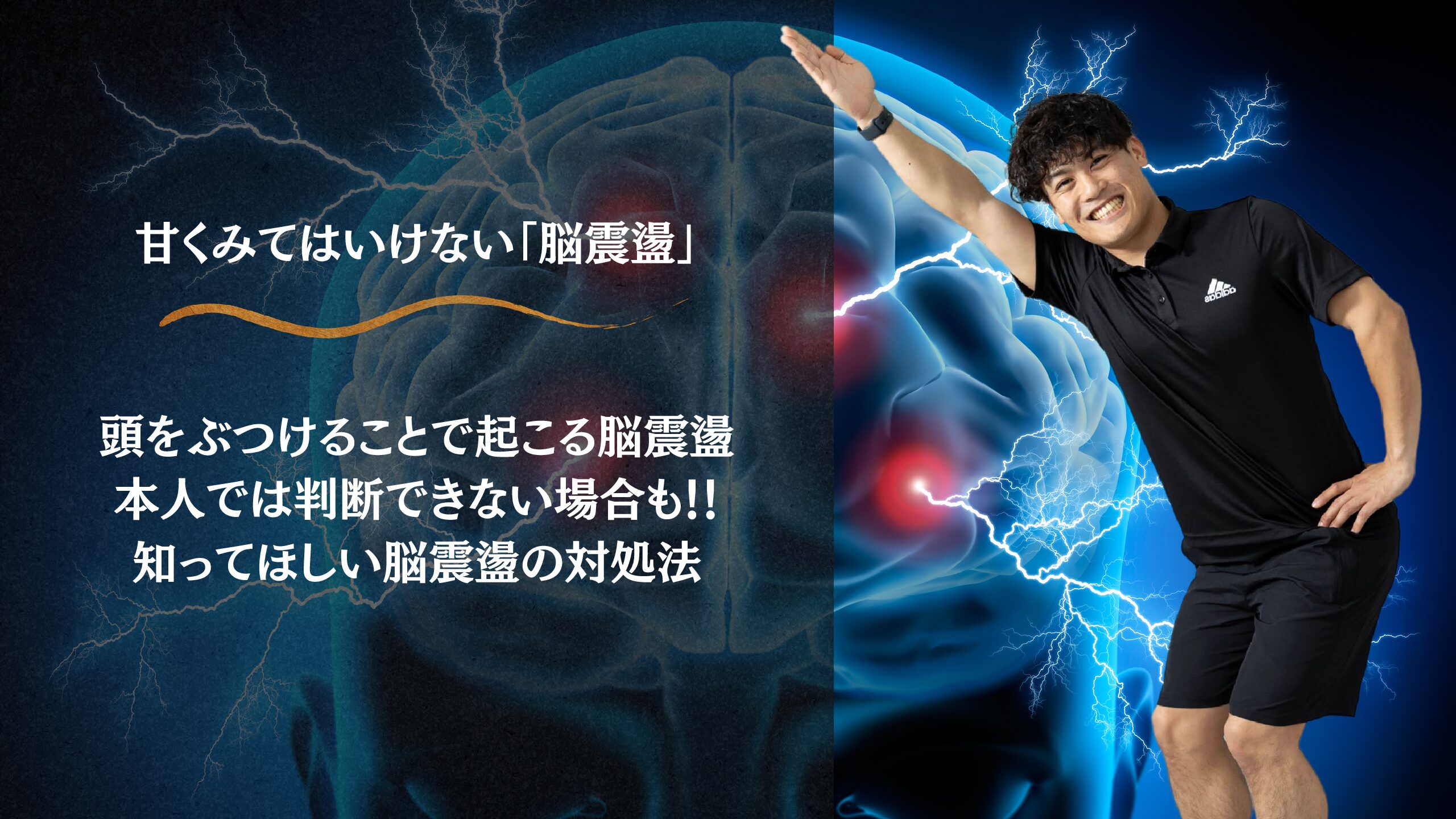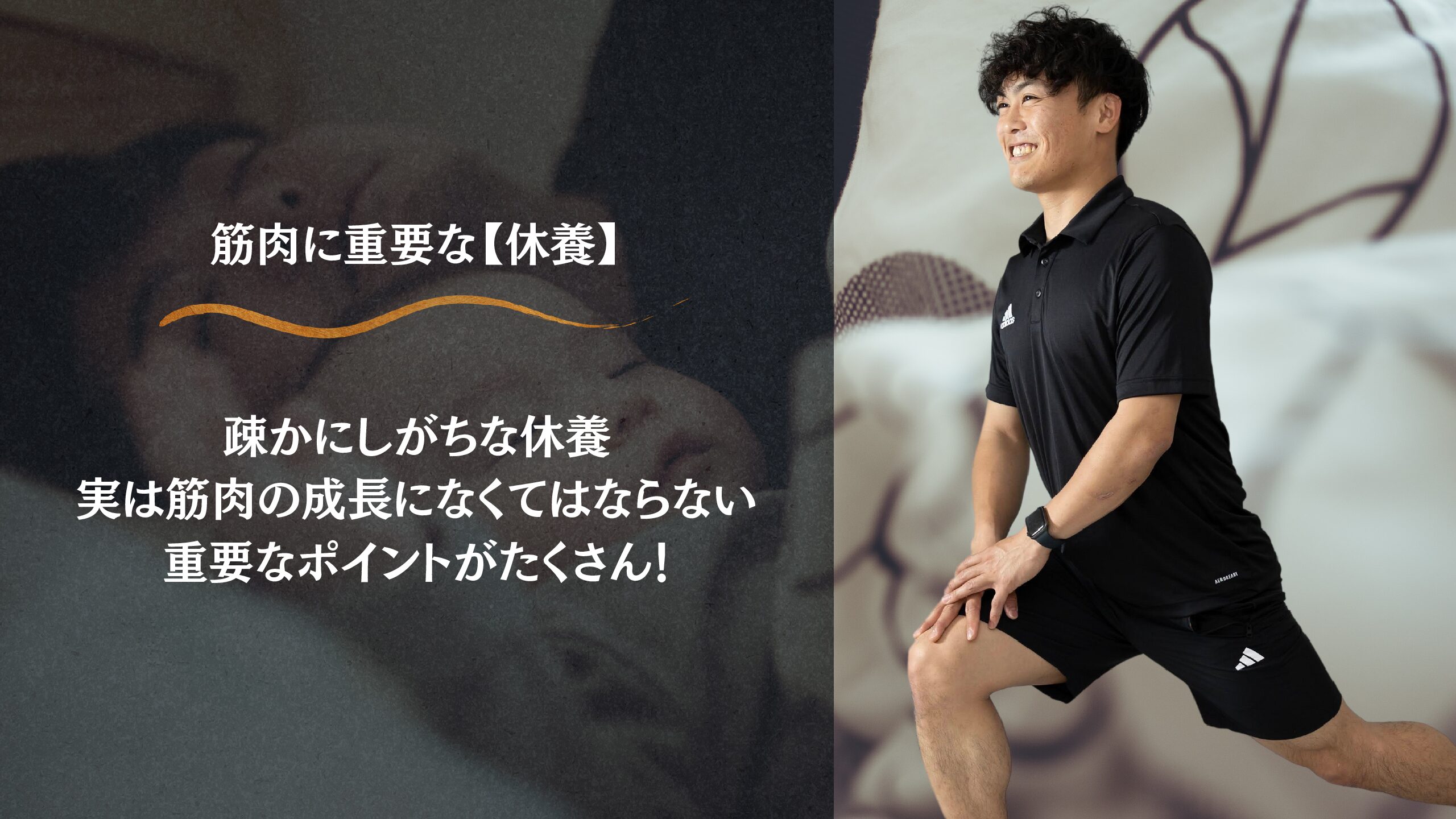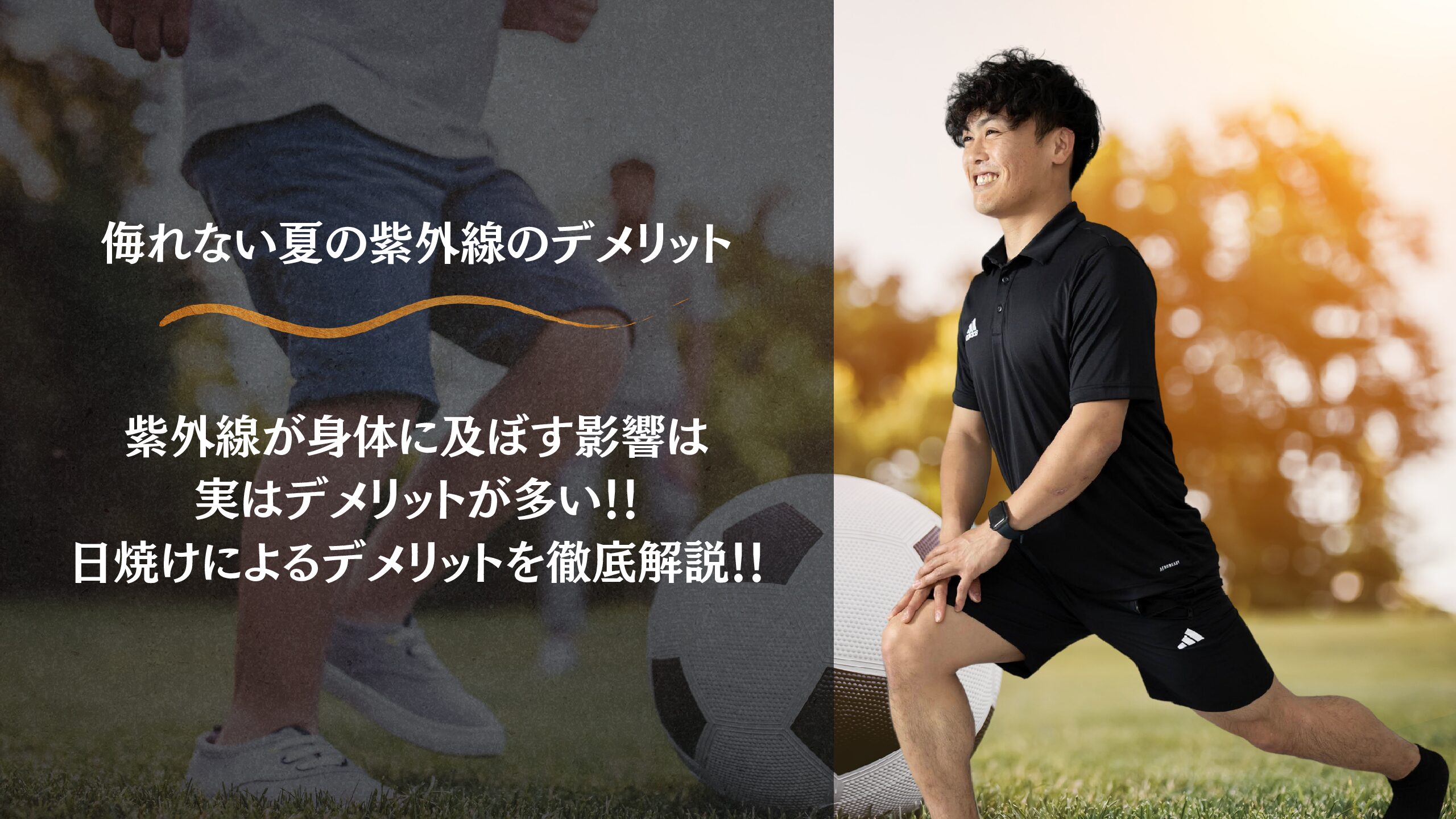【サッカーと腰椎分離症】若い選手に多い腰痛の正体とは?
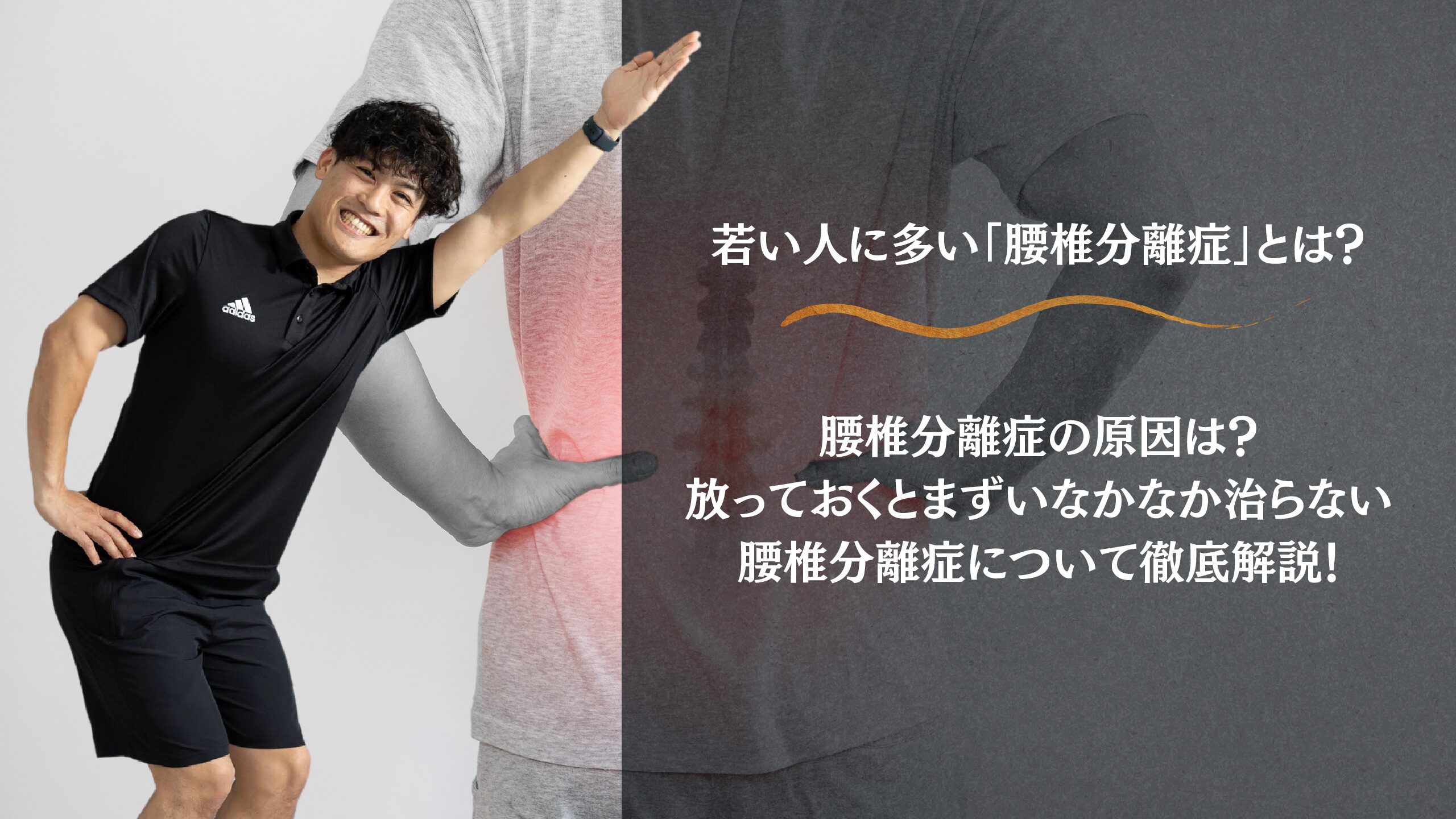
大阪メトロ緑橋駅から徒歩1分
整体とパーソナルトレーニングで痛みや疲労の改善をサポートする
カラダの説明書 緑橋の春藤謙介です。
サッカー選手に多い悩みのひとつが「腰の痛み」です。
中学生、高校生の男子選手に特に多く見られる腰の痛みの原因のひとつに「腰椎分離症(ようついぶんりしょう)」があります。
腰椎分離症は、放置すると将来的な慢性腰痛やパフォーマンス低下につながる可能性もあるため、早期の対応が重要です。
この記事では、「腰椎分離症とは何か?」「なぜサッカー選手に多いのか?」「どうすれば予防・改善できるのか?」という点を解説していきます。
サッカー選手に多い腰椎分離症とは?
腰椎分離症は、成長期の選手に特に多いスポーツ障害のひとつです。
腰椎分離症とは?
腰椎分離症とは、腰の骨(腰椎)の後方にある「椎弓」という部分にひびが入る、または骨が完全に分離してしまう状態を指します。
特に5番目の腰椎(L5)に起こりやすいとされています。
この骨の分離によって、腰の安定性が損なわれ、運動時に痛みが出たり、将来的に「すべり症」へと進行する可能性もあるため、注意が必要です。
サッカーでなぜ発症しやすいのか?
サッカーは、シュートやロングキック、ヘディングなどで「腰を反る・ひねる」動作が多く、これが腰椎に繰り返し負担をかけます。
特に成長期の骨は柔らかく、過度な負担によって椎弓にストレスが集中し、疲労骨折が起こりやすくなります。
キック動作における「腰の反り」や「無理な姿勢でのターン」地面からの衝撃の吸収が不十分な選手は、腰椎分離症のリスクが高まります。
初期症状と見逃されやすさ
分離症の初期は「なんとなく腰が重い」「練習後に腰が張る」など、曖昧な症状が多く、普通の腰痛と区別がつきにくいことがあります。
特に、分離症では前屈よりも後屈(反る動作)で痛みが強くなるのが特徴です。
放置すると、分離が進行し、完治が難しくなるため、早期発見と対応が重要になります。
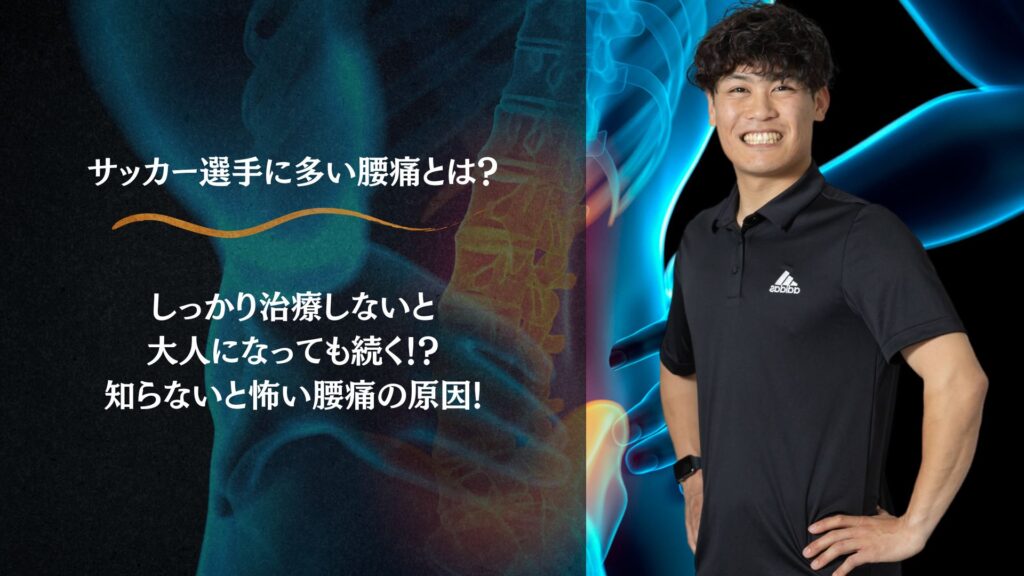
腰椎分離症の予防と改善に必要なこと
分離症を予防・改善するには、サッカー選手特有の体の使い方を理解した上でのケアとトレーニングが必要です。
股関節と体幹を正しく使う
腰を反らせずに動くためには、股関節の可動性と体幹の安定性が不可欠です。
キックのときに股関節がうまく使えないと、代わりに腰を反って動こうとするため、腰椎に無理な負担がかかります。
腸腰筋・殿筋群・腹横筋などのインナーマッスルを使えるようにし、腰ではなく「股関節で動く」クセをつけることが、最も重要な予防策です。
姿勢とプレースタイルの見直し
猫背や反り腰、骨盤が前に倒れた姿勢は、腰椎に負担をかけやすくなります。
立ち姿勢や走るフォーム、キックフォームなど、日常の中で無意識に取っている姿勢を見直すことが、怪我予防の第一歩です。
また、足元ばかり見てプレーするクセや、体を反らせて蹴るクセなど、技術面の指導と並行して姿勢指導を行うことも効果的です。
これらの問題はトレーニングや整体によって解決することができるので気になる方は、お気軽にご連絡ください。
痛みがある時は安静+専門的対応を
分離症は疲労骨折の一種であるため、痛みが出ている間は練習を中止し、骨の回復を優先させる必要があります。
無理をして練習を続けると、骨が完全に分離してしまい、自然治癒が困難になるケースもあります。
病院での画像検査(MRIやCT)を受けることも大切ですし、スポーツに理解のある整体やトレーナーと連携しながら、リハビリやフォームの改善を行うことが望ましいです。
最後に
腰椎分離症は「サッカー選手にとっての職業病」とも言えるほど、発症しやすい障害です。
しかし、その多くは「姿勢」や「動き方」のクセを変えることで、予防・改善が可能です。
・いつも腰がだるい
・練習後に腰に痛みが出る
・前よりキック力が落ちた気がする
こんなサインがある選手は、腰椎分離症を疑ってみてください。
「痛みがあるから休む」のではなく、「なぜ痛みが出るのか?」という原因を知り、改善することで、選手としての成長につながります。
腰痛に悩む選手・保護者の方は、ぜひ一度ご相談ください。