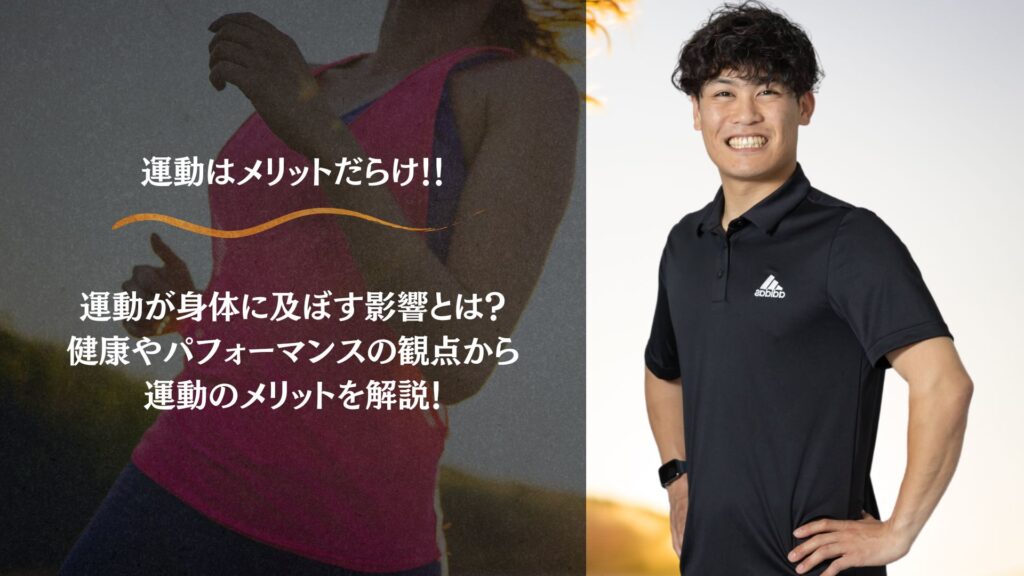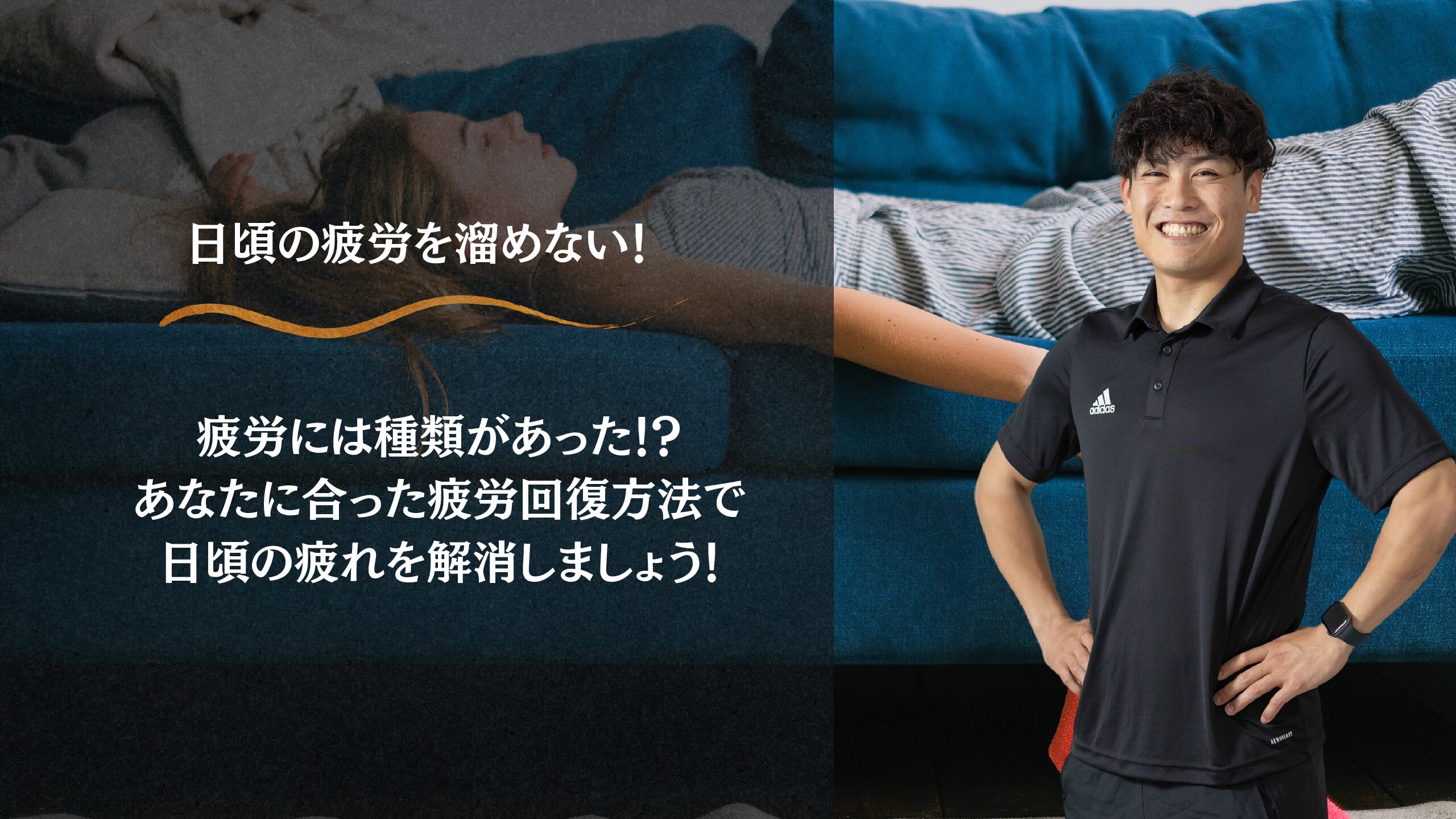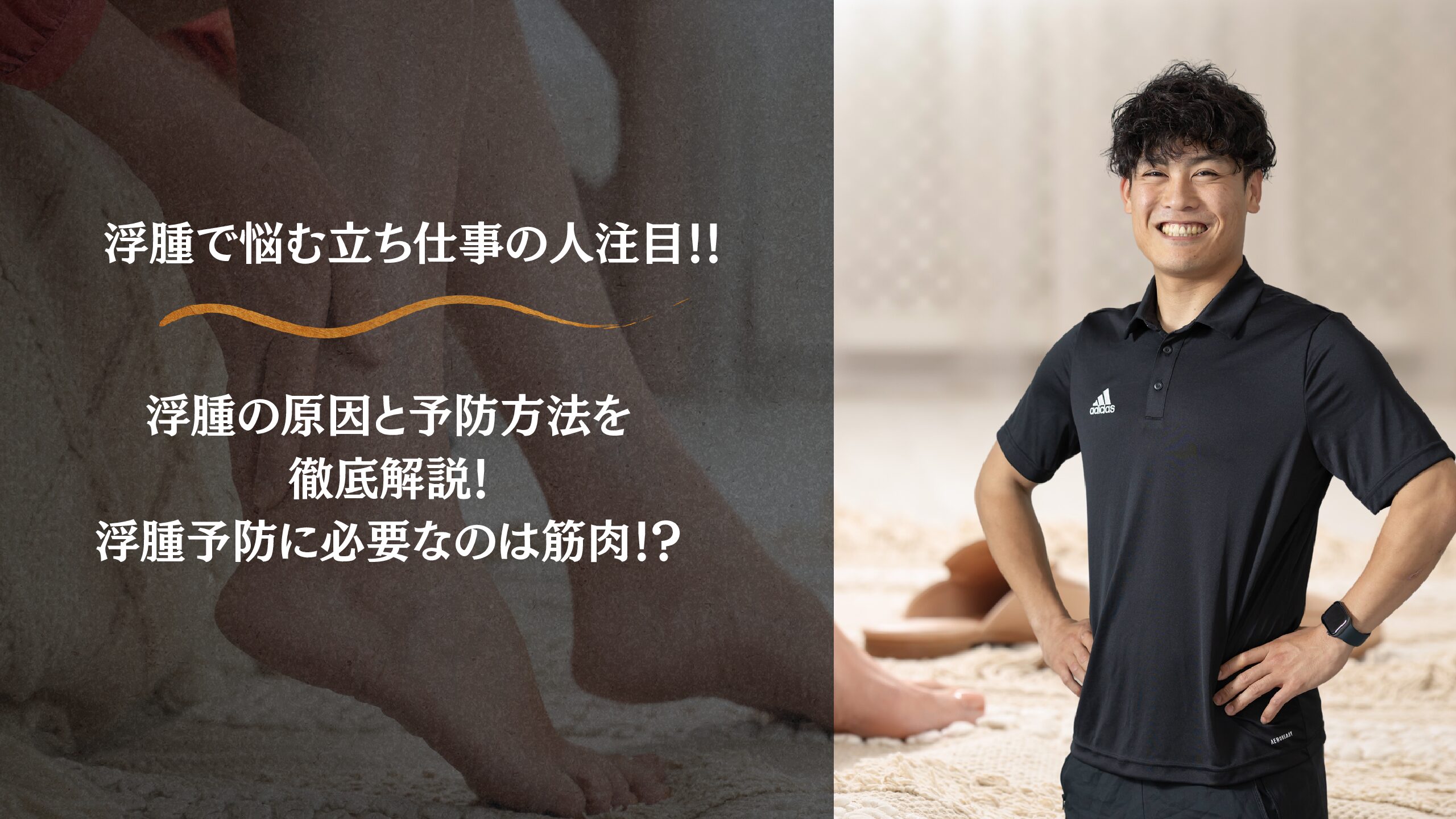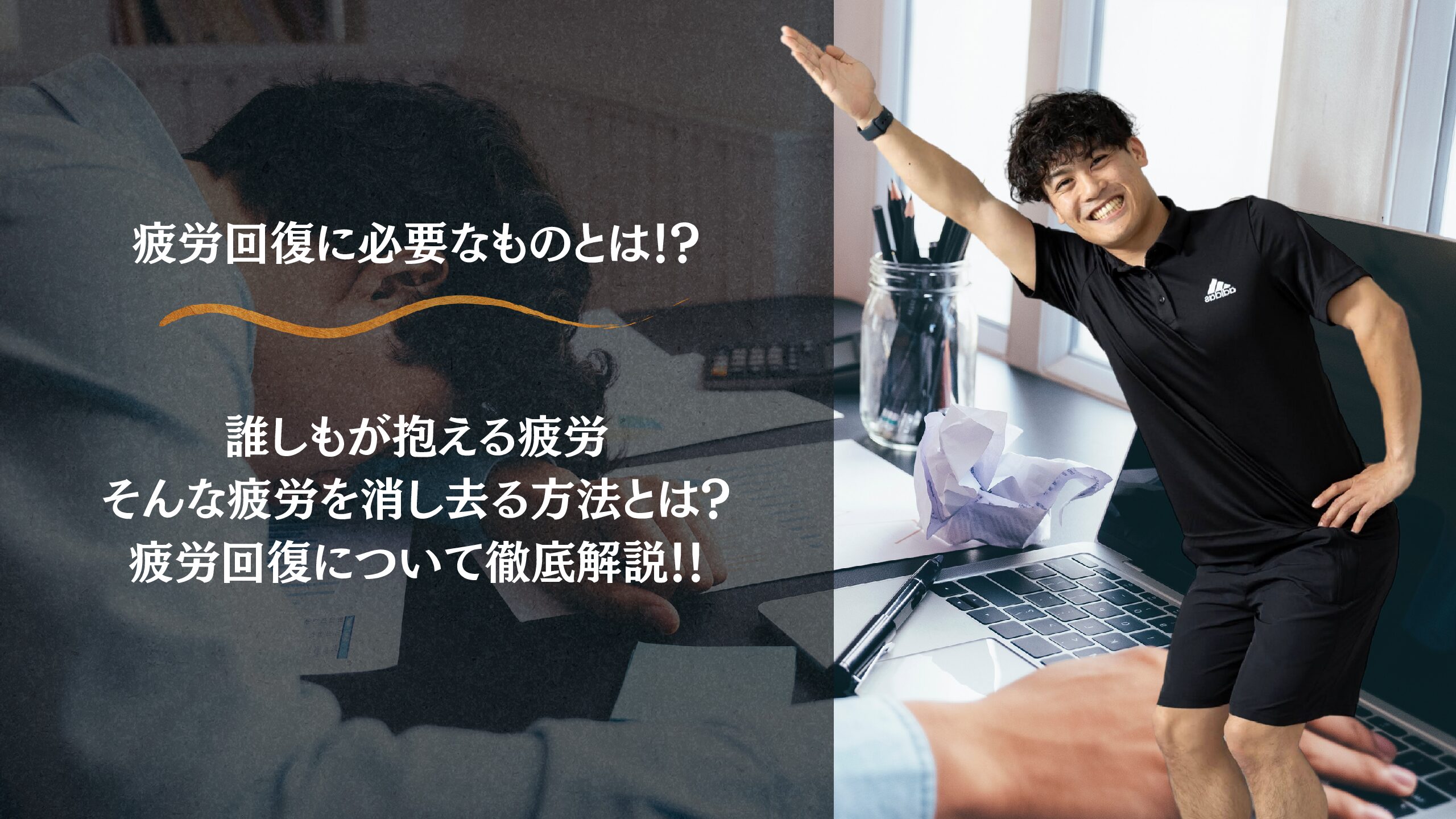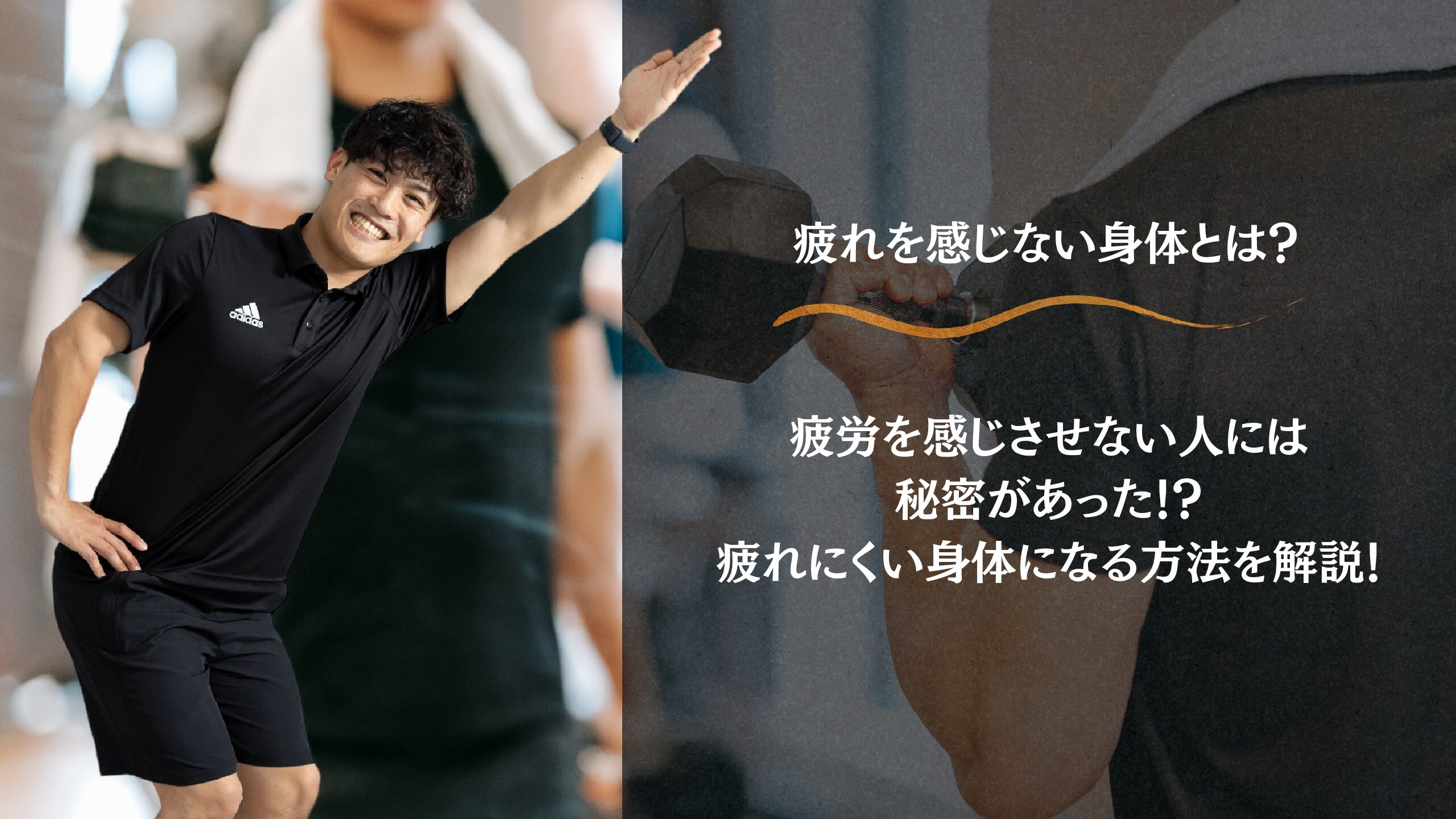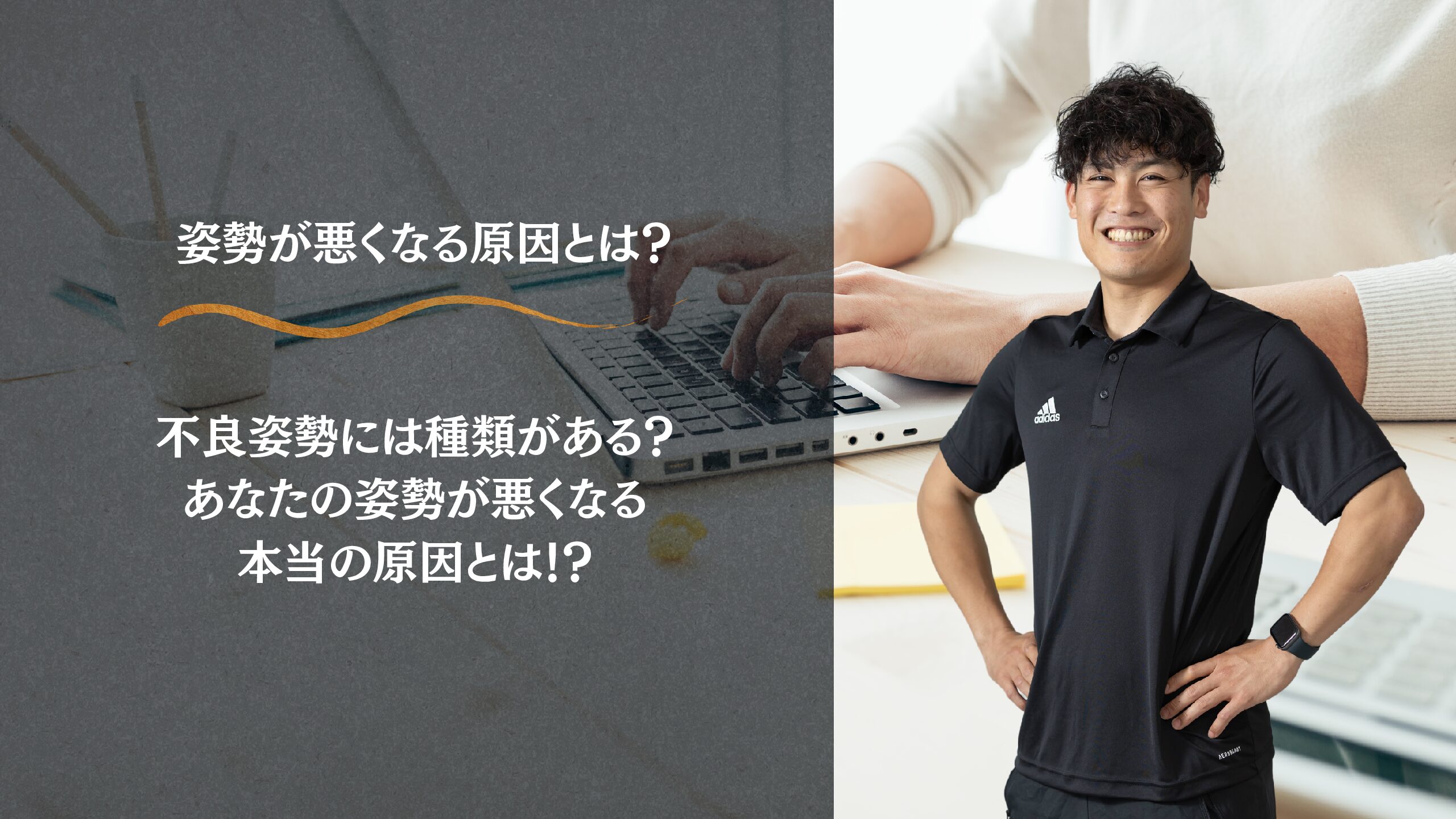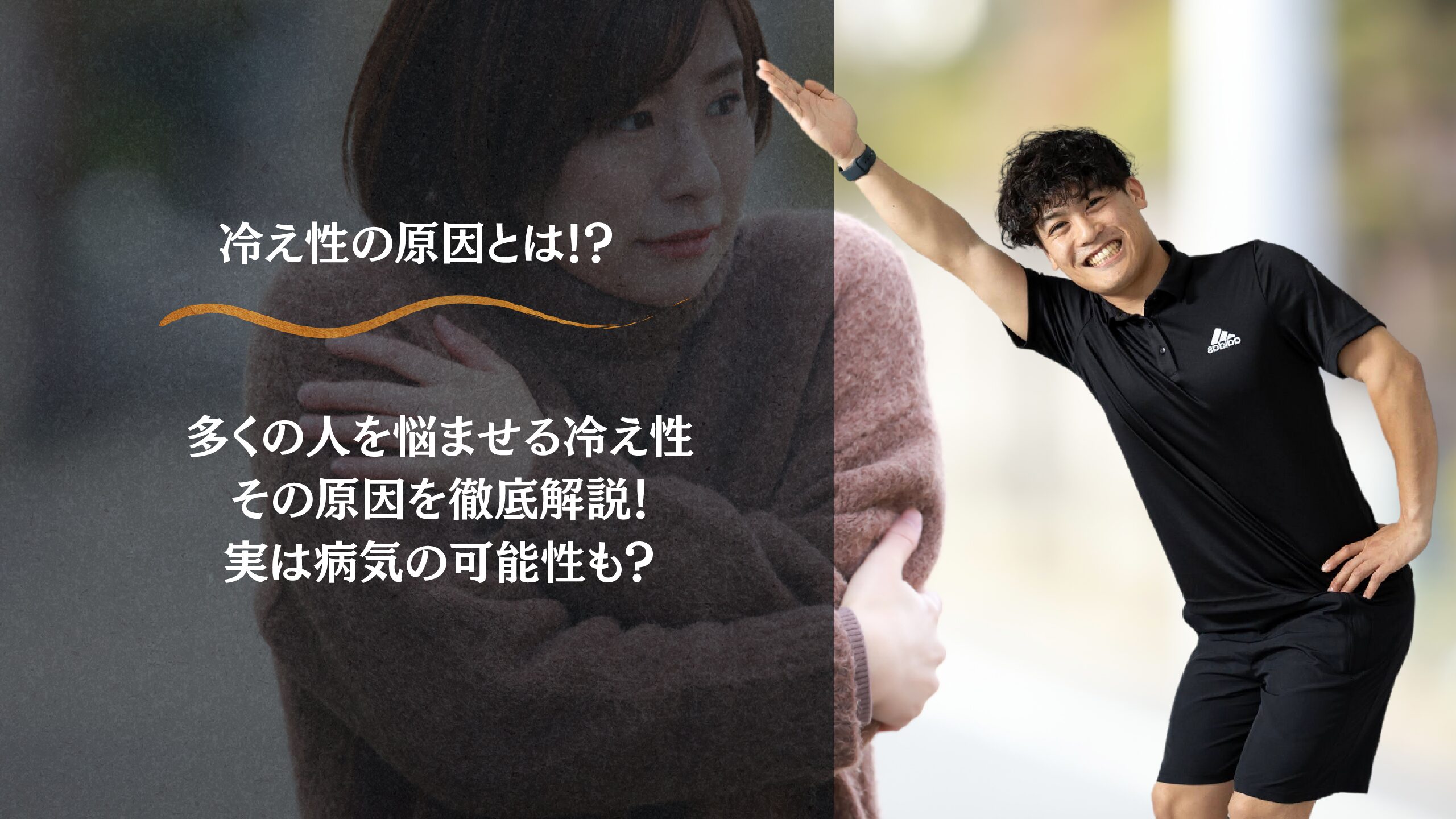【X脚の原因と改善方法】見た目の歪みだけじゃない、膝や股関節のトラブルにも注意
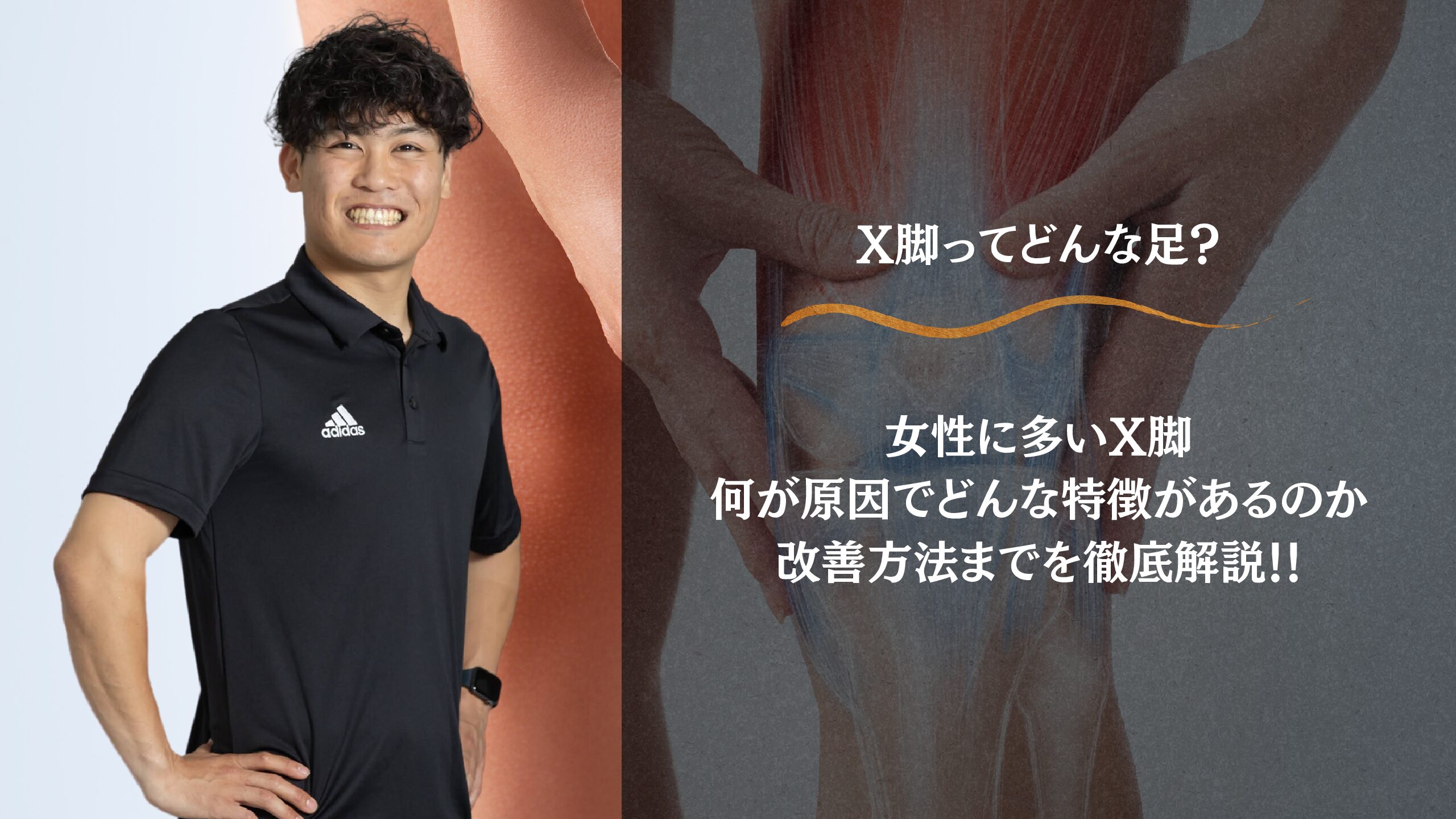
大阪メトロ緑橋駅から徒歩1分
整体とパーソナルトレーニングで痛みや疲労の改善を目指す
カラダの説明書 緑橋の春藤謙介です。
「膝が内側に入りすぎて見える」「立ったときに足首がくっつかない」などの悩みはありませんか?
それは、脚のアライメントが崩れている「X脚」かもしれません。
X脚は、見た目の問題だけでなく、膝・股関節・足首にかかる負担が偏ることで、慢性的な痛みや疲労感を引き起こす原因にもなります。
今回は、X脚の種類や原因・身体への影響、そして改善のためにできることを解説していきます。
・下半身のラインが気になる
・膝や股関節が疲れやすい
・立ち姿や歩き方に違和感がある
こうした方にぜひ読んでいただきたい内容です。
X脚とは?種類と原因
X脚とは、足を揃えて立ったときに膝が内側に寄りすぎて、足首の間にすき間ができる状態のことを言います。
「膝が内に入りすぎる歩き方」「内股姿勢」などもX脚のサインです。
骨格性X脚と機能性X脚
X脚には「骨格性」と「機能性」の2つのタイプがあります。
骨格性X脚は、生まれつきの骨の形や成長期の変形によって、骨自体の角度が内側に傾いているケースです。
この場合は整形外科的な管理が必要になることもあります。
機能性X脚は、筋肉のアンバランスや日常の姿勢のクセによって、骨格がねじれてしまうものを言います。
このタイプであれば、整体やトレーニングで改善が見込めます。
特に女性や10代後半から20代の方に多く、日常の立ち方・座り方・歩き方が強く影響しています。
X脚の主な原因
X脚の原因は多岐にわたりますが、主に以下のような点が挙げられます。
・太ももの内側(内転筋)の緊張している
・股関節が内旋位(内巻き)で固まっている
・外側の筋肉(外転筋や腸脛靭帯)が弱い
・骨盤が後傾している
・足のアーチが潰れている(偏平足・過回内)
こうした要因が組み合わさることで、膝が内側に寄り、X脚の状態が強くなっていきます。
また、体幹の弱さや猫背といった姿勢全体の崩れも、X脚を助長する要因となります。
X脚が引き起こす身体への影響
X脚を放置してしまうと、以下のような身体への悪影響が起こることがあります。
・膝の外側の筋肉に過度な負担
・足首のねじれによる外反母趾や偏平足の悪化
・股関節のつまり感・違和感
・歩き方のバランスの崩れ
・太もも外側の張りやすさ
・将来的な変形性膝関節症のリスク
特に、膝のねじれが強くなることで、関節の軟骨に片寄った摩耗が起こり、膝の痛みや違和感を訴える人が増えてきます。
X脚を改善するためにできること
X脚の改善には、脚の使い方・姿勢・筋バランスを整えることが重要です。
ここでは、日常生活で実践できる改善アプローチを3つ紹介します。
お尻の筋肉(中臀筋)を活性化させる
X脚の方は、お尻の外側の筋肉「中臀筋」がうまく使えていないケースが非常に多いです。
この筋肉は、股関節を外側に開く動きを支える重要な筋肉です。
例えば、横向きで寝て脚を開く「股関節の外転トレーニング」などは中臀筋の活性化に効果的です。
また、片脚でバランスをとるトレーニングを行うことで、日常の中でもお尻の筋肉を使えるようになっていきます。
足のアーチを整える習慣を持つ
X脚の多くは、足の内側アーチ(いわゆる土踏まず)が潰れてしまっている「過回内(オーバープロネーション)」の状態にあります。
この状態では、地面からの力が不安定になり、膝が内側に倒れ込む原因となります。
足裏のアーチを意識的に高めるトレーニングを行うことが大切です。
また、裸足での生活時間を増やすことも感覚入力としては非常に有効です。
最後に
X脚は「ただの脚の歪み」と思われがちですが、放置すれば将来的な膝の痛みや姿勢の崩れにつながります。
特に、筋肉のアンバランスや足の使い方のクセによって引き起こされる機能性X脚であれば、トレーニングや姿勢改善で充分に改善が期待できます。
大切なのは「ただ脚を真っ直ぐにしようと頑張る」のではなく、「なぜそうなっているのか」を知り、「根本の使い方から見直す」ことです。
緑橋駅すぐの「カラダの説明書」では、脚の歪みチェックや姿勢分析を行い、一人ひとりに合わせたアプローチをご提案しています。
X脚が気になる方、自分に合った改善方法を知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。