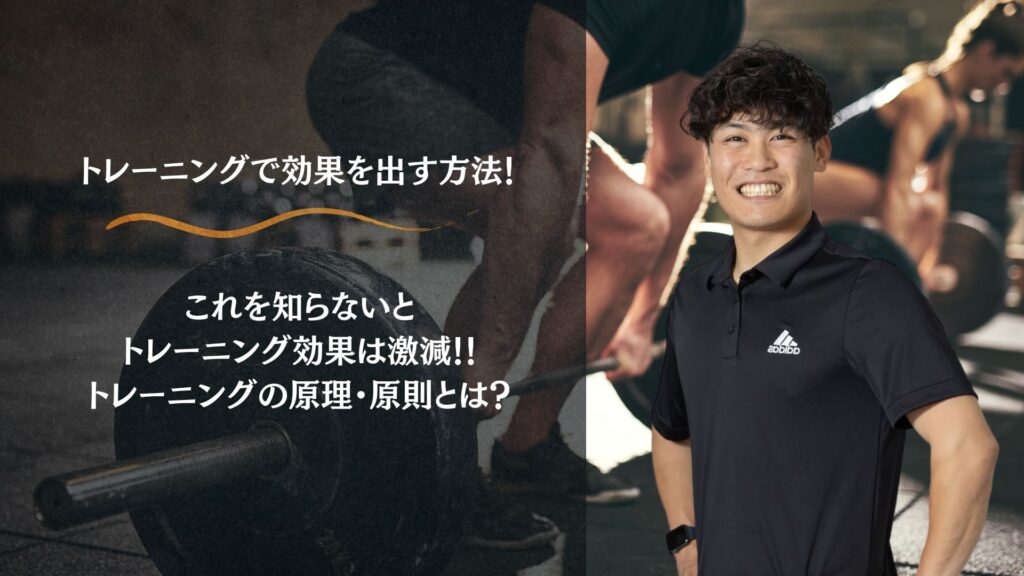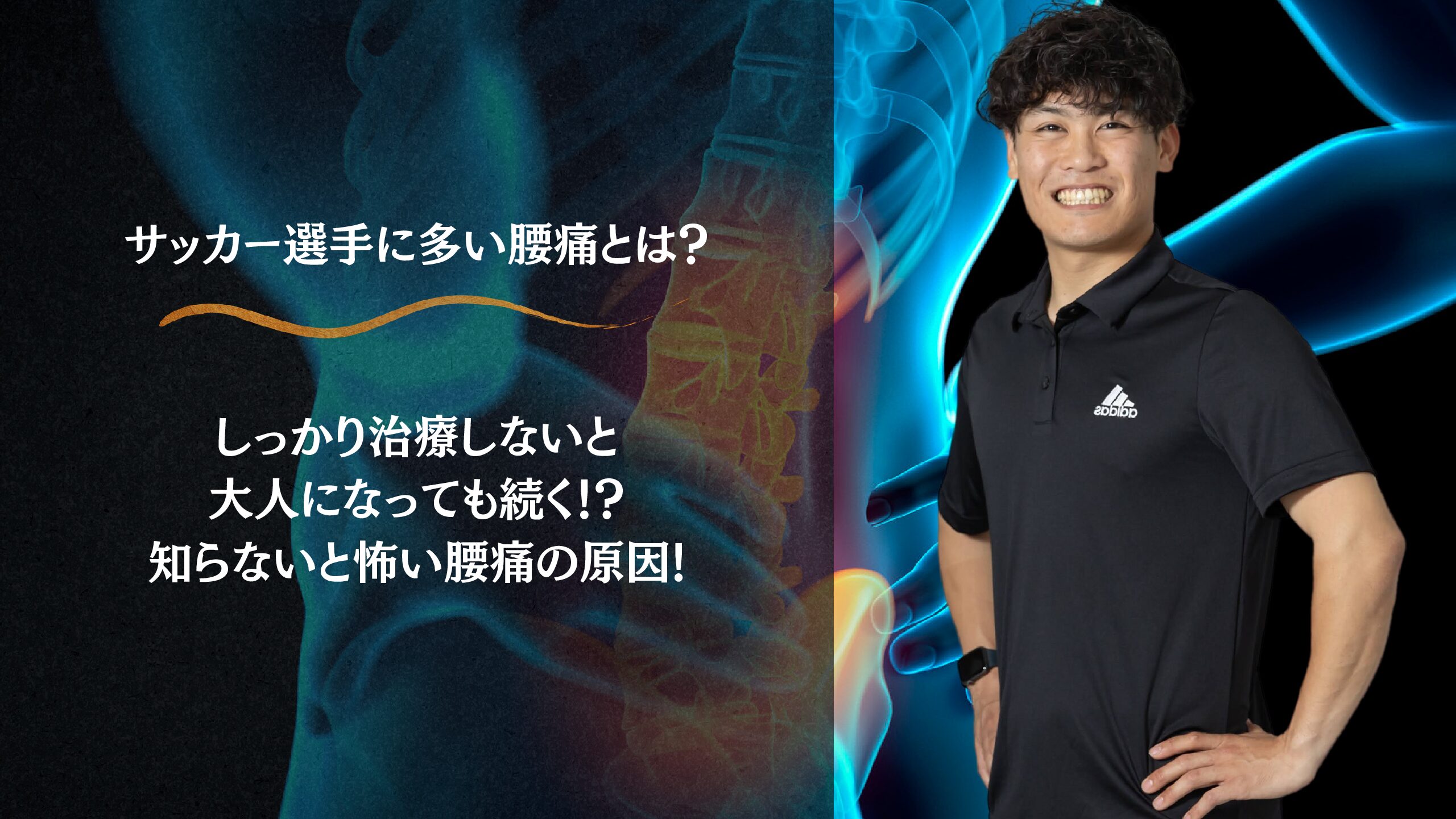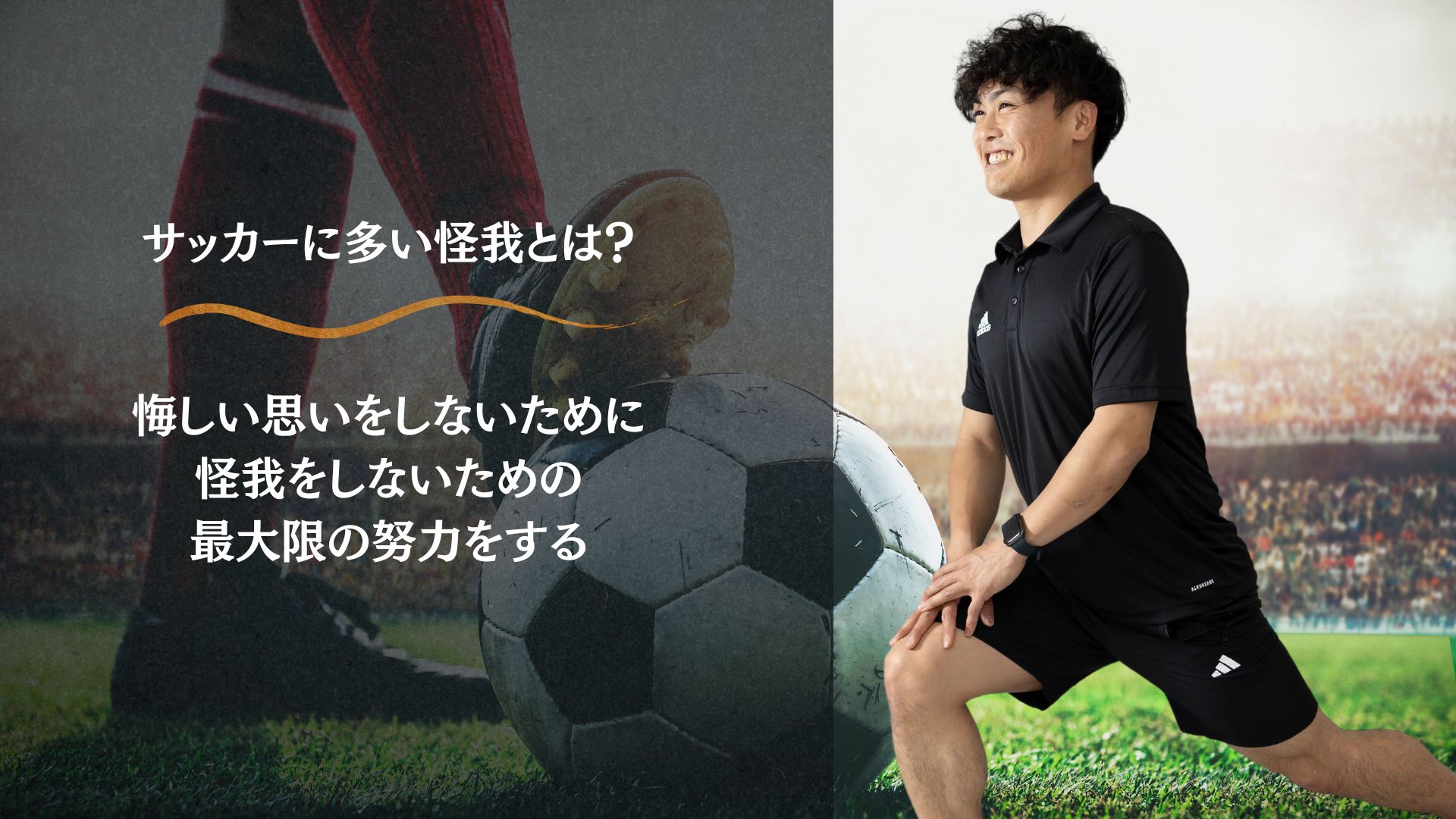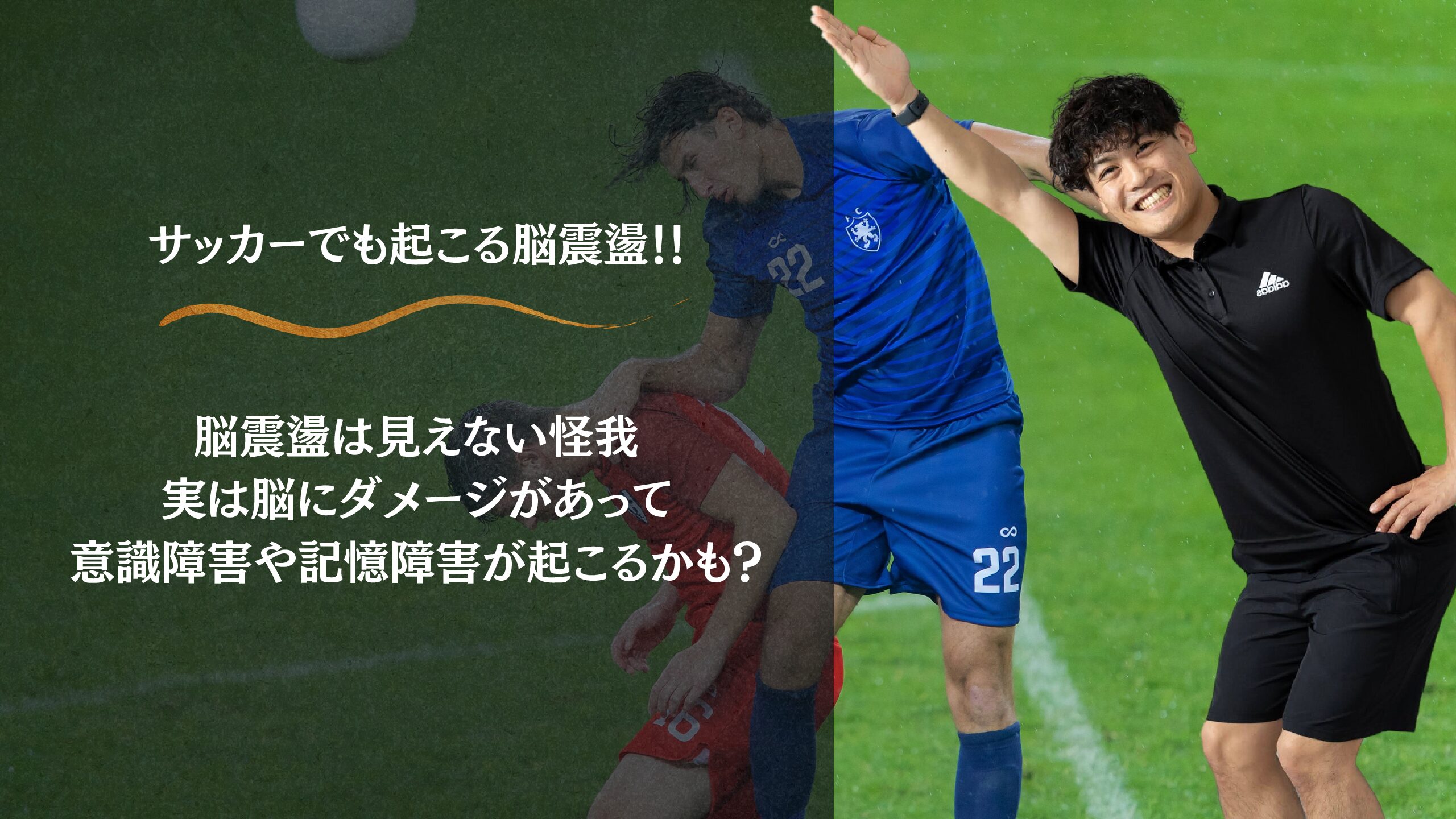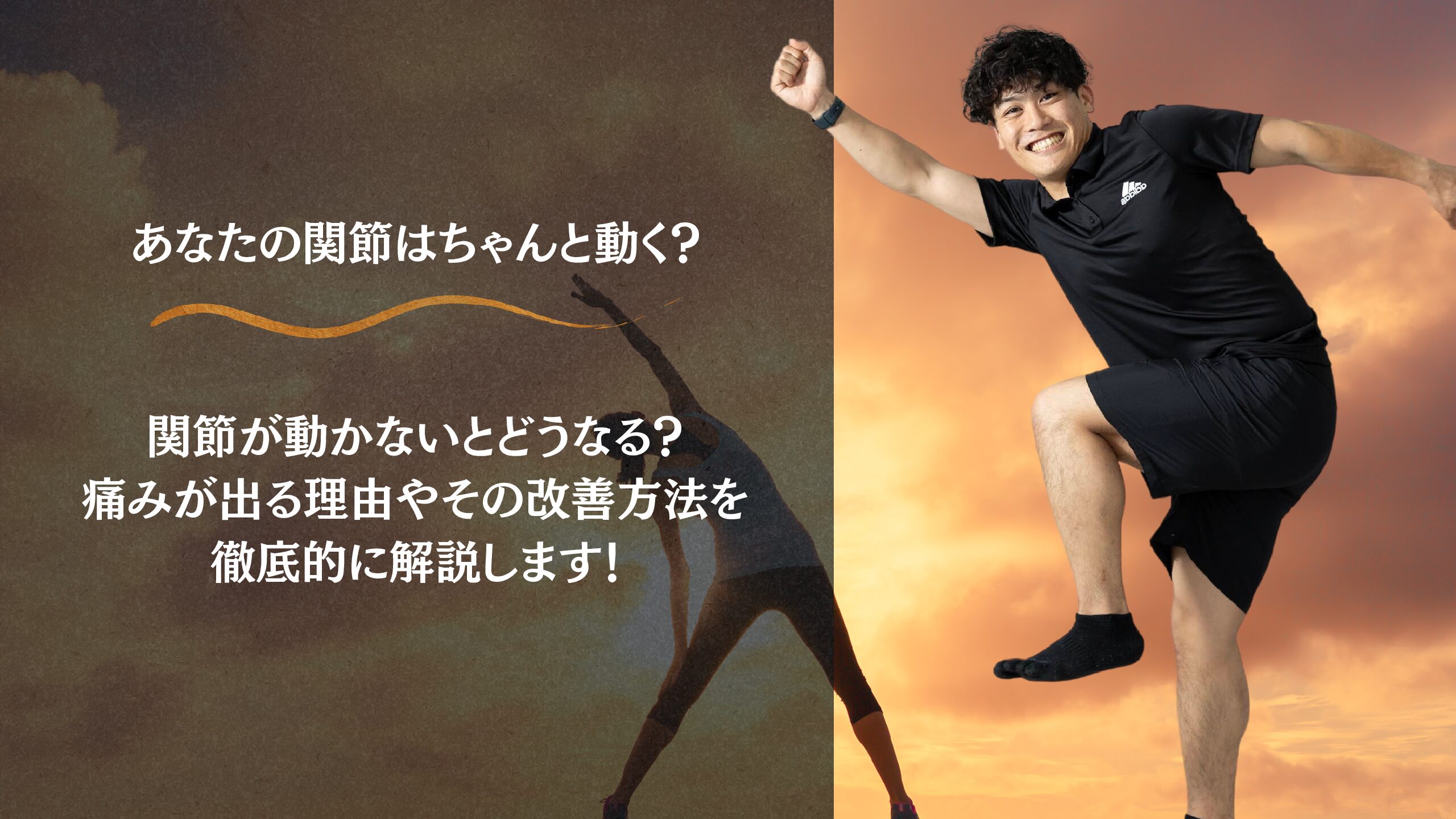【肉離れは再発しやすい怪我】肉離れの再発を防ぐために必要なこととは?
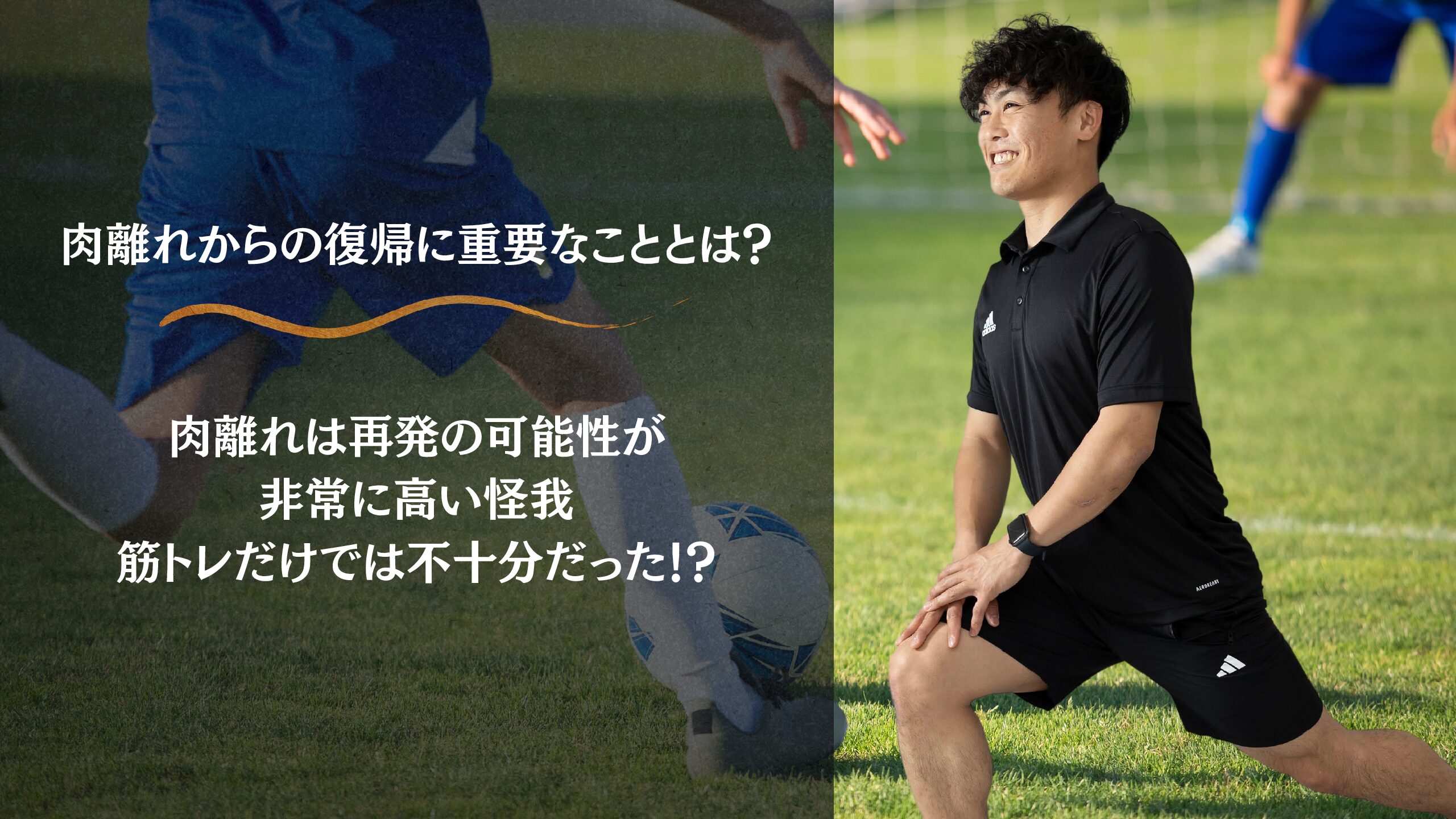
こんにちは!緑橋で整体院をしている【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。
まだまだ寒い日が続きますが、この時期はアップが不十分なことによって、いろんな怪我が起こります。
その中でも、特に多いのが【肉離れ】です。
肉離れは、幅広い年齢に起こり、一度損傷してしまうと、再発の可能性が高く、やっかいな怪我です。
そのため、日頃からしっかり体のケアと予防をしていく必要があります。
ここからは、そんな肉離れについて症状や治療方法、復帰するために必要なことを解説していきます。
この記事を読んで、少しでも多くの肉離れを繰り返す選手が、少なくなれば幸いです。
肉離れとは?
そもそも肉離れとは、どんな怪我かご存じでしょうか?
肉離れとは、筋や腱が損傷または断裂している怪我で、正式名称は「筋挫傷」と言います。
部位によって発生するタイミングは少し変わりますが、筋肉が急激に伸ばされたタイミングや筋肉に力を入れたタイミングなどで起こります。
ここからは、そんな肉離れの症状や治療方法について解説していきます。
肉離れはどんな症状?
肉離れは、損傷度合いによって三つに分けられます。
✅軽傷
→筋肉や筋膜に大きな損傷はなく、少し伸ばされた程度
対象の筋肉にストレッチをかけた時に少し痛みが出現
自分で歩くことも可能
✅中等度
→筋肉や筋膜に少し損傷があり、皮下出血などが見られる
患部を押すと痛みがあり、自分で歩くことは困難なことが多い
✅重度
→筋肉や筋膜が深く損傷が見られる
外見からも患部が少し凹んでいるのがわかる
痛みも強く、自力での歩行はほぼ不可能
共通して起こる症状は、患部を伸ばした時に痛みが出現します。
しかし、軽度の場合、患部に力を入れても痛みが出現しないこともあり、ただの筋疲労による痛みなのか、それとも、肉離れなのかを見極める一つのポイントになります。
治療方法は?
肉離れが、起こった直後の現場での対応は、「PEACE &LOVE」を中心に行いましょう。
すぐに病院にいくことが難しい場合は、応急処置としてこれを参考にしてみてください。
またこの中でも、現場での判断が難しいものは、無理にせず安静を心がけて、なるべく早く病院に連れて行けるようにしましょう。
✅Protection (保護)
→数日間は痛みの伴う運動は控える
✅Elevation (挙上)
→怪我をした部位を心臓より高く挙上する
✅Avoid Anti-inflammatories (抗炎症薬を避ける)
→怪我をした組織の回復を低下させる可能性があるため、抗炎症薬の服用は避ける
また、アイシングも避ける
✅Compression (圧迫)
→腫れを抑える
✅Education (教育)
→患者の状態に最も適した対処法を教え、過剰な医学的診療と薬の服用、そして不必要な受動的療法を避ける
✅Load (負荷)
→痛みと相談しながら、徐々に日常生活に戻る
✅Optimism (楽観思考)
→自信を持ち、前向きな考えを持つことで最適な回復が可能になる
✅Vascularisation (血流を増やす)
→痛みが伴わない有酸素運動を行うことで、負傷組織への血流を増やし、回復を促進させる
✅Exercise (運動)
→回復へ向けた積極的なアプローチをとることで、身体の動き、筋力を回復させる
部活動のコーチは、トレーナーがいなくても最低限、これらのことができるようにしておくことをお勧めします。
復帰するためには?
肉離れは、冒頭でもお伝えした通り、再発の可能性が非常に高い怪我です。
そのため、痛みが引いたから復帰というわけにはいきません。
そのまま復帰してしまうと、再発の危険性が非常に高いため、しっかりとリハビリを行う必要があります。
では、どんなリハビリが必要なのでしょうか?
ここからは、復帰に向けて必要なリハビリについて解説していきます。
柔軟性を上げる
肉離れの一つの原因に、柔軟性の低下があります。
肉離れは、筋肉が急激に伸ばされ、限界以上に伸ばされた時に起こります。
そのため、日頃から筋肉の柔軟性を上げておくことは、肉離れの予防として重要になってきます。
また、肉離れの後は必ずと言っていいほど、筋肉の柔軟性は落ちています。
最低でも、怪我をしていない側の足と同じぐらいには、柔らかくしていきましょう。
筋力を上げる
肉離れの原因は、柔軟性が低下しているだけではありません。
筋肉の力を発揮しないといけない場面で、その筋肉の許容範囲を超えた力が加わると、筋肉は断裂してしまいます。
これは、特に筋肉が引き伸ばされながら使う場面で見られます。
そのため、筋肉の許容範囲を広げるためにも、筋力の強化は必須になります。
そのトレーニングの際には、注意点があります。
筋肉には、三つの収縮形式があり
✅求心性収縮
→筋肉の長さが短縮しながら、力を発揮する方法
例)力こぶを作るとき
✅等尺性収縮
→筋肉の長さを変えずに力を入れる方法
例)空気椅子をしている時の足の筋肉
✅伸張性収縮
→筋肉の長さが引き伸ばされながら、力を入れる方法
例)ダンベルを持ってゆっくり下ろす時の力こぶの筋肉
この収縮様式の中の「伸張性収縮」で肉離れは起こります。
そのため、初めから伸張性収縮のトレーニングはせずに、
等尺性収縮→求心性収縮→伸張性収縮の順番でトレーニングを入れていきましょう。
最低でも怪我をしていない側の筋力と同等になるまでは、復帰をしないことをお勧めします。
競技特性を踏まえてトレーニングをする
トレーニングの原理原則の中に「特異性の原理」というものがあります。
これは、簡単にいうと目的に応じたトレーニング内容をしないと効果は得られない、ということです。
詳しく知りたい方は、下記の画像から読んでいただけます。
ここまで、柔軟性や筋力のトレーニングを行なってきても、最終的に競技に繋げていかないと意味がありません。
例えば、サッカーのように、素早い切り返しが必要な競技では、切り返しのタイミングにかかる負荷を、スクワットだけで補うことは不可能です。
そのため、サッカーでいうと、リハビリの中で、切り返しの動作に近い動きを入れていくことが重要になってきます。
全てのリハビリで言えるのは、怪我をする前の状態で復帰してしまうと、また同じような怪我をしてしまいます。
そのため、怪我をして復帰する時には、怪我をする前より強い状態になるようにしましょう。
最後に
肉離れは、再発の可能性が非常に高い怪我です。
そのため、痛みが引いた後のリハビリがとても重要になってきます。
最低でも、柔軟性や筋力、競技特性に合わせた動作が怪我をする前より、向上している状態を目指してリハビリをしていきましょう。
今現在、肉離れで悩んでいる人は、緑橋駅にある整体院、カラダの説明書にご相談ください。
カラダの説明書では、国家資格を持ったトレーナーが、自分に必要なリハビリや治療を提案させていただきます。
お悩みの方がいたらぜひ、ご相談ください。