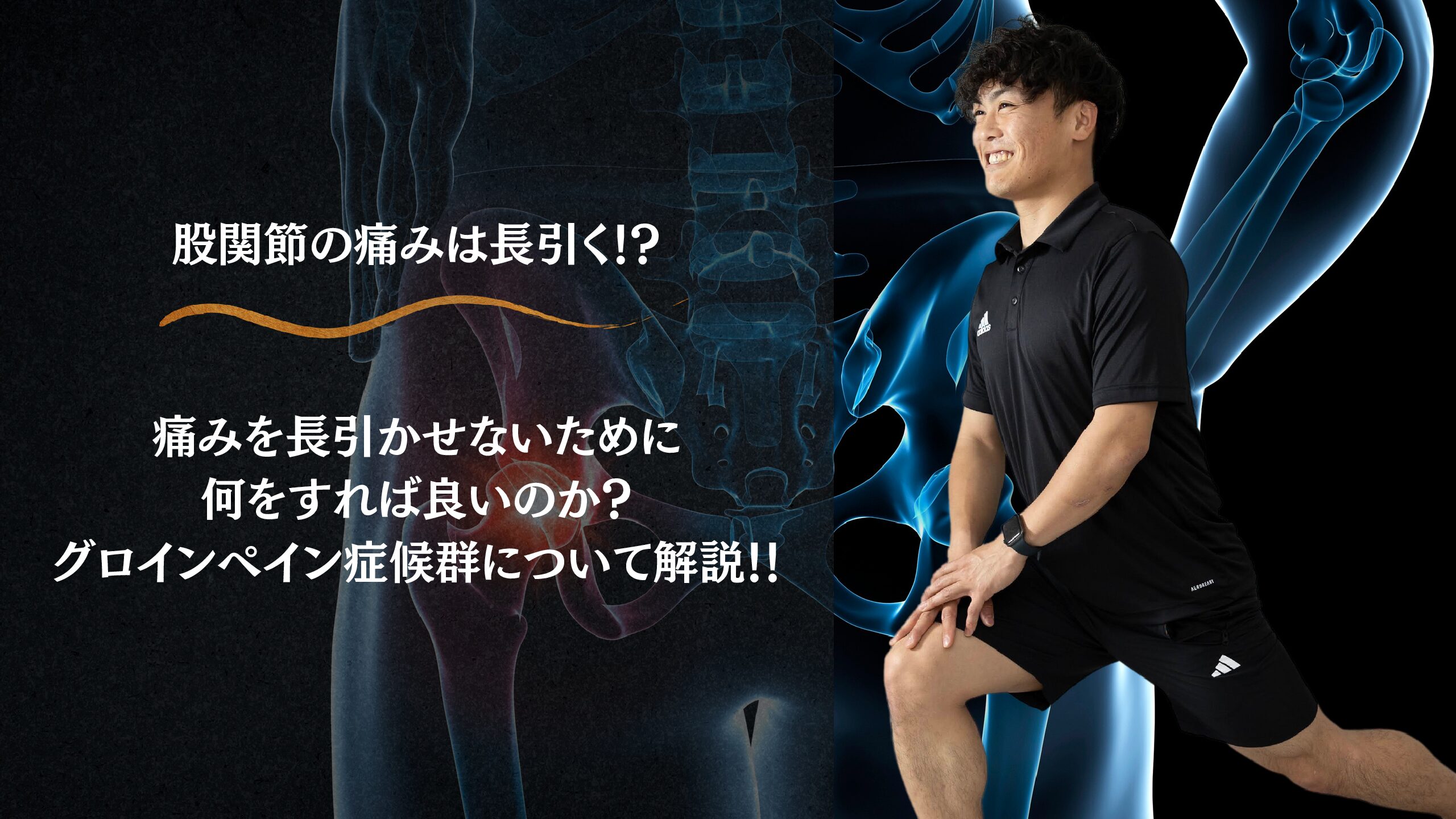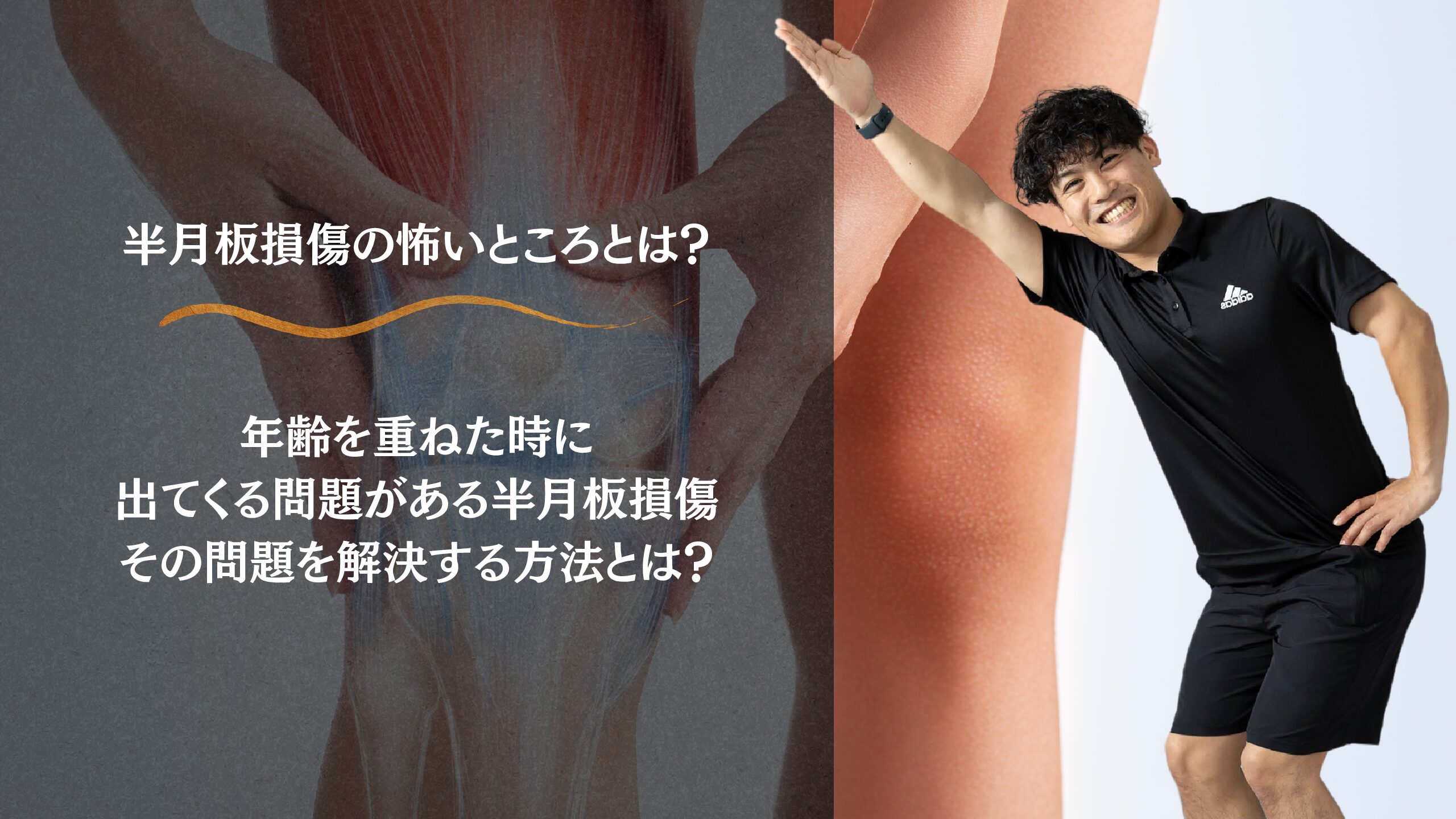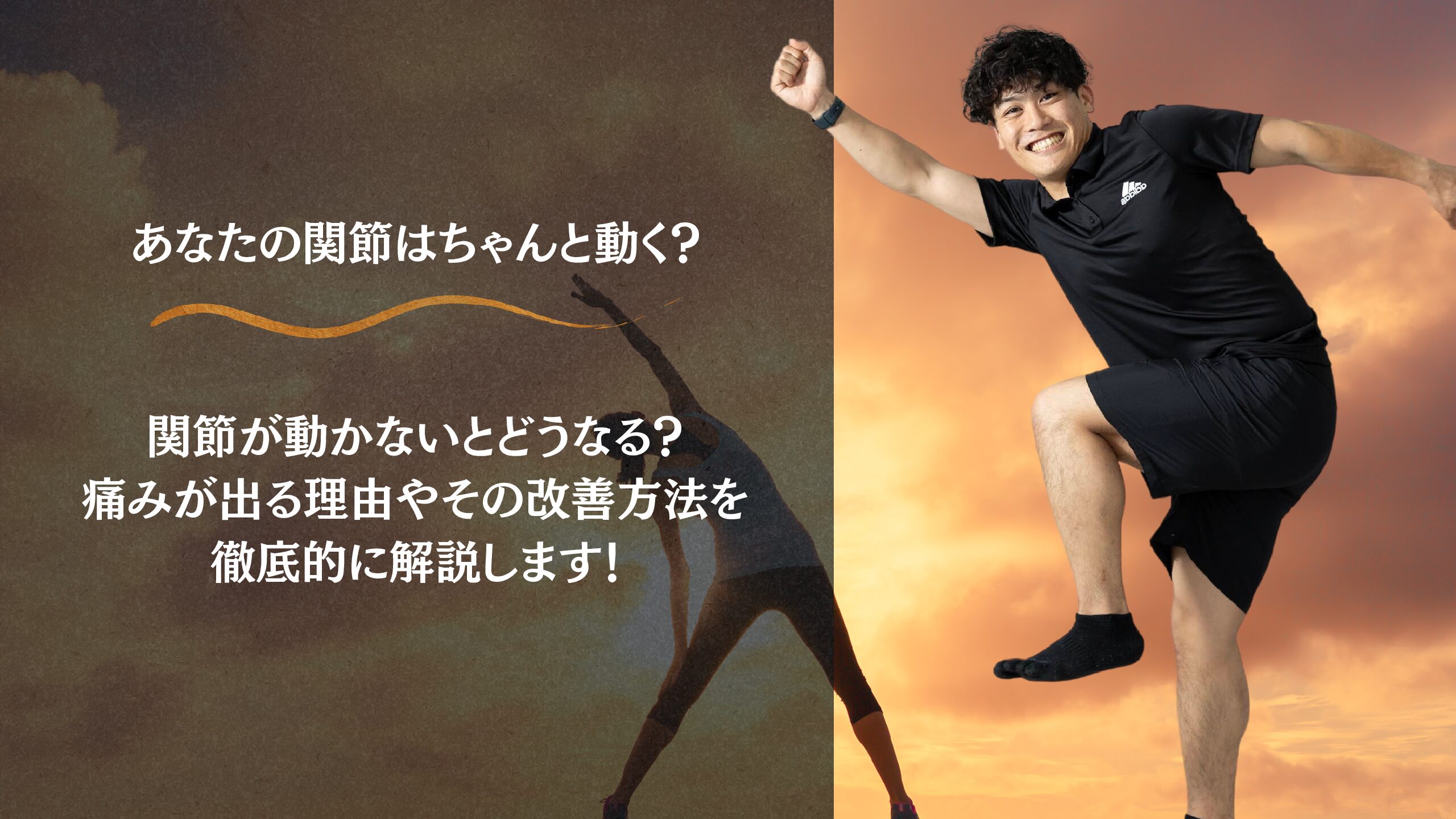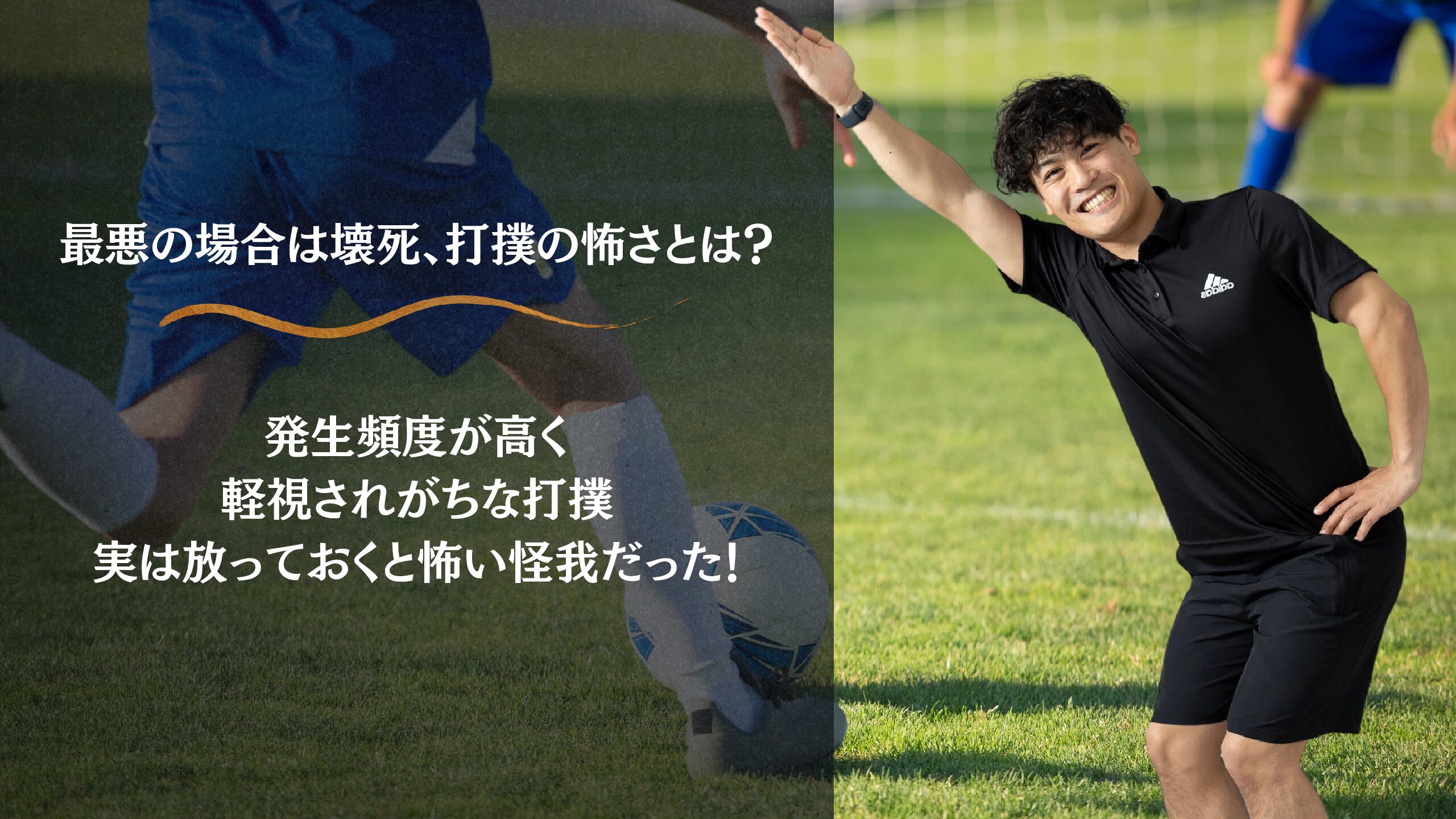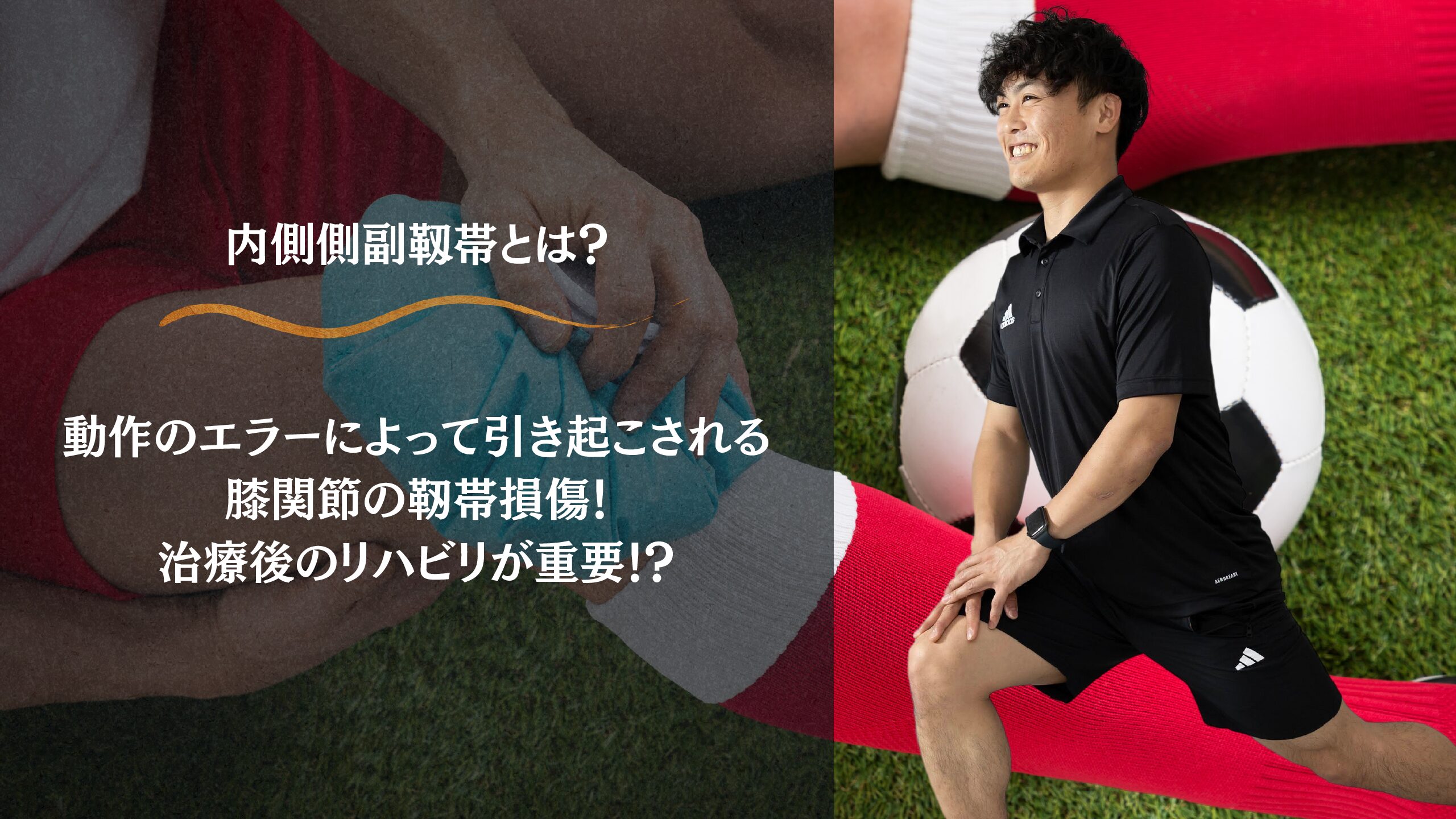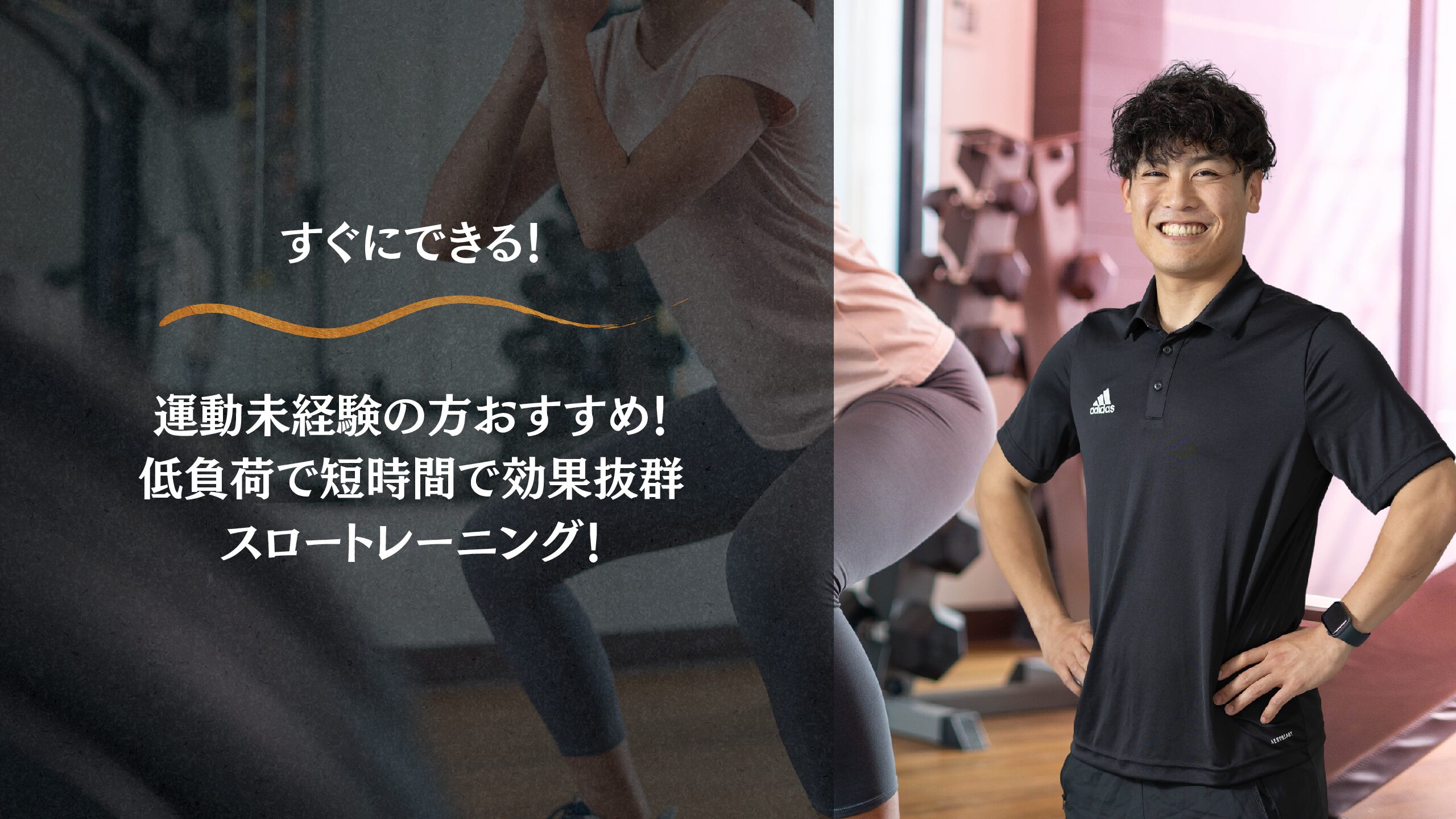【成長期に多くの方が経験する】膝が出っ張るオスグッド・シュラッター病とは?
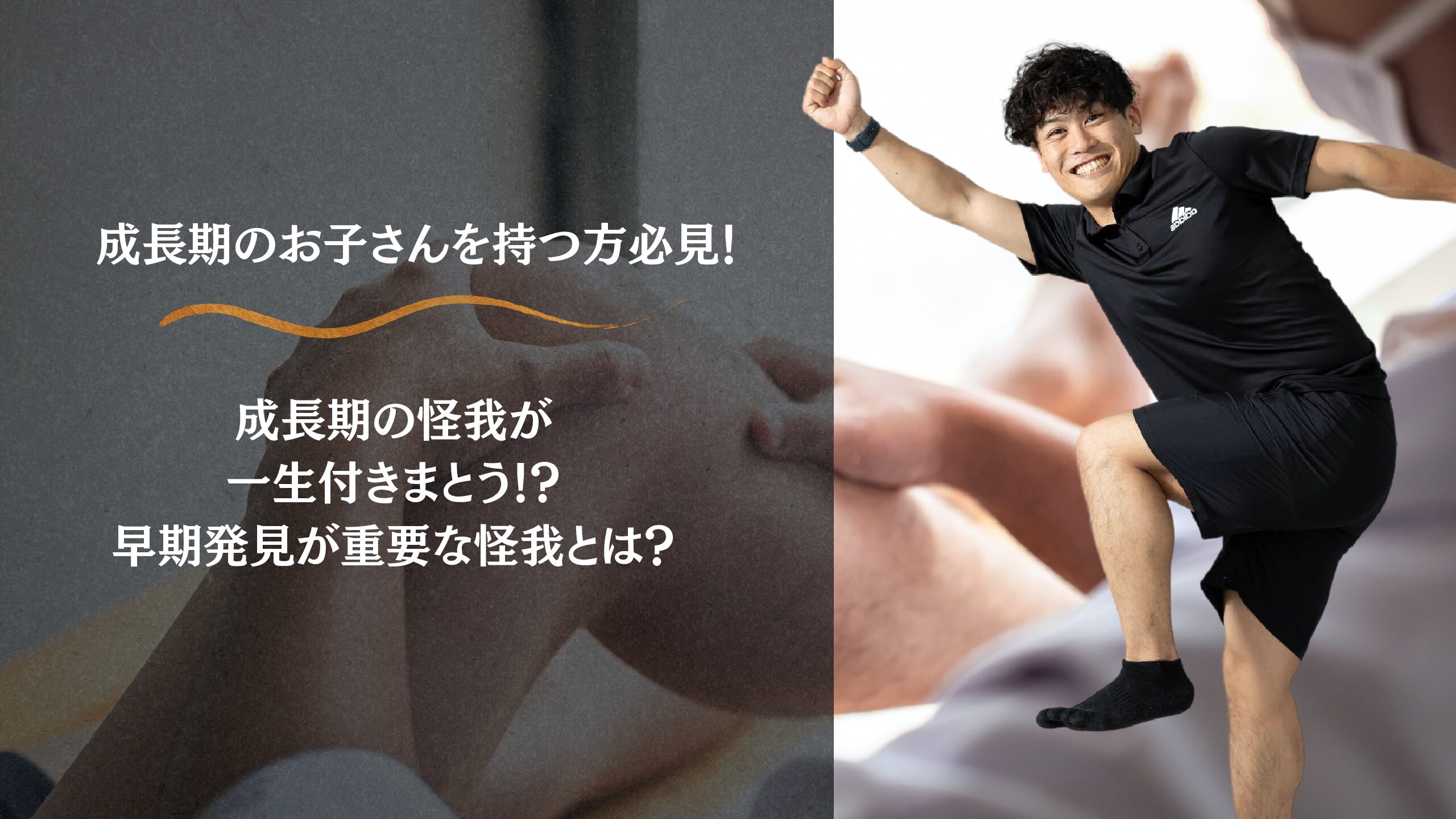
こんにちは!緑橋で整体院をしている【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。
みなさんは、膝を痛めたことはありますか?
膝は、どんなスポーツにおいても怪我が多く、復帰までの期間がとても長くかかります。
特に、成長期に見られる【オスグッド・シュラッター病】は、初めは、運動した時だけに傷みが現れ、すぐに痛みがなくなります。
しかし、それを放置して我慢していると、痛みが長引き、何もしていなくても痛くなってきます。
また、ひどくなると痛みが取れないだけでなく、大人になっても正座ができないなどの、問題が起こります。
今回は、そんな【オスグッド・シュラッター病】について解説していきます。
オスグッド・シュラッター病とは?
オスグッド・シュラッター病とは、お皿の下にある、脛骨粗面と呼ばれる部分が大腿四頭筋の牽引力によって、剥がれてしまう病気です。
ここから、オスグッド・シュラッター病の原因や症状について解説していきます。
何が原因でオスグッド・シュラッター病になる?
人間の身体は、初めから全てが硬い骨で、できているわけではありません。
初めは、成長軟骨と呼ばれる、骨よりも柔らかい組織でできています。
オスグッド・シュラッター病が、成長期に多い理由は、この成長軟骨が骨になっておらず柔らかい状態だからです。
しかし、筋力は発達し、練習強度や練習の頻度はどんどん高くなっていきます。
それによって、負荷に耐えられなくなった脛骨粗面が剥がれてしまいます。
では、オスグッド・シュラッター病を予防するには、どうすれば良いのか?
それには「柔軟性」「筋力」「休養」が重要になってきます。
○柔軟性
→オスグッド・シュラッター病では、大腿四頭筋の柔軟性が低下し、脛骨粗面にかかる牽引力が強くなることで、引き起こされます。
そのため、日頃からストレッチをして、大腿四頭筋の柔軟性を高めておくことが、重要になってきます。
○筋力
→筋力の低下もオスグッド・シュラッター病の原因となります。
特に、お尻の筋肉や太ももの裏の筋力不足は、オスグッド・シュラッター病の予防のためには、重要になってきます。
また、サッカーやバスケなど、ストップ動作を繰り返し行うスポーツでは、大腿四頭筋の筋力の低下でも、オスグッド・シュラッター病は起こります。
ただ、がむしゃらに鍛えるのではなく、人によって、必要な筋力は違うので、注意が必要です。
自分が弱い筋肉はどこなのか、知りたい方は、ぜひ、緑橋にある、カラダの説明書にご相談ください。
○休養
→成長期は、身体が成長するにつれて、練習の強度や練習頻度も高くなってくる時期です。
そのため、疲労が蓄積していき、本来よりも筋力が発揮できなくなってしまいます。
また、練習のしすぎで脛骨粗面に何度も引っ張られる力が加わることで、オスグッド・シュラッター病になってしまいます。
どんな症状が出てくるのか?
オスグッド・シュラッター病は、ジャンプや切り替え動作の多いスポーツでよくみられます。
そのため、サッカーやバスケをしているお子さんは、特に注意が必要です。
主な症状としては「圧痛(押すと痛い)」「熱感」「脛骨粗面の膨隆」などがあります。
そして、オスグッド・シュラッター病の厄介なところは、これらの症状が、動いているときだけ出てきて、安静にしていると軽減するところです。
そのため、たいした怪我ではないと、放置してしまい、発見が遅れ、治療が長引き、復帰が遅れてしまいます。
早期発見するためには、脛骨粗面の部分を押して、痛みがある場合は、オスグッド・シュラッター病になりかけている可能性が高いと考えられます。
これは、早期発見にとても有効で、小学校高学年から中学生のお子さんがいらっしゃる方は、一度試してみてください。
痛みがある場合は、すぐに整骨院や整形に行って、きちんとリハビリを受けるようにしましょう。
早期発見をして、しっかりリハビリをすることで、オスグッド・シュラッター病の予防になり、動作の改善、パフォーマンスアップに繋がる可能性もあります。
どんな治療をするのか?
どれだけ予防をしていても、怪我をすることはあります。
では実際にオスグッド・シュラッター病の治療はどのように進めていくのでしょうか?
ここからは、治療方法について解説していきます。
アイシング
オスグッド・シュラッター病の治療は、まずはアイシングからです。
痛みが炎症によって起こっているため、まずはアイシングをして、炎症を抑えていきます。
アイシングは、自宅やスポーツ現場でもできるため、簡単にできるアイシングから始めてみましょう。
サポーターを使う
基本的にオスグッド・シュラッター病は、脛骨粗面にストレスが加わらなければ、痛みは出ません。
そのため、サポーターをつけて動くことで、痛みは大幅に軽減されます。
また、テーピングでも簡単に、サポーター代わりにできます。
しかし、サポーターをつけたら練習してOK、というわけではありません。
これはあくまで、補助の役割をしてくれているだけです。
本来は、しっかりサポーターなしでも、痛みが出ないくらいになってから、練習や試合に出るようにしましょう。
動作の改善
オスグッド・シュラッター病になる患者様には、特徴があります。
それは「ストップ動作」が苦手なことです。
オスグッド・シュラッター病の患者様に、ストップ動作をしてもらうと、膝が前に突っ込んでいくように止まります。
その結果、大腿四頭筋が過剰に働き、脛骨粗面にかかるストレスが強くなってしまいます。
そのため、痛みが落ち着いてきたら、ストップ動作を始め、股関節の使い方などの動作改善を行って、脛骨粗面にかかるストレスを軽減できるように、トレーニングしていきます。
最後に
オスグッド・シュラッター病は、成長期にとても多い病気です。
発見が遅れたり、大したことのない痛みだからと放置していると、大人になっても痛みがあったり、剥がれた脛骨粗面が戻らず、固まってしまったりします。
また、リハビリが不十分で、動作の改善ができておらず、オスグッド・シュラッター病が再発してしまう方もいます。
膝にかかる負担を減らすためにも、動作改善は必要不可欠です。
もし、今、オスグッド・シュラッター病で悩んでいる方がいれば、しっかりリハビリや運動指導のできる、病院に行くことをおすすめします。
緑橋駅の近くに住む方は、カラダの説明書にご相談ください。
国家資格を持って、スポーツ医療に特化した整骨院で、働いていたトレーナーがお客様にあった、治療やトレーニングプランをご提案いたします。