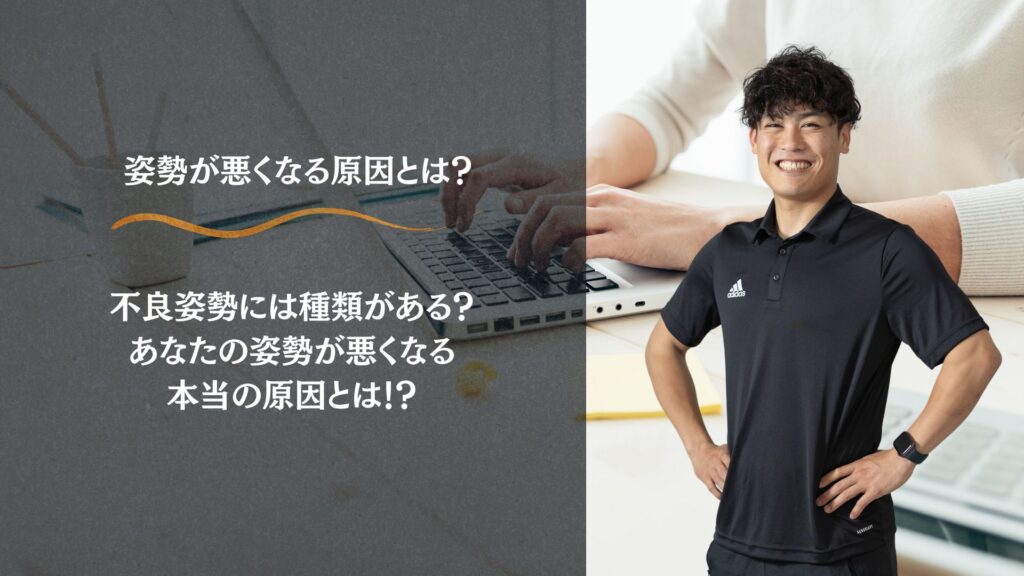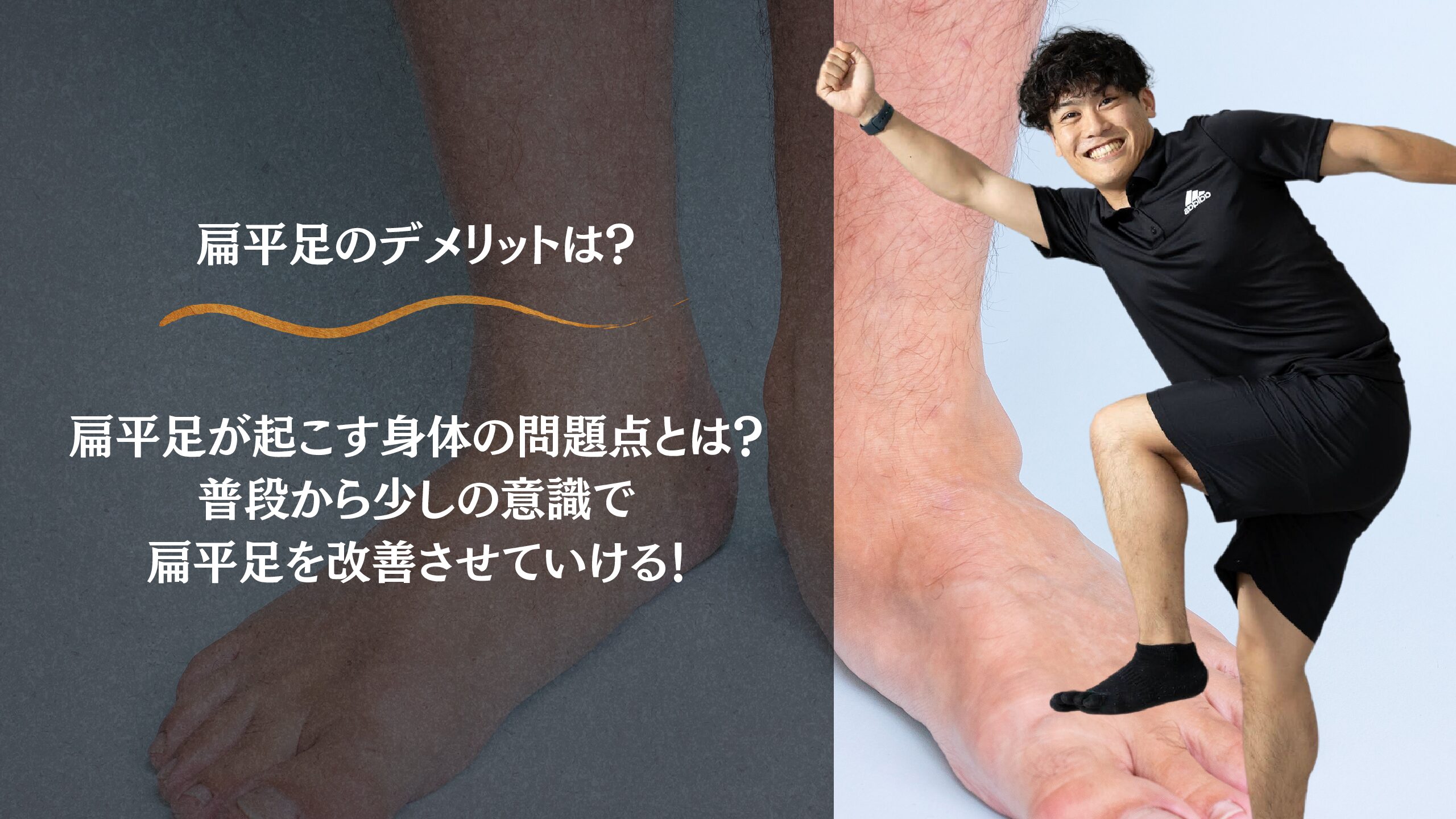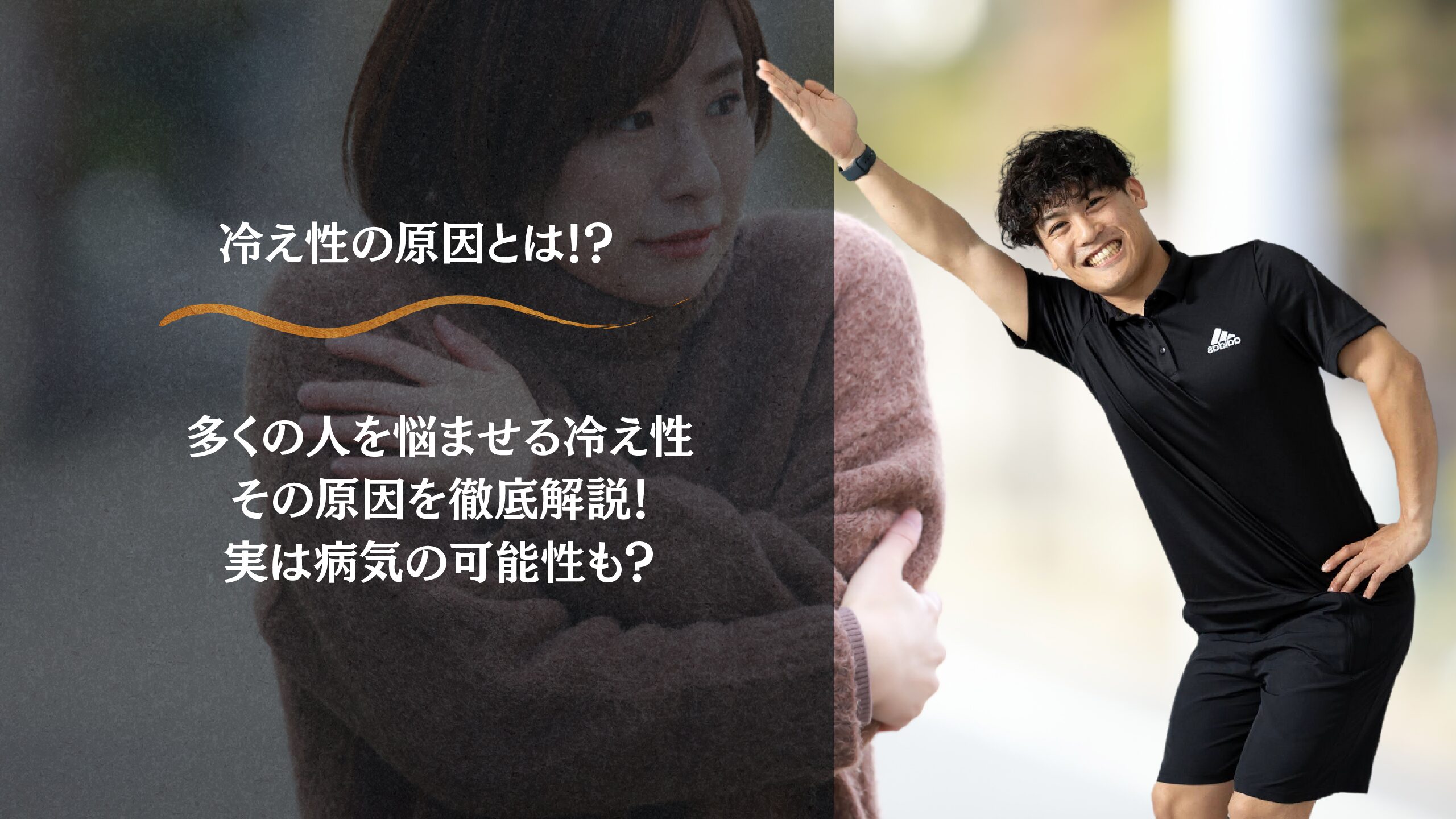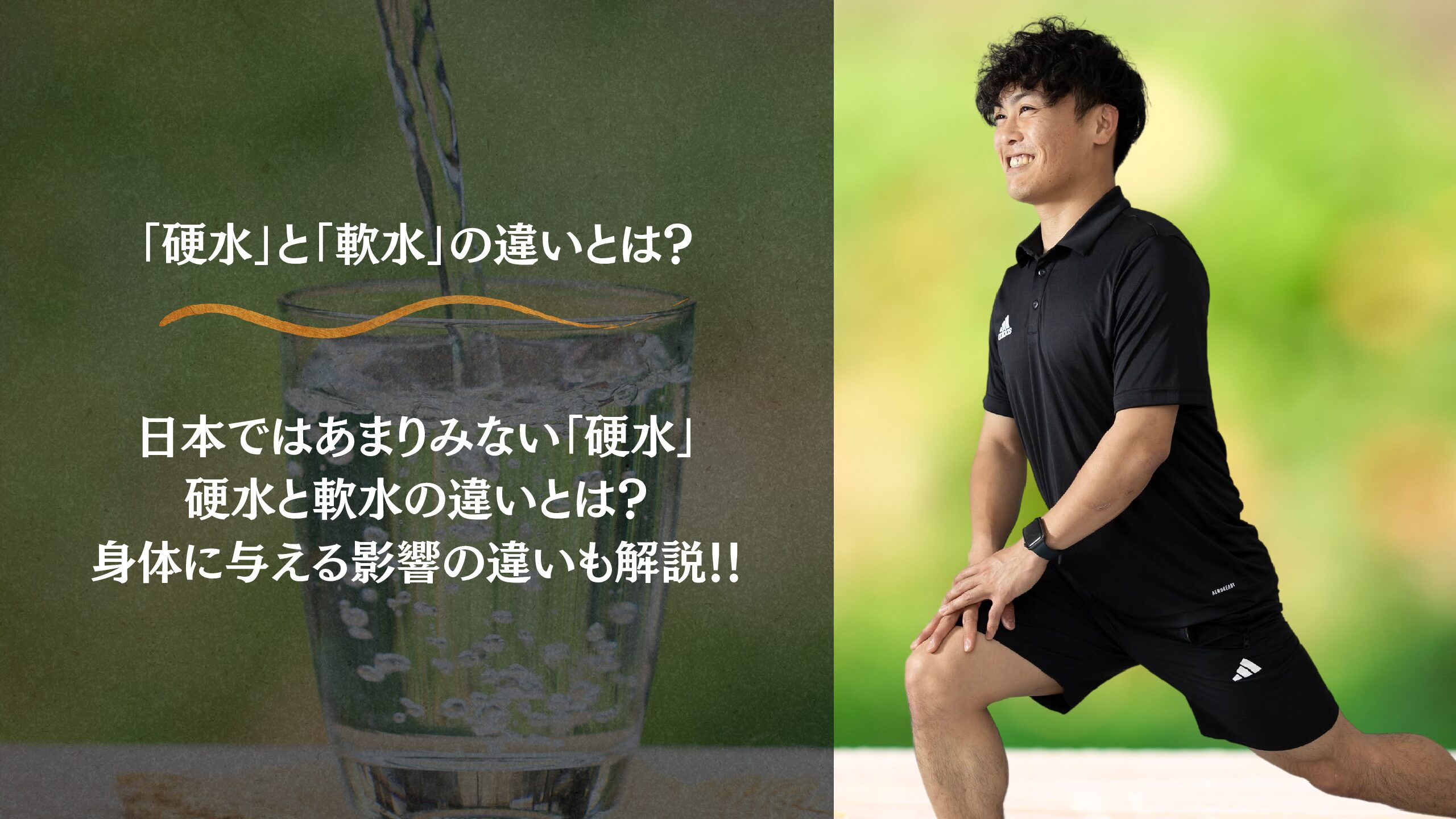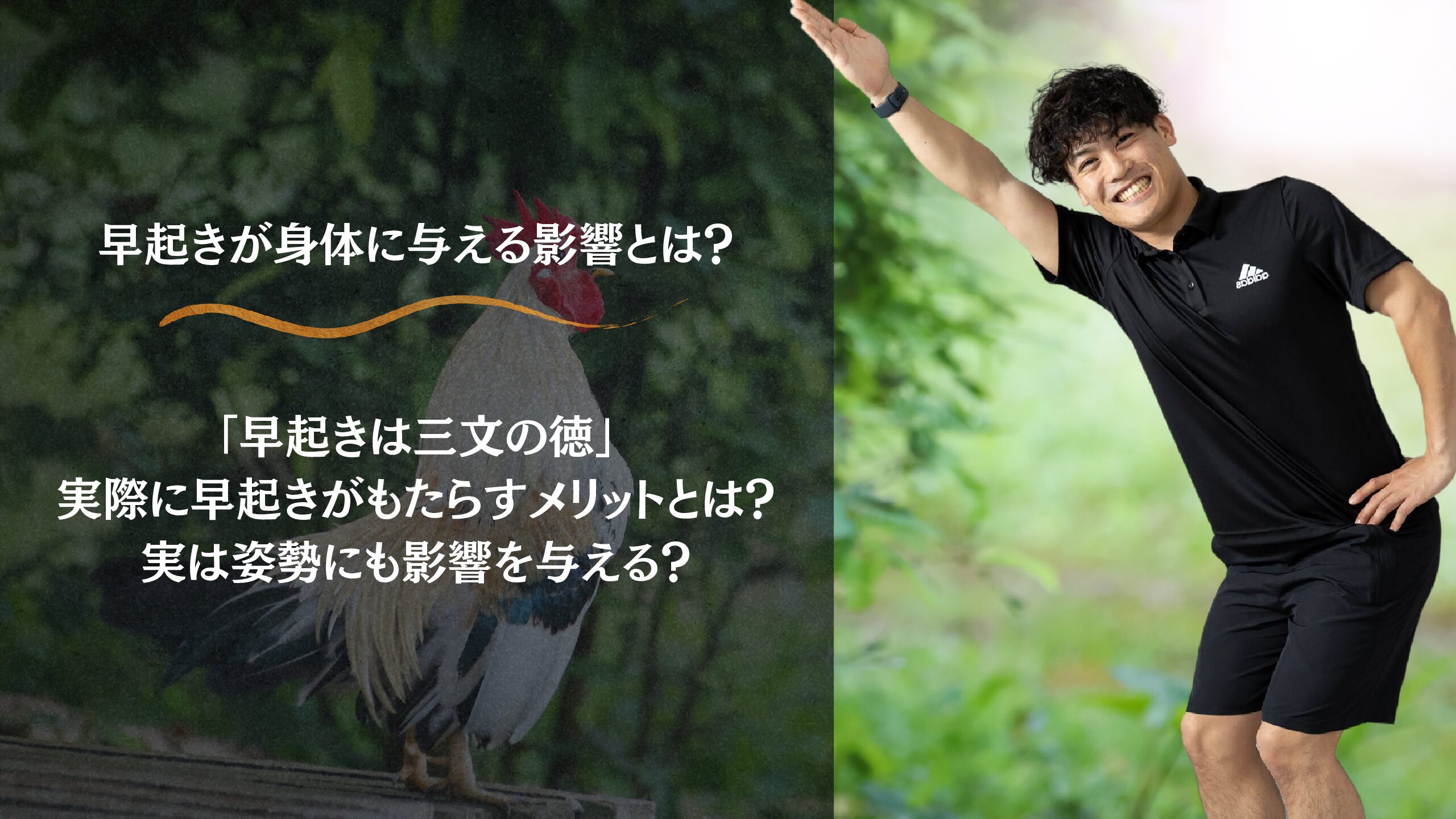【呼吸が浅いとストレスが溜まる!?】呼吸を深くする方法とは?
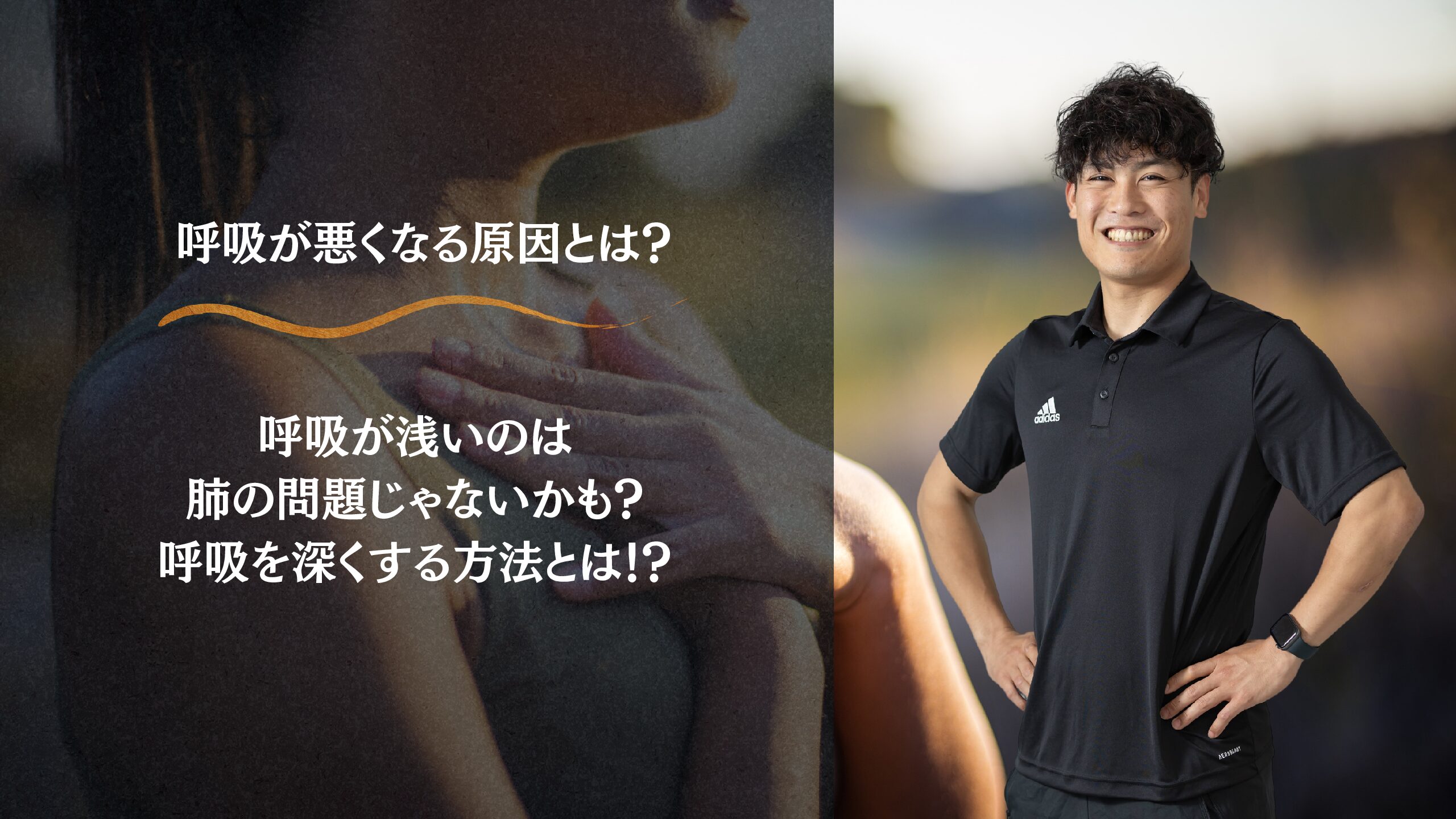
こんにちは!大阪市城東区【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。
みなさんは呼吸が浅いなと思ったことはありますか?
自分ではなんとも思っていなくても、ストレスや疲労が溜まっている人は知らない間に呼吸が浅くなっていることもあります。
呼吸は浅くなってしまうことで自律神経が乱れてストレスが溜まりやすくなったり、睡眠の質が低くなったりしてしまいます。
今回はそんなみなさんに身近で、生きている限り絶対し続ける【呼吸】について解説していきます。
- 呼吸が浅くなる原因は?
- 呼吸を深くするためには?
この記事を読んでみなさんの悩みが少しでも解決に迎えば幸いです。
呼吸が浅くなる原因は?
別に意識しているわけではないのに、知らない間に呼吸が浅くなってしまう。
これには原因があります。
呼吸が浅くなってしまう原因は大きく分けて2つになります。
- ストレス
- 姿勢
今回はこの2つについてお話していきます。
ストレス
呼吸は自律神経という神経が大きく関わってきます。
この神経はさらに交感神経と副交感神経に分かれます。
呼吸はこの2つの自律神経がバランスよく働くことで正常に保たれています。
しかし、今の日本はとてもストレスの多い国になっており、長時間の仕事や膨大なタスクにより睡眠時間も短く、ゆっくりと時間を取ることが難しくなっています。
それにより交感神経のバランスが乱れてしまい、浅い呼吸になりやすくなってしまいます。
姿勢
みなさんが呼吸するときにはおそらく、胸やお腹が一番大きく動いているかと思います。
人間は呼吸をする時は横隔膜が動き、それにより肋骨が開いていきます。
しかし、巻き肩や猫背になってしまうと肋骨や胸の動きが悪くなってしまい、本来よりも息が吸いづらくなってしまいます。
その結果、最後まで息が吸えず呼吸が浅くなってしまいます。
実際にその場で巻き肩にして背中を丸めてみてください。
その状態で大きく息を吸おうと思ってもなかなか吸えないかと思います。
それぐらい呼吸にとって姿勢は大事なものになります。
呼吸を深くするためには?
日常には呼吸が浅くなってしまう要因がたくさんあります。
しかし、呼吸が浅くなっていたとしても改善する方法もしっかりあります。
- 運動
- 姿勢を改善する
少しでも呼吸が浅くなっているなと感じた方はぜひ次から紹介する方法を試してみてください!
運動
呼吸を深くするために僕が1番、みなさんにおすすめするのは「運動」です。
理由は運動することによって得られる効果にあります。
運動には
- リラックス効果
- 血流改善
- 心肺機能向上
などたくさんの効果があります。
運動のリラックス効果とは運動をすることによって頭がすっきりしたり、分泌されるホルモンによって気分を前向きにしてくれたりします。
それがストレスの軽減につながり自律神経を整え、呼吸を深くしてくれます。
また運動をすることによって血流や心肺機能も上がるためそれにより呼吸が深くなることも期待できます。
ストレスなどによって呼吸が浅くなっている方は、騙されたと思って運動を続けてみてください!
- やり方がわからない
- なかなか続けられない
- 身体に痛みがあってできない
などの悩みがある方は一度お気軽にご相談ください!
姿勢を改善する
姿勢改善も呼吸を深くする重要な要素になります。
どれだけ自律神経を整えたとしても、身体が丸くなっているままではうまく息を吸うことができません。
姿勢を整えることで肋骨や胸の動きが良くなり、息を大きく吸うことができるようになります。
この姿勢改善をするためにも運動は重要になってきます。
しかし、闇雲にやっていても姿勢を改善させることは難しいです。
この記事の下に姿勢を改善させるための方法や、重要な要素をまとめた記事のURLを貼ってあります。
姿勢が気になる方はぜひ読んでみてください!
最後に
呼吸を深くしていくためには「姿勢」と「運動」の2つはとても重要な要素になってきます。
この2つをしっかり自分に合った内容で改善していくことで、目一杯大きく息を吸えるようになってきます。
運動内容や姿勢改善の方法も人によって内容は変わるため、もし気になる方はカラダの説明書にご相談ください。
お待ちしております!